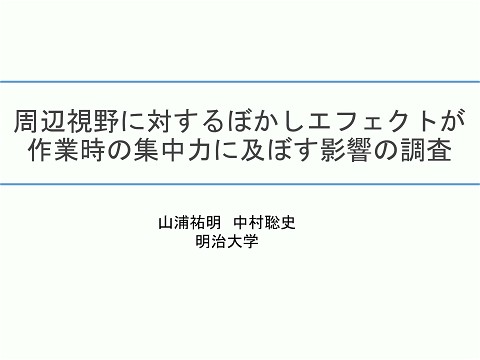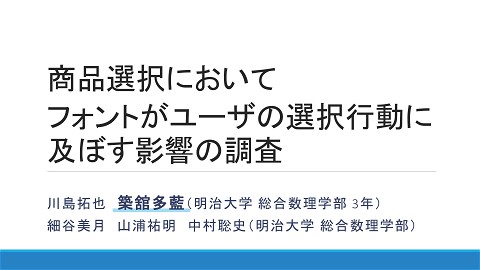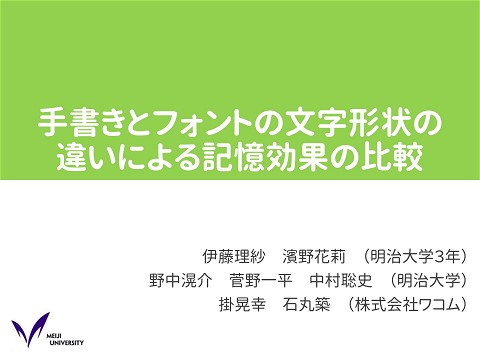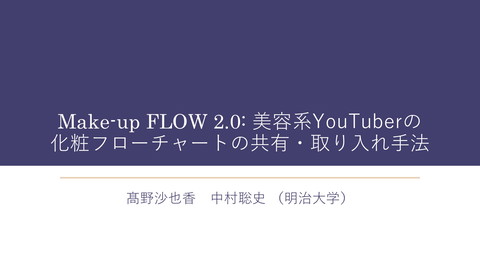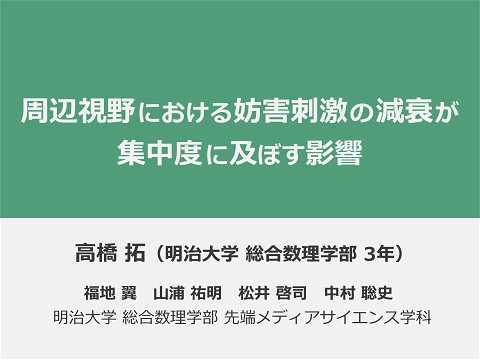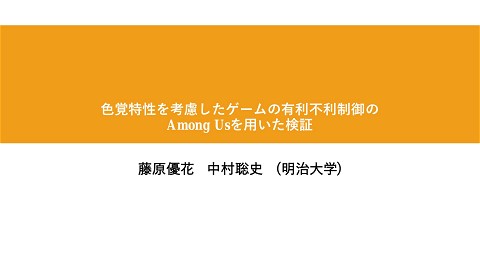視線に連動したぼかし深度制御を用いた単語の記憶容易性向上システムの開発と検証
1K Views
March 07, 25
スライド概要
記憶は,人間の経験や知識を蓄積し,それを活用する能力の中核をなす重要な要素である.しかし,そのために主に行われている繰り返し学習には多くの労力と時間がかかってしまうという問題がある.我々は過去の研究にて,視線に連動して記憶対象文字列の読みやすさが変化する流暢度制御手法を提案し,実際に提案手法がハイライトを与える比較手法と比べて単語の記憶容易性を向上させることを明らかにした.しかし,これまでの実験では主に特徴記憶実験という形式を用いて行っており,情報が箇条書きで提示されていたりあらかじめ出題箇所に手法が付与されている状態であったりと実際の記憶学習とは乖離のある条件で実験を行っていた.そこで本研究では,重要だと思った箇所を自身で選択し,ぼかしによるマーキング可能とするシステムを作成し,より実環境に近い設計のもと実験を行った.その結果,実環境に近い設計でも視線に連動したぼかし深度制御を利用した場合の方がハイライトを利用した場合よりも点数が高くなることが明らかになった.
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科 中村聡史研究室
関連スライド
各ページのテキスト
視線に連動したぼかし深度制御を用いた 単語の記憶容易性向上システムの開発と検証 青木柊八 (明治大学 中村聡史 先端数理科学研究科)
• 高橋京介. いちばんやさしい 基本情報技術者 絶対合格の教科書 + 出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ). SBクリエイティブ, 2024. 2
• 高橋京介. いちばんやさしい 基本情報技術者 絶対合格の教科書 + 出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ). SBクリエイティブ, 2024. 3
背景 • 記憶は学習において重要な要素である 記憶という行為は容易ではない • 暗記をする際には短期記憶を長期記憶に 昇華させる必要がある 繰り返し学習には多くの時間と労力がかかる 4
背景 • 学習効率を上げることで 少ない繰り返し学習でより多くの暗記が行える • 単語の記憶容易性が向上する手法は いくつか存在する • ハイライトなどで単語を目立たせる • 赤ペン・赤シートなどで復習をしやすくする 5
背景 • 学習効率を上げることで 少ない繰り返し学習でより多くの暗記が行える 単語の記憶容易性が向上する • 単語の記憶容易性を向上させる手法は 効果として知られている いくつか存在する • ハイライトなどで単語を目立たせる 非流暢性効果に着目 • 赤ペン・赤シートなどで復習をしやすくする 6
関連研究:非流暢性効果 • 文字の流暢度が低ければ低いほど 記憶容易性が高くなる効果(=非流暢性効果) • 文字色を薄くして流暢度を低くすることで 記憶保持力が向上する[Oppenheimer 2011] • Oppemheimer, D. M., Diemand-Yauman, C., Vaughan, E. B.. Fortune favors the bold (and the italicized): Effect of disfluency on educational outcomes. Cognition. 2011, vol. 118, no. 1, p. 111-115. 7
関連研究:非流暢性効果 • 人の視線は低解像度の部分から 高解像度の部分に誘導される[Hata 2016] →非流暢性効果を狙いつつ,視線に連動した変化で 単語への注視を行わせる手法の検討 視線に連動したぼかし深度制御の提案 • Hata, Hajime, Hideki Koike, and Yoichi Sato. "Visual guidance with unnoticed blur effect." Proceedings of the International Working Conference on Advanced Visual Interfaces. 2016. 8
提案手法 記憶対象文字列に ぼかしを付与 ↓ 視線を向けると かかっているぼかしが 段階的に弱まる 9
これまでの研究(HCI201、MVE2023) • 実験結果 • 提案手法を利用した際の方がなにもない条件よりも 単語の記憶容易性を向上させられる • 提案手法を利用した際の方がハイライトを利用した 際よりも単語の記憶容易性を向上させられる • 青木 柊八, 髙野 沙也香, 中村 聡史. 視線に連動した記憶対象文字列への非流暢性制御による記憶容易性向上手法, 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI), Vol.2023-HCI-201, No.2, pp.1-8, 2023. • 青木 柊八, 髙野 沙也香, 中村 聡史. 視線に連動した記憶対象文字列へのぼかし深度操作による記憶容易性向上手法のより多角的な調査, 信学技報, Vol.123, No.433, MVE2023-44, pp.13-18, 2024. 10
目的 目的 視線に連動したぼかし深度制御手法を利用した 学習支援システムの実装・検討 11
実際の暗記学習環境への応用 • 視線に連動したぼかし深度制御の 有用性は示された • 実際の暗記学習に適用するために必要なこと • 既存の教科書やノートに利用可能 • 重要な箇所を自身で選定可能 12
特徴記憶実験 • これまでの研究で利用した 記憶実験設計 • 架空の生物や物体の特徴を 覚えてもらう • 特徴は箇条書きで書かれている • 重要箇所はあらかじめ選定 固有名詞 7つの 特徴 13
提案システムの利用実験 • 提案システムの有用性を利用実験で調査 • 過去の実験からの変更点 • 教科書やノートは文章形態で表記されている →特徴記憶実験を文章形態に調整 • 重要な箇所はユーザ自身が選定する必要がある →ユーザ自身が重要だと考えた箇所を選定可能に 14
提案手法を用いた学習支援システム • 重要だと思った箇所をドラッグ&リリース することでぼかしを付与するシステム 15
実験協力者 • 実験協力者は大学生及び大学院生16名 (男性12名,女性4名) • テストの点数が平均±2SDに含まれない者は いなかったため,除外はなし 16
比較手法 • 比較手法としてハイライトでの強調を利用 • 実際の学習でも利用される 17
テーマ • 生物系:恐竜、絶滅危惧種 • 従来の特徴記憶のような ある生物・物に関する特徴を解説 • 物語系:小説、映画 • 従来の特徴記憶とは違い 話の流れ込みで特徴を説明する 18
実験設計:1セットの流れ 19
実験設計:実験の流れ • 1回のセット内で2テーマを同時に記憶 • 同じ系統のテーマを同時に記憶 • テストによるマーキングへの影響を考慮 • 各フェーズを交互に行う • セット内のマーク手法は別に設定 • 片方は提案手法、もう片方は比較手法でマーク • 順番は基本ランダム、2セット目は1セット目の逆順 20
実験設計:マーキングフェーズ • 3分間提示された記憶対象の重要だと思った箇所に 提案手法か既存手法でマーキングを行う 21
実験設計:記憶フェーズ • マークした記憶対象を追加で2分間記憶する 22
実験設計:パズルフェーズ • 15分間の休憩時間を用意 • 簡単にできる単純作業として 15分の間パズルを行う • 特徴の記憶維持に意識を向けさせない • 基本は達成できない難易度に設定 23
実験設計:テストフェーズ • 1問5点の計20問を出題 • それぞれの特徴を 回答してもらう形式 • 架空の名称は 変化の小さい4択形式に 24
実験設計:実験の流れ(全体) 25
実験結果 • 提案手法群 →41.4点 • 比較手法群 →35.2点 →提案手法を利用した際の 方が点数が有意に高くなる 26
実験結果:テーマ系統別 生物系:提案手法の方が有意に高い 物語系:提案手法の方が高い 27
実験結果:マークされた箇所の分析 各手法のマークされていた箇所と マークされていなかった箇所の平均単語数と 標準偏差(括弧の中が標準偏差) 28
実験結果:マークされた箇所の分析 マークされていた箇所と されていなかった箇所における正答率の平均 マークされていた箇所に関しては提案手法の方が 正答率が高かった 29
実験結果:不快感に対するアンケート 5段階のリッカート尺度 (1:とても弱い~5:とても強い)で回答 30
実験結果 • 実験結果 • 提案手法を利用した際の方が既存手法を利用した 場合よりも単語の記憶容易性を向上させられる • 特に生物系のテーマにおいては高い効果があった • 提案手法を利用した際の方が マークされた箇所に対する正答率が高くなる 31
まとめ • 背景:記憶学習の難易度の問題 • 提案手法:視線に連動したぼかし深度制御を組み込んだ暗記支 援システム • 暗記学習支援システム:重要箇所をなぞることで提案手法を付 与 • 結果:提案手法の方が有意に効果的 32