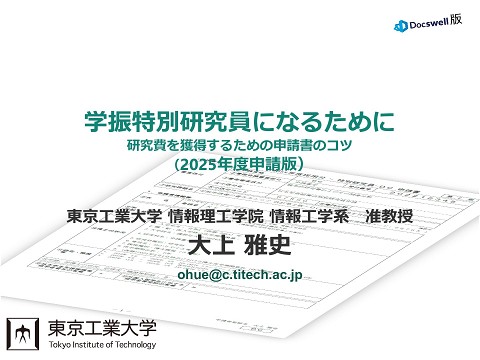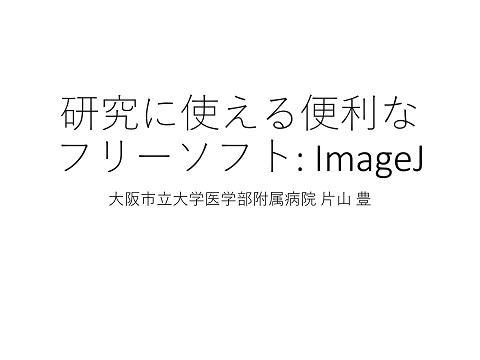「行為する意識」 (2025年9月9日開催 CHAINシンポジウム講演のスライド)
7.6K Views
September 29, 25
スライド概要
2025年9月9日に開催されたCHAINシンポジウムでの講演「行為する意識」のスライドです。
詳しいことはこちらのブログ記事からどうぞ: https://pooneil.sakura.ne.jp/archives/permalink/001770.php
講演は、2025年5月に出版された著書「行為する意識: エナクティヴィズム入門」(吉田正俊+田口茂)に沿った内容となっています。意識に関する研究の流れを追いながらそこにある問題を指摘し、それを克服するための方策として、予測的処理、エナクティヴィズム、神経現象学について説明します。そのうえで、「脳の過程と意識の過程の絡み合い」という考えを提案して、著者なりの神経現象学を提案しています。
なお、書籍で使用している図については、CC BY4.0ライセンスを採用しています。
吉田 正俊 (Masatoshi Yoshida) 北海道大学 人間知・脳・AI研究教育センター(CHAIN) A neuroscientist and a campfire guitarist. https://www.chain.hokudai.ac.jp/members/pooneil/ https://bsky.app/profile/pooneil.bsky.social
関連スライド
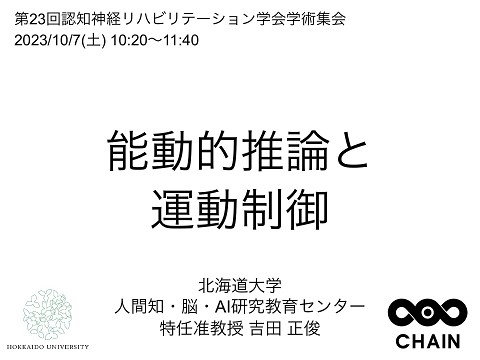
能動的推論と運動制御

ZAZA株式会社_会社紹介

StampFlyで学ぶマルチコプタ制御
各ページのテキスト
CHAINシンポジウム 2025年9月9日(火) 15:00-16:00 行為する意識 北海道大学 人間知・脳・AI研究教育センター 教授 吉田 正俊
「行為する意識: エナクティヴィズム入門」 書評 読売新聞 6/29 (為末大) ダ・ヴィンチ 8月号 週刊読書人 8/29 http://www.seidosha.co.jp/book/index.php?id=4026
本講演の構成 著書「行為する意識: エナクティヴィズム入門」 に沿って説明 + その後のアップデート 講演時間は~45分くらいを予定 そのあとで質疑応答 「行為する意識」から引用した画像のライセンス: 吉田 正俊 CC BY 4.0 または 田口 茂 CC BY 4.0
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
何についての本? 「意識を理解するとは?」 「脳と意識の関係」についての本。
特色1: 神経科学者 x 現象学者 吉田 正俊 (北海道大学) 田口 茂 (北海道大学) 科学者 (神経科学) 哲学者 (現象学)
特色2: エナクティヴィズム 特色3: 予測的処理の見直し
結論はなに? 「脳の状態と意識の状態の対応づけ」から 「脳の過程と意識の過程の絡み合い」へ 時間 脳の状態 意識の状態 B1 C1 B2 C2 B3 C3 脳の 過程 互いが互いを 可能にする 意識の 過程 行為的媒介 (本書 図6-6)
結論はなに? 「脳の状態と意識の状態の対応づけ」から 「脳の過程と意識の過程の絡み合い」へ 脳の状態 意識の状態 B1 C1 脳の 状態 B1 B2 C2 B2 B3 時間 B3 C3 脳の 過程 意識の 過程 b c 意識の 状態 C1 C2 C3 (本書 図6-6)
I章 表象することから自律性へ ──意識は外界のコピーではない 意識の科学の現状: 脳状態-意識状態 の対応づけ 自律性とは? VI章 意識の謎に挑む 脳過程-意識過程 の絡み合い 神経現象学 + 予測的処理 V章 エナクティヴィズム ――行為的媒介による相互決定 II章 自律性とはなにか ──開きつつ閉じている、われわれと環境 自律性: オートポイエーシス 生命と精神の連続性 III章 世界を経験するとはどういうことか ──切ることによってつながる、行為による媒介 「因果」から「媒介」へ 自律性 = 行為的媒介 差異を 消費する 予測=遡言 =意味づけ エナクティヴィズム IV章 「予測」を展開する 予測誤差 最小化 自由 エネルギー 原理 生物にとっての予測とは? (本書 p.18の簡略版)
I章 表象することから自律性へ ──意識は外界のコピーではない 意識の科学の現状: 脳状態-意識状態 の対応づけ 自律性とは? VI章 意識の謎に挑む 脳過程-意識過程 の絡み合い 神経現象学 + 予測的処理 V章 エナクティヴィズム ――行為的媒介による相互決定 II章 自律性とはなにか ──開きつつ閉じている、われわれと環境 本講演では 差異を 予測=遡言 自律性: オートポイエーシス 消費する =意味づけ 要点をかいつまんで説明します。 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム 詳しいことは本を読んでください。 III章 世界を経験するとはどういうことか ──切ることによってつながる、行為による媒介 「因果」から「媒介」へ 自律性 = 行為的媒介 IV章 「予測」を展開する 予測誤差 最小化 自由 エネルギー 原理 生物にとっての予測とは? (本書 p.18の簡略版)
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
つか意識ってなに? Don’t think, just feel.
ハーマングリッド Hermann Grid を例に。 図の初出: 立命館大学 北岡明佳教授のFacebook (2016/9/11) https://www.facebook.com/photo.php? fbid=10207806660899237&set=a.2215289656523.118366.1076035621&type=3
差し替え
眼(網膜)に映っているものすべてを 「意識経験」として持っているわけではない。 「意識を科学的に研究する」 というときには このような意識の内容物contentが 対象となってきた。
NCCプロジェクト (1990年代あたりから) フランシス・クリック: いまこそ意識研究を始める機会である。 そのためのストラテジーとして • 視覚意識に注力する (いちばんよく研究されているから) • 第一歩として「意識の神経相関 (Neural correlates of consciousness: NCC)」を探索する Crick F. Astonishing hypothesis Crick F. and Koch C. (1990) Towards a neurobiological theory of consciousness. Seminars in Neuroscience Vol. 2, 263–275.
意識の神経相関 (NCC) クリックとコッホ (1990) が提唱 Crick F. and Koch C. (1990) Towards a neurobiological theory of consciousness. Seminars in Neuroscience Vol. 2, 263–275. 意識に相関がある神経活動(NCC)とは、 特定の現象としての意識状態を生じさせるのに 十分な最小限の神経活動 https://en.wikipedia.org/wiki/Neural_correlates_of_consciousness#/ media/File:Neural_Correlates_Of_Consciousness.jpg, CC BY-SA 3.0
視覚的気づき(awareness)に関連する脳活動 右脳 左脳 両眼視野闘争 外側 差し替え 差し替え 内側 Lumer ED, Friston KJ, Rees G. (1998) Neural correlates of perceptual rivalry in the human brain. Science. 280(5371):1930-4. 「意識」を「視覚的気づき」(=「顔が見えた」という報告) に置きかえて検証。 脳の側頭葉、頭頂葉、前頭葉のさまざまな部位が活動した。 => 意識には脳のネットワーク活動が重要そう。 => NCCプロジェクトは一定の成功をみた。
意識の理論についての論争: Nature (2025) 結果の事前予測: 2つの意識の理論が 白黒つけるために 共同で検証実験 • グローバル神経ワークス ペース理論 (GNWT) • 統合情報理論 (IIT) 結果の事前予測: 差し替え 予測1 意識内容のデコード • GNWT: prefrontal ROIから • IIT:posterior ROIから 実際の結果: 結果1: 両方を支持 Cogitate Consortium., Ferrante, O., Gorska-Klimowska, U. et al. (2025) Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. Nature. 642(8066):133-142
神経表象説 神経表象説 われわれの意識は こんな受け身の図式で 説明できるものだろうか? 「見る」とは 神経表象を作ること 神経表象説: 「心的表象をもつ =脳が外界に関する 表象状態を実現する」 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」V章 p.207
脳と心の関係の図式 神経表象説 予測的処理 / 無意識的推論 「見る」とは 神経表象を作ること 「見る」とは 外界の状態を推定すること 神経表象説: 「心的表象をもつ =脳が外界に関する 表象状態を実現する」 逆向きで考える 受け身ではない積極的な役割を重視 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」V章 p.207
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
予測誤差最小化理論 予測誤差 ユニット 予測誤差 ユニット 予測ユニット 予測ユニット 予測誤差 ユニット 予測ユニット 予測誤差 ユニット 感覚入力 神経ネットワークを 予測するユニットと 予測誤差を送るユニット の組み合わせと捉える 人工神経ネットワーク の分野では PredNetなどで実装 https://en.wikipedia.org/wiki/ File:Emotions_according_to_the_Atlas_of_Personality,_Emotion_and_Behaviour.svg
予測誤差最小化理論 予測誤差 ユニット 予測ユニット 予測誤差 ユニット 予測ユニット 予測誤差 ユニット 予測ユニット 「意識的な状態とは、 感覚入力を 現在のところ もっとも良く 予測するような、 外界の表象である」 ヤコブ・ホーヴィ (2021) 予測する心. 勁草書房 予測誤差 ユニット 感覚入力
両者とも一方通行であり、二元論的 神経表象説 「見る」とは 内的表象を 作ることである 無意識的推論 「見る」とは 外界の状態を 推定すること 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.207 両者とも 表象主義の一種 ホーウィは意識の表象 主義の立場から、無意 識的推論での信念が表 象であると考える。心 は脳に閉じ込められて いることを強調する。 ヤコブ・ホーヴィ (2021) 予測する心. 勁草書房
「制御された幻覚」という考え 差し替え 「今ここで 起きている知覚もまた 幻覚みたいなものです。 ただしそれは、 制御された幻覚」 https://www.ted.com/talks/ anil_seth_your_brain_hallucinates_your_consci ous_reality 「主体が外界を一方的に構築する」 という考えに基づいている。 吉田(と田口)はこれには同意しない。 アニル・セス (2022) なぜ私は私であるのか: 神経科学が解き明かした意識の謎.青土社
エナクティヴズム 表象説 無意識的推論 エナクティヴズム 「見る」とは 内的表象を 作ることである 「見る」とは 外界の状態を 推定すること 「見る」とは 知覚的に導かれた行為 のことである エナクティヴィズムでは知覚と行為の双方向性の作用を重視する。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.207
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
エナクティヴィズム Enactivism 神経生理学者/人工生命学者のVarelaは、 彼のオートポイエーシスと自律性の考えを発展させて、 Enactiveアプローチを提案した。 Enact (役を演ずる) => 「行為からの産出」 Enactivismの定義 (p.246): 「知覚とは、知覚的に導かれた行為のことである」 Perception consists in perceptually guided action. World mutually specify Agent (意図的に再帰的な定義 になっていることに注意) フランシスコ・ヴァレラ、エヴァン・トンプソン、エレ ノア・ロッシュ (1991) 身体化された心 仏教思想からの エナクティブ・アプローチ. 工作舎 (日本語訳 2006)
エナクティヴィズムとは 表象主義 古典的表象主義 pre-given World cast image recover = represent Agent Cognition as the recovery of a pregiven outer world エナクティビズム World mutually specify Agent Cognition as embodied action ヘルムホルツの無意識的推論 pre-given World project = represent Perception consists in perceptually guided action. Agent Cognition as the projection of a pregiven inner world Varela F. J., Thompson E. & Rosch E. (1991) The embodied mind: Cognitive science and human experience. MIT Press, Cambridge. p.172-173
生物の自律性、生命と精神の連続性 エナクティヴィズムを理解するために、 • 生物の自律性 • 生命と精神の連続性 について説明を行う。 意識の問題についてはそのあとまた戻る。
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
生きているとはどういうこと? 神経生理学者のマトゥラーナとヴァレラは 1) 代謝 2) 膜 に注目した。 (遺伝や生殖も重要だが、 ここではある時点で「生きている」が実現する条件 に注目している。)
生命に必須なもの1: 代謝 例: クエン酸回路 細胞内代謝の「自己触媒セット」 が閉回路になって 「自分で自分を維持している」 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.78
生命に必須なもの2: 膜 崩壊していくミドリゾウリムシ 差し替え 膜が壊れると 生命が壊れる 膜があることで 代謝が可能になる 膜は自他を区切り、 環境との相互作用の インターフェースになる 崩壊していくミドリゾウリムシ https://www.youtube.com/watch?v=Qkm-a8bZdIk 差し替え
生きているとはどういうこと? そこでは膜の中で代謝が維持される という意味で「閉じている」が、 それと同時に膜を通じて外界と相互作用をする という意味で「開いている」。 このような「開きつつ閉じる」という 生物特有の自律性 autonomy に注目する。
オートポイエーシス: 自律性の実現 生命システムのorganization(組織としての特性)とはなにか? これに対する答えが「オートポイエーシスautopoiesis」。 Autopoeisis = Auto (自己) + poiesis (制作) = 自己を産出する 元の定義はややこしすぎるので、後年の説明を採用する。 オートポイエーシスとは、 操作的閉包 + 構造的カップリング だ。 マトゥラーナ、バレーラ (1980)『オートポイエーシス — 生命システムとは何か』河本英夫訳、国文社 (日本語訳1991)
単細胞生物におけるオートポイエーシス 細胞膜の 空間配置 過程 process 細胞内代謝が可能な 物質濃度を保つ 互いが互いを 可能にする 構造的 カップリング 外界との 相互作用 操作的閉包 物質、エネルギー の流入出 細胞内代謝 ネットワーク 過程 process A C B 細胞膜の材料を産生 オートポイエーシスの条件: • 操作的閉包 - 閉じていること (組織構成) • 構造的カップリング - 開いていること (構造) • 組織構成: 抽象的な変換関係 (代謝が「閉じて」いる) • 構造: 具体的な関係 (代謝を担う個々の化学反応) Varela FJ. (1997) Patterns of life: intertwining identity and cognition. Brain Cogn. 34(1):72-87. Di Paolo, E., & Thompson, E. (2014). The enactive approach. In L. Shapiro (Ed.), Routledge handbooks in philosophy. The Routledge handbook of embodied cognition (p. 68–78). Routledge/Taylor & Francis Group.
単細胞生物におけるオートポイエーシス 細胞膜の 空間配置 過程 process 細胞内代謝が可能な 物質濃度を保つ 互いが互いを 可能にする 構造的 カップリング 外界との 相互作用 操作的閉包 物質、エネルギー の流入出 細胞内代謝 ネットワーク 過程 process A C B 細胞膜の材料を産生 オートポイエーシスの条件: • 操作的閉包 - 閉じていること (組織構成) • 構造的カップリング - 開いていること (構造) このふたつを通して「開きつつ閉じる」が実現している。 一見矛盾して見える両者は組織構成と構造の違いによって両立可能。 だがそれは予定調和ではなく、生命特有の不安定性 precaliousnessを生み出す。
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
認知する個体における(生物学的)自律性 感覚運動 カップリング 過程 process 構造的 カップリング 外界との 相互作用 操作的閉包 ニューロン間 ネットワーク 過程 process 互いが互いを 可能にする 単細胞生物と同様に、認知する個体も同じ組織構成を持っている。 操作的閉包: [感覚運動カップリング (例: 頭を動かせば網膜像が変わる)] と[ニューロン間ネットワークでの活動の維持]というふたつのプロセスが互 いを可能にしている。 構造的カップリング: 外界との相互作用の歴史によって、生物と外界の調和 的な関係を維持している。(≒ 適応) 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.102
生命と精神の連続性 細胞膜の空間配置 構造的 カップリング 操作的閉包 互いが互いを 可能にする 外界との 相互作用 細胞内代謝ネットワーク A C B 物質、エネルギー の流入出 感覚運動カップリング 構造的 カップリング 外界との 相互作用 操作的閉包 ニューロン間ネットワーク 互いが互いを 可能にする Lifeとmindは同じ組織構成(organization)を持っている。 Varela FJ. (1997) Patterns of life: intertwining identity and cognition. Brain Cogn. 34(1):72-87.
生命と精神が共有する(生物学的)自律性 命題2: 生物で創発した個別性は 「相互作用の領域」の参照枠(視点)を与える。 個別性 Identity 命題1: 生物とは 「個別性identityを 創発する 構築constituteする emerge プロセス」である。 操作的閉包 互いに絡み合ったプロセスが 結果としてそのプロセス を生産する 相互作用の領域 必然的に伴う entail 創発する emerge Intentional link (構造的カップ リングに該当) 参照枠が与えられたこと が、その生物にとっての 意味、価値の源となる 意味、価値 このループが維持される のが(生物学的)自律性 生物は意味を生み出す 認知する個体が意味生成(sense-making)をする。 Varela FJ. (1997) Patterns of life: intertwining identity and cognition. Brain Cogn. 34(1):72-87.
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
エナクティヴィズム Enactivism 神経生理学者/人工生命学者のヴァレラは、 彼のオートポイエーシスと自律性の考えを発展させて、 Enactiveアプローチを提案した。 Enact (役を演ずる) => 「行為からの産出」 Enactivismの定義 (p.246): 「知覚とは、知覚的に導かれた行為のことである」 Perception consists in perceptually guided action. World mutually specify Agent (意図的に再帰的な定義 になっていることに注意) フランシスコ・ヴァレラ、エヴァン・トンプソン、エレ ノア・ロッシュ (1991) 身体化された心 仏教思想からの エナクティブ・アプローチ. 工作舎 (日本語訳 2006)
生命と精神が共有する(生物学的)自律性 命題2: 生物で創発した個別性は 「相互作用の領域」の参照枠(視点)を与える。 個別性 Identity 命題1: 生物とは 「個別性identityを 創発する 構築constituteする emerge プロセス」である。 操作的閉包 互いに絡み合ったプロセスが 結果としてそのプロセス を生産する 相互作用の領域 必然的に伴う entail 創発する emerge Intentional link (構造的カップ リングに該当) 参照枠が与えられたこと が、その生物にとっての 意味、価値の源となる 意味、価値 このループが維持される のが(生物学的)自律性 生物は意味を生み出す 認知する個体が意味生成(sense-making)をする。 これがエナクティヴィズムにおける 「知覚とは、知覚的に導かれた行為のことである」の内実。 Varela FJ. (1997) Patterns of life: intertwining identity and cognition. Brain Cogn. 34(1):72-87.
エナクティヴィズムにおける感覚運動ループを より直接的に知覚の条件として捉えた、 「感覚運動随伴性説 sensorimotor contingency」 について紹介する。
感覚運動随伴性 Sensorimotor contingency (SMC) 例えば、私たちが対象に向かって近づくと対象の姿が 大きくなる。 私たちの知覚能力は、この種の感覚-運動随伴性の所有 によって構成されている。 感覚-運動随伴性の所有: 命題知ではなく技能知。 (例: 自転車の乗り方を 「本で読んで知ってる」 vs. 「乗りこなせる」) アルヴァ ノエ (2010) 知覚のなかの行為. 春秋社
逆さメガネ 左右反転、上下反転が可能。
左右反転メガネをつけっぱなしにすると 装着前 装着直後 順応段階1 順応段階2 目が回る〜 メガネを通して 見える視野 元の視野 視野 メガネ を通して 見える視野 意識 経験 目や頭を動かしたとき 手を伸ばして の視野の変動という ものを掴むなどの SMCに習熟 SMCに習熟 時間
Held and Hein’s experiment Development of vision was normal for active movers but not for passive movers. 差し替え Held R, Hein A. (1963) Movement-Produced Stimulation in the Development of Visually Guided Behavior. J Comp Physiol Psychol. 56:872-876.
Recent studies in support for Held and Hein 差し替え Two mice in a virtual-reality environment 差し替え Attinger A, Wang B, Keller GB. (2017) Visuomotor Coupling Shapes the Functional Development of Mouse Visual Cortex. Cell. 169(7):1291-1302.e14.
この実験から明らかになったこと 視覚野 センサー値 網膜 感覚運動 随伴性 予測誤差 + センサー値の予測 筋肉 運動野 第一次視覚野V1では、運動に関連した活動 (運動からの予測) と 感覚フィードバック (運動の結果)を用いて予測誤差を計算している。 => 感覚運動随伴性の実現には、このような予測と予測誤差最小化 のサイクルが関わっている。 Attinger A, Wang B, Keller GB. (2017) Visuomotor Coupling Shapes the Functional Development of Mouse Visual Cortex. Cell. 169(7):1291-1302.e14.
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
ここで意識の問題に戻る
Neurophenomenology (神経現象学) このようなエナクティブな視点から 意識の問題に取り組んだのが神経現象学。 Q: 意識経験を一人称的かつ誰でも同意できる形で説明する にはどうすればよいか? A: 「経験の構造についての現象学的説明」と 「認知科学におけるその対応物」とは 相互に拘束条件を与えることで関係し合う。 (=>相関よりも強い関係) Varela, F. J. (1996) Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem. Journal of Consciousness Studies 3, 330–349. Varela, F. J. (1999) The specious present: A neurophenomenology of time consciousness in Naturalizing phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Petitot, J., Varela, F. J., Pachoud, B. & Roy, J.-M.) 266–329 (Stanford University Press).
ヴァレラの「神経現象学」 神経生物学的な基盤 相互に 拘束条件 現象学的還元の元での 「生きられた経験」の性質 神経生物学 ここについては skip 現象学 非線形力学 主に非線形力学に基づいた 形式的な描写 Varela, F. J. (1996) Neurophenomenology: a methodological remedy for the hard problem. Journal of Consciousness Studies 3, 330–349. Varela, F. J. (1999) The specious present: A neurophenomenology of time consciousness in Naturalizing phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Petitot, J., Varela, F. J., Pachoud, B. & Roy, J.-M.) 266–329 (Stanford University Press).
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
行為的媒介と観察的媒介 現象学者の田口茂(共著者)は 「媒介」の概念を使って、脳と意識の関わりかたを表現する。 私から見た主観的世界はどこまでいっ ても主観的世界だが、同時にわれわれ はその外があることも知っている。 この意味で、主観的世界と外的世界の 間には境界線はない。 われわれは「境界線を引く」 という操作(観察)ではなくて、 「行為」によって その見えない境界を乗り越えている。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.129
行為的媒介と観察的媒介 このような異なる関わり方 (「観察」と「行為」)を表現するために、 田辺元の「媒介」の概念を援用する。 媒介とは: 1) AなしにはBはない 2) 切ることによってつなぐ (媒介は因果(AがBを生み出す)ではない) われわれは「境界のない外」と行為的に 関わっている => 行為的媒介 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.129
「脳の状態と意識の状態の対応付け」という前提 意識の神経表象説も予測的処理も、二元論を暗黙に前提としている。 そこでは脳のstateと意識のstateの同型isomorphismを前提としている。 脳のstateと意識のstateの対応づけ問題 (explanatory gap)に直面する。 これがハードプロブレムの元凶。 脳の状態 時間 意識の状態 B1 C1 B2 C2 B3 C3 意識のハードプロブレム: why and how do physical processes in the brain give rise to conscious experience? (Chalmers)
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」という発想 そこで吉田と田口は発想を転換して、 脳の過程processと意識の過程processが絡み合いの関係にある、 という描像を提案する。 脳の状態 時間 意識の状態 B1 C1 B2 C2 B3 C3 脳の 過程 互いが互いを 可能にする 意識の 過程 われわれは「境界のない外」と行為的 に関わっている。 「脳の過程と意識の過程の絡み合い」 とはこのような行為的媒介。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.207
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」という発想 そこで吉田と田口は発想を転換して、 脳の過程processと意識の過程processが絡み合いの関係にある、 という描像を提案する。 脳の状態 意識の状態 B1 C1 脳の 状態 B1 B2 C2 B2 B3 脳の 過程 意識の 過程 b c 意識の 状態 C1 C2 C3 時間 B3 C3 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.207
状態と過程: クエン酸回路で考える 「実体(状態)が 因果によって結ばれる」 「過程が他の過程を可能にする (可能化条件=行為的媒介)」 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.295
状態と過程: クエン酸回路で考える 過程 (化学式) クエン酸 cis-アコニット酸 + 水 状態 クエン酸の濃度など 可能化関係 cis-アコニット酸 + 水 D-イソクエン酸 可能化関係とは非自明な物理的な制約のことだ。 過程と過程の関係は可能化関係であり、 数式で明示的に表現されていない非自明な物理的制約、 もしくは物質性やオープンエンド性が入り込む。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.285
状態と過程: 神経細胞の活動で考える 一つの神経細胞の活動は力学系として取り扱う。 神経活動は膜電位Vとカリウム電流IKの状態空間で表現される。 状態空間の中での時間発展は、微分方程式という過程で表現できる。 神経の連続発火はアトラクターとして表現される。 力学系モデル 実際の神経活動 IK V INa I t dV = f(V, IK ) dt 0.6 V R = 250Hz IK dIK = g(V, IK ) dt NNの形式ニューロン 0.0 I R = f(I) -80 R 0 V 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.110
状態と過程: 神経細胞の活動で考える 高次の状態 (パラメーター) 0.6 I, gNa, gK, . . . IK 0.0 状態 -80 0 V V, IK 過程 (微分方程式) dV = f(V, IK ) dt dIK = g(V, IK ) dt 神経活動は膜電位Vとカリウム電流IKの状態空間で表現される。 状態空間の中での時間発展は、微分方程式という過程で表現できる。 微分方程式の形を決めるパラメーターは高次の状態。 パラメーターの選択すらも高次の状態のひとつと捉えることができる。 このとき、微分方程式という過程は空っぽの箱である。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.285
状態と過程: 神経ネットワークで考える 脳のマクロな状態 (脳波など) 全神経細胞のV, IK 高次の状態 (パラメーター) k1, k2, . . . 状態 過程 (微分方程式) db = f(b) dt b 同様に脳ネットワークの活動も力学系として表現できる。 脳の過程と脳の状態は両者があることで稼働する。 「脳の過程」とは、力学系を描写する微分方程式であり、 それは状態量を抜いた、空っぽの箱になっている。 (つまりそれは感覚運動随伴性のように、実際に稼働しなくても 成り立っている。) 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.285
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」とは もし意識の流れを形式化できる としたら、それも力学系で表現 されるだろう。 「脳の過程bと意識の過程cの絡 み合い」とは、それぞれの力学 系を描写する微分方程式(状態 量を抜いた、空っぽの箱)がお 互いを可能とする可能化関係の ことだ。 そしてそれは行為的媒介の関係 にあり、システムを作動させて みないと見えてこない 拘束条件のことなのだ。 脳の 状態 b1 脳の 過程 意識の 過程 b c b2 意識の 状態 c1 c2 b3 c3 db = f(b) dt 可能化 関係 dc = g(c) dt =行為的媒介 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.286
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」とは もしこの「絡み合い」を相 互作用として明示的に表現す ると、以下のようになる。 db = f(b, c) dt dc = g(b, c) dt しかしこれでは、脳と意識が 因果的に関わるひとつながり の過程になってしまう。 絡み合い = entanglement 量子エンタングルメント のような非自明な相関 とは似てるけど違う? 脳の 状態 b1 脳の 過程 意識の 過程 b c b2 意識の 状態 c1 c2 b3 c3 db = f(b) dt 可能化 関係 dc = g(c) dt =行為的媒介 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.286
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」とは Q: 「状態のないからっぽの過程 f()」という表現に意味はあるか? f()の形を決めているのは パラメーターなのだから、 それはパラメーター間の 対応付けに還元されるのでは? A: たとえばパラメーターk1が 取れる範囲が、f()だけを想定 していたときと比べて、g()が 併存すると制限される、 という事態を想定している。 それは稼働させないとわから ない行為的媒介の関係。 非自明な拘束条件: 取れる範囲が制限 高次の状態 (パラメーター) 高次の状態 (パラメーター) m1, m2, . . . k1, k2, . . . 脳の過程 db = f(b) dt 意識の過程 可能化 関係 dc = g(c) dt =行為的媒介 脳の状態 b1, b2, . . . 意識の状態 c1, c2, . . . 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.286
ヴァレラの「神経現象学」 神経生物学的な基盤 相互に 拘束条件 現象学的還元の元での 「生きられた経験」の性質 神経生物学 現象学 非線形力学 主に非線形力学に基づいた 形式的な描写 いま提示した考えは、ヴァレラの神経現象学での 「神経生物学と生きられた経験が互いの拘束条件となっている」 をより解像度を高くして表現したものと言える。
吉田と田口の「神経現象学」 行為的媒介 現象学的還元の元での 「生きられた経験」の性質 神経生物学的な基盤 神経生物学 互いが互いを 可能にする 現象学 非線形力学 主に非線形力学に基づいた 形式的な描写 しかしそれだけに留まらない。ヴァレラとトンプソンは心から脳への 下降因果(downward causation)と表現していた。 しかしこの「拘束条件」は因果ではない。それは行為的媒介なのだ。
Tom Froeseのirruption theory この考えは、 Tom Froeseのirruption theoryに対する批判 or 拡張 になっている。 Irruption theoryの予測は 脳と意識の間の非自明な相関がノイズのゆらぎとして現れ るというものだ。 しかしわれわれの理論によれば、 それは高次の状態の間の拘束条件を反映したものだ。 より脳と意識の問題に関連が高いのは、 脳の過程と意識の過程の間の可能化関係(行為的媒介)だ。
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
フッサール現象学での視覚論 私が身体を左に動かせば、眼前のサイコロの これまで見えていなかった左側の側面が見えてくる。 われわれが見ているものは、 つねに自分の身体の運動可能性 と結びつけられる仕方で経験されている。 吉田正俊, 田口茂 (2018) 自由エネルギー原理と視覚的意識. 日本神経回路学会誌 25 (3), 53-70 田口茂「現象学という思考」筑摩書房
フッサール現象学での視覚論 「われわれにとっての視覚経験は一般に、身体の運動可能性 のシステムに相関する仕方で、「こうすればこうなる」という 現われのシステマティックな変化によって成立している。」 「身体をもった主体が環境に働きかけ(介入し)、そこに 予測→確認→修正→予測→……というループが形作られるとき、 視覚経験に対応するものが立ち現われる。」 => 予測的処理を先取りしている! 田口茂「現象学という思考」筑摩書房
「予測誤差最小化」の見直し 生物は予測誤差最小化をしているだろうか? そもそも予測誤差最小化は工学的な技法として導入さ れたものであって、生物の原理である保証はない。 「役に立たない機械」 この機械は 予測誤差を最小化を達成すると 機能を停止する。 センサー値(スイッチの状態)についての 予測誤差を感知して、 行為でスイッチをオフにすること で予測誤差を解消している。 CC BY-NC-SA 2.0 https://en.namu.wiki/jump/ hvCqfihMkToeEDsz1V0wZY4hA64R0NE2lltpn6KwYJIqBwhnXxf1h l%2FhAOSehn1PFy5JqKpcERZ5W%2BM3sa%2FEFQ%3D%3D
「予測誤差消費」へ 環境との差異がゼロになることは、生物にとっては死である。 むしろ予測誤差という差異がありつづけるからこそ、 生命システムとそれに属するネットワークは 活動を続けてゆくことができる。 さまざまな階層における予測誤差という無数の差異は、 むしろ生命を生かし続ける糧であり、 生命はそれを「食らい続ける」ことで生きながらえている。 この点を考えると、 「予測誤差最小化」というよりはむしろ、 「予測誤差の消費」について考えたほうがよいのではないか。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.228-229
予測誤差消費のプロセスで置き換える 感覚運動カップリング 構造的 カップリング 操作的閉包 互いが互いを 可能にする 外界との 相互作用 予測誤差消費のプロセス センサー値 または 他プロセスへ の「出力」 ニューロン間ネットワーク 予測誤差 信念 ニューロン間ネットワーク 予測誤差消費のプロセス 効果器 または 他プロセスへ の「入力」 センサー値 操作的閉包 可能化条件 効果器 ニューロン間ネットワークの単位を予測誤差消費のプロセスとして、 それらが可能化関係で閉じることが、操作的閉包を作る 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズム入門」青土社 p.232
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
アクティブ・ヴィジョン: 我々の意識経験は行為によって構成される (A) (B) (C) 図1-5
アクティブ・ヴィジョンの場合 意識に 与えられて いるもの (感覚) 志向的に乗り越える 志向的 対象 ソファーからの眺め という意識経験
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」 「脳の過程processと意識の過程processが絡み合いの関係にある」 という考えに立ち戻る。この「絡み合い」とは エナクティヴィズムでの世界とagentの相互規定のことを指していたのだ。 そしてこの絡み合いは媒介論での「行為的媒介」の関係にある。 エナクティヴィズム 「知覚とは、知覚的に導か れた行為のことである」 脳の 状態 B1 World mutually specify Agent B2 B3 脳の 過程 意識の 過程 b c 意識の 状態 C1 C2 C3
アクティブ・ヴィジョンの神経現象学 差異を消費し続ける過程 行為的媒介 意識の過程 脳の過程 現象学 予測的処理 意識に 与えられて いるもの 互いが 互いを 可能にする 時点1 時点2 時点3 「手が見える」 「窓が見える」 「足首が見える」 「手は胴体の 近くにある」 「私の部屋に は窓がある」 「私の部屋には 椅子がある」 「自分の手か どうかは動か せばわかる」 「眼を動かせ ば遠くの視野が 見える」 「自分の足かど うかは動かせば わかる」 センサー値 志向的な乗り越え 志向的対象 信念 相互浸透 非主題的な 前提条件 生成モデル 「大抵の場合、物体は同じ場所にありつづける」 「眼を動かせば、視野が反対に動く」 「…………………」 図6-7
アクティヴ・ビジョンの神経現象学 行為的媒介 意識の過程 脳の過程 現象学 予測的処理 意識に 与えられて いるもの 互いが 互いを 可能にする センサー値 志向的な乗り越え 志向的対象 信念 相互浸透 非主題的な 前提条件 意識とは、 信念(現状の推定)と 生成モデル(世界とagentの関係につ いての知識)が一体となって、 知覚のたびに オンラインで照合され続ける過程 である。 生成モデル 「脳の過程」とは、より正確には、 「感覚運動カップリング」と 「誤差を消費する神経ネットワーク」 で成立する生物学的自律性のこと。 「生成モデル」は脳だけでなく、身体 と環境にも埋め込まれている。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.295
「脳の過程と意識の過程の絡み合い」とは だからこそ、 システムを作動させなければわからない 未知の事象にそのつど対応しながら生き続ける というオープンエンド性への対応が前提となり、 いつその生物学的自律性が壊れるかもわからない という不安定さprecariousnessと隣り合わせ となっている。 こういう不確定性が われわれの意識と脳の関係には つねに付きまとっているのだ。 吉田正俊+田口茂 (2025) 「行為する意識: エナクティヴィズ ム入門」青土社 p.286
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
エナクティヴィズムとFEPの関係 (谷忠さんとの議論やネットの反応を踏まえて) • 無意識的推論 (=> ベイズ確率 => FEPやPEM) • エナクティヴィズム: (=> 力学系) エナクティヴィズムをFEPにつなげるのは あくまでも近似 しかし、これは誤解を生んできた エナクティヴィズムは 力学系から確率になる過程こそが焦点
エナクティヴィズムとは エナクティビズム 表象主義 古典的表象主義 pre-given World World cast image recover = represent Agent Cognition as the recovery of a pregiven outer world ヘルムホルツの無意識的推論 pre-given World project = represent Agent Cognition as the projection of a pregiven inner world mutually specify Agent Cognition as embodied action Perception consists in perceptually guided action. エナクティヴィズムを 表象主義の代替として、 すべてを説明しようとする 考えにこだわらないほうが よいのではないか。 Varela F. J., Thompson E. & Rosch E. (1991) The embodied mind: Cognitive science and human experience. MIT Press, Cambridge. p.172-173
両者をどう折り合いをつけるか • エナクティヴィズム (=> 力学系) • 無意識的推論 (=> ベイズ確率) 両者の関係は 非平衡系の物理と平衡系の物理のように 捉えたらよいのではないか。 習慣化された世界(=平衡系)を取り扱うにはベイズ確率が有用。 でもわれわれの認知と生命はつねに揺らでいる(=非平衡系)。 意識の理解において、この揺らぎは無視できない。 だからこそエナクティヴィズムは不可欠。
例: 確率空間の作り直し 蝶と蛾のみの世界 センサー値s1, s2 隠れ状態xの信念q(x) 1 (確率分布 として表現) 0 蝶 蛾 x バッタとの邂逅 新たなセンサー値s3 隠れ状態xの組み直し 1 0 蝶 蛾 蝗 x
両者をどう折り合いをつけるか エナクティヴィズムでなんでも説明する 必要はないし、実際できていない。 そうできると主張することは、エナク ティヴィズムを浸透させることを妨げる。 いっぽうで、あらゆる現象において、 習慣化されていない状態に立ち返るとき にエナクティブな視点が必要になる。
本講演の構成 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 概要 NCCプロジェクト 予測的処理 エナクティヴィズム 生物の自律性 生命と精神の連続性 エナクティヴィズム再び 神経現象学 吉田と田口の神経現象学 • 脳の過程と意識の過程の絡み合い • 予測的処理の見直し • アクティブ・ヴィジョンのモデル 10. 出版後に考えたこと
END