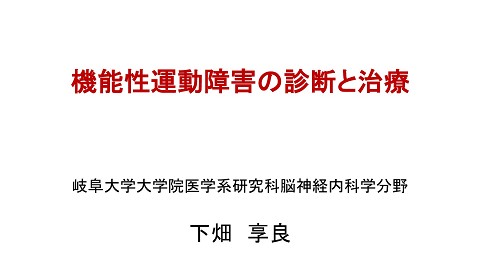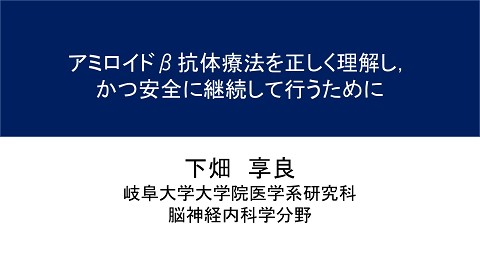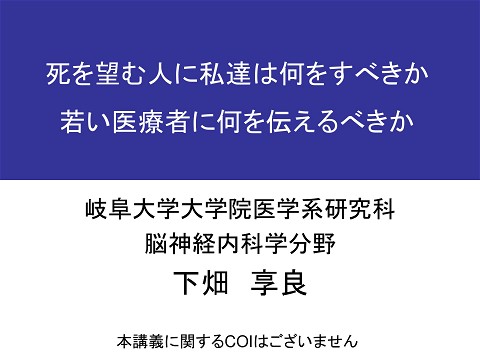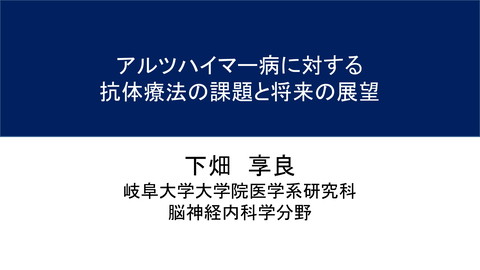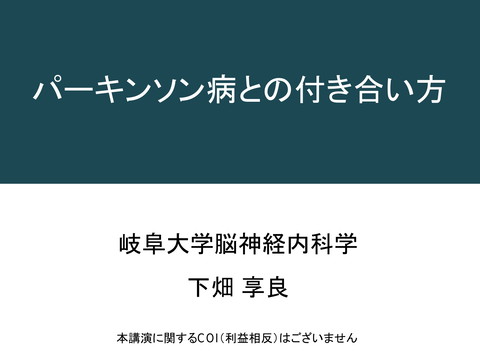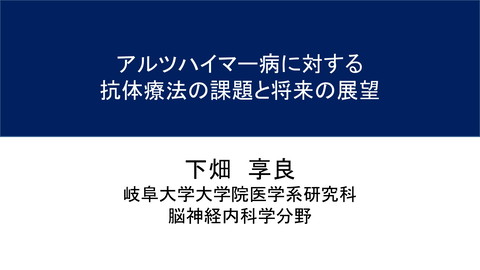機能性神経障害における倫理的課題とその対応
1.8K Views
November 09, 25
スライド概要
第43回日本神経治療学会シンポジウム「脳神経内科医が直面する臨床倫理の最前線―終末期・遺伝・治療選択をめぐって― 」で使用したスライドです.
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 教授
関連スライド
各ページのテキスト
機能性神経障害における 倫理的課題とその対応 下畑 享良 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経内科学分野
日本神経治療学会 COI 開示 筆頭発表者:下畑 享良 岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野・教授 本発表に関連し,明示すべきCOI関係にある企業などはありません.
はじめに • 機能性神経障害(functional neurological disorder; FND)は,筋力低下, けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の 高い疾患である. • かつてヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体化障害, 身体表現性障害,心気症,詐病など,さまざまな名称で呼ばれてきた.
パンデミック当初から患者数が増加した 2019 2019 小児 Neurology. April 14, 2021 (doi.org/10.1212/CPJ.0000000 000001082) 2020 2020 成人 全体 ベイラー医科大学 女性が75.6%.
COVID-19ワクチンにて患者数が増加した 非接種群 イタリアの検討. ワクチン未接種での入院と,接種後 30日以内の入院を比較し,増加した 疾患は・・・ FND(12.3%対3.6%;OR 4.2) 頭痛(10.8%対5%;OR 4.1) Eur J Neurol. 2024 Jan 2:e16191.
コロナ後遺症外来でFND患者受診の増加を経験し, シャルコー先生の診療を改めて意識した • シャルコーが普仏戦争後(1870-1871)に増加した ヒステリー患者にどのように向き合ったのかを知り たいと思い,文献や資料を渉猟した. • 脳と心の接点を恐れずに探究した彼の姿勢に,深い 感銘を受けた. Jean-Martin Charcot(1825-1893)
機能性神経障害をめぐる現状 • 近年は「機能性神経障害」という診断名の使用が一般的になりつつある. その理由は,心身いずれに原因を帰するかを前提とせず,患者に説明・ 共有しやすく,さらに症状の回復にも寄与する可能性があるためである. • すなわち本疾患は,神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として 再構築されつつある. • しかし,依然として医師による誤解や否定的態度が根強く残り,誤診も 生じており,患者はしばしば不必要な苦痛を強いられている.
機能性神経障害においてまず医療者が共有すべきこと 機能性神経障害(FND)は,かなりの苦痛と障害を伴う. 症状は偽りではない. Stone J, Burton C, Carson A. Recognising and explaining functional neurological disorder. BMJ. 2020 Oct 21;371:m3745. Prof. Jon Stone University of Edinburgh
本講演の目的 • FNDにおける臨床倫理的問題について近年の文献を概観し, その体系的な分類を試みる. • 各問題に対する解決の方向性を,臨床倫理の四原則に則って 検討する.
文献レビューのプロトコル ((“Ethics”[Mesh]) OR (“Social Stigma”[Mesh])) AND (“Conversion Disorder”[Mesh] OR “functional neurological disorder” OR “psychogenic non-epileptic seizure”) を 条件に,2025年8月に過去10年分の文献をPubMedで検索した. 検索結果から臨床倫理的問題を扱った論文を選択し,editorialおよびコメントは除外した. さらに,引用文献を確認し,必要に応じてハンドサーチを行って文献を追加した. 採用した論文の内容に基づいてカテゴリー分けを行い,各問題の 内容と解決の方向性を検討した.
結果;文献レビュー PubMed検索結果 22編 1次スクリーニング (抄録) 除外論文:7編 該当論文:15編 2次スクリーニング (本文内容) 除外論文:4編 ・FNDの倫理的問題への言及無し:2編 ・editorial,コメントなど:2編 ハンドサーチによる追加:4編 レビュー対象論文: 15編
15編の研究デザインの内訳 • システマティック・レビュー 4論文 • スコーピング・レビュー 2論文 • ナラティブ・レビュー 2論文 • 前向き観察研究 1論文 • 横断研究 4論文 • 質的研究(半構造化インタビュー) 2論文
採用論文のカテゴリー分類 採用論文を分析し,FNDの臨床倫理的問題は 以下の4つに分類できると考えた. 1. スティグマ(stigma) …最多 2. 誤診と医原性の害(iatrogenic harm) 3. 病態理解のギャップと患者体験の軽視 4. ジェンダーと歴史的偏見 社会的に望ましくない特性に付与される ラベルや偏見を意味する.
① スティグマ • FNDのスティグマは,患者の尊厳を傷つけ,QOLを大きく低下させる. • 個人・家族・社会・制度といったレベルに多層的に存在し,相互に作用し 持続する. Seizure 2022; 99: 131–152. Clin Psychol Rev 2024; 112: 102460. J Psychosom Res 2024; 181: 111667. Disabil Rehabil 2024; 46: 1–12. • スティグマは機能性発作(=心因性非てんかん性発作)で特に強い: てんかん患者の4倍以上のスティグマを呈する. • 機能性発作のスティグマは健康関連QOL低下と関連する. Epilepsy Behav 2017; 73: 133–137. Seizure 2018; 55: 93–99. Epilepsy Behav 2020; 111: 107269.
スティグマを強める外的要因 1. 「他者化」:医師に理解されにくい異質な存在として扱われること. 2. 症状を正当なものとして認めない医師の否定的態度. 3. 「心因性・・・」「偽性・・・」などの病名. J Psychosom Res 2024; 181: 111667. Seizure 2022; 99: 131–152. CNS Spectr 2021; 26: 619–626. • 外的要因は社会・教育・就労の場にも広がり,患者を孤立させる. • この結果,「自分は劣っている,迷惑をかけている」と考えるようになる. このようにスティグマを自ら取り込んでしまうことを「内面化」と言う. J Psychosom Res 2024; 181: 111667. Epilepsy Behav 2017; 73: 133–137. BMJ Neurol Open 2025; 7: e000694. Disabil Rehabil 2024; 46: 1–12. Psychol Health 2024; 39: 1130–1147.
スティグマへの対策 • 医療者教育により,FNDに対する否定的態度を改善する. • 「心因性・・・」「偽性・・・」などの精神的負担を与える病名を回避し, 「機能性神経障害」として説明する. • ただし医療者教育のみでは不十分で,それ以外の多面的アプローチ が必要であるという報告もある. CNS Spectr 2021; 26: 619–626. BMJ Neurol Open 2024; 6: e000633.
② 誤診と医原性の害 • 質的研究のシステマティック・レビューの結果,FNDではしばしば診断の 遅れや医師への不信感が生じることが分かった. • この結果,不要な検査・処置による身体的・社会的ダメージ,治療の遅れ, 不要な薬剤の使用などの医原性の害(医療行為が患者に有害な影響を 及ぼすこと)が生じる. Disabil Rehabil 2025; 47: 1–15. Brain 2025; 148: 27–38.
② 誤診と医原性の害 FNDの診断に不慣れ,否定的な医師 不信感 診断の遅れ 不要な検査・処置 誤診 FNDへの治療介入の遅れ ダメージ 不要な薬剤 FNDの重症化 (不可逆的変化)
誤診の典型例 • 機能性発作がてんかんと誤診されるケース ✓ 不要な抗てんかん薬が処方される ✓ てんかん重積状態と誤診 → 気管内挿管,ICU管理に至る. • 診断の遅れ → 適切な治療介入機会の喪失,回復可能性が減少. • 逆に,早期の明確なFND診断 → 患者に安心感と回復の契機となる. Disabil Rehabil 2025; 47: 1–15. Brain 2025; 148: 27–38.
医原性の害の種類 Disabil Rehabil 2025; 47: 1–15. Brain 2025; 148: 27–38. ① 誤診による不要な薬剤の処方や処置 ② 診断変更に伴う心理的・社会的ダメージ ③ 診断・治療の遅延 ④ 不適切で侮辱的な対応 ⑤ 「詐病」「偽性」などレッテルによるスティグマ ⑥ 「機能性」の概念の誤用・誤解 ⑦ 潜んでいる器質的疾患の見逃し ⑧ 過剰診断・早計な診断 発作後の患者の顔に手を落とす
医原性の害への対策 • FNDを「陽性徴候」により,病初期で診断できるようにスキルアップする. • 適切な検査と説明を行い,安心を提供する. • 医療者教育を行い,スティグマを低減する. • 他疾患と同等の診療・研究体制を整備する. • 社会に対し,FNDの啓発を行う.
③ 患者と医療者の病態理解のギャップと患者体験の軽視 • 患者と医療者の間に症状の認識に大きな隔たりがあることを認識する. • 例:機能性運動異常症の随意性・コントロール可能性の解釈の違い. • 医師:「随意とも不随意とも解釈可能」 • 患者:「自分の意思ではなく,全く抑えられない」 • この乖離が診断受容や信頼関係の構築を妨げる. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2017; 88: e1.
医師が尊重すべき患者体験 • 質的研究レビューで抽出されたネガティブな体験 ✓ 身体症状が「心の問題」と片付けられる体験 ✓ 自己同一性,職業,社会的役割を喪失する体験 ✓ 理解されず不信感を抱きつつ,支援を強く求める体験 • 患者は医師との関係を通じて自己を再構築できる可能性があるので, 医師は,病態を正確に説明するだけでなく,患者の体験を尊重し, 一人ひとりに合わせた支援を行うことが求められる. BMJ Neurol Open 2025; 7: e000694.
④ジェンダーと歴史的偏見 • 「ヒステリー」の語源はギリシア語 hystera(子宮)であることからも分か るように,女性特有の疾患とみなされ,男性よりも女性に圧倒的に多く 診断がなされた. • この過程で女性へのスティグマが形成され,尊厳や医療への信頼を 損なうことになった. • シャルコーやバビンスキーらの臨床的観察,フロイトによる精神分析学 的解釈は,FNDの理解の発展に寄与した一方で,ジェンダーバイアス を強める要因にもなった.
シャルコー先生の「火曜講義」における ヒステリー患者Wittman ポール・リシェの描いたヒステリー発作 体幹を弓なりに反らせる「l’arc de cercle」姿勢 → 女性特有の疾患というイメージの形成
女性特有のFNDのリスク因子 妊娠・出産・育児・介護 ホルモン変動,妊娠中の薬物制限,出産後の疲労 睡眠不足,社会的役割変化 性暴力,家庭内暴力 FND患者は健常者の約8倍の虐待歴を有する J Psychosom Res 2011; 71: 369-376. Lancet Psychiatry 2018; 5: 307-320.
ジェンダーバイアス克服に向けた対応 • FNDをジェンダーに依存する疾患ではなく,神経学的に診断・治療可能 な疾患単位として再構築する. • 必要な対策 • 教育を通じた偏見是正 • 妊娠・授乳期を含む診療ガイドラインの整備 • 育児・介護支援体制の拡充 • 暴力被害への早期介入 J Psychosom Res 2011; 71: 369-376. Lancet Psychiatry 2018; 5: 307-320.
FNDへの対応を臨床倫理四原則からまとめなおす 自律尊重 善行 無危害 公正
① 自律尊重原則 ★患者が自分自身の価値観や意思に基づいた医療上の決定を自律的に行えるよう, その意思を尊重し,情報提供や意思決定を支援する. • FND患者の言葉を傾聴し,症状への理解のギャップを埋める • 陽性徴候を的確に捉え,患者に明示する • 疾患が実在することを保証し,自己理解と受容を支援する • 生活背景やライフイベントを踏まえた治療選択肢を示し共有する
② 善行原則 ★患者にとって最善の医療を提供することを目指す. • 医療者教育による偏見の是正・スティグマ低減 • 安心して診療に参加できる環境整備 • 患者・家族を含めた心理社会的サポートの充実 • 妊娠・出産・育児・介護などライフステージに即した医療体制の構築 • ピアサポートや患者団体との連携 → 社会的包摂の促進
③ 無危害原則 ★患者に身体的,精神的な危害を与えないように行動し,危険や苦痛を予防・回避する ことを目指す. • FNDを陽性徴候により積極的に診断する • 病名において「心因性・・・」「偽性・・・」など有害な表現を避ける • 誤診を避け,不要な薬物の処方,侵襲的処置を回避する • FND以外に他の疾患が潜んでいる可能性も常に念頭に置く
④ 公正原則 ★すべての患者を公平・公正に扱い,限られた医療資源を適切に配分することを目指す. • 母性神経学の視点を反映した診療ガイドラインの策定 • 暴力被害者への早期介入 • 育児・介護に伴う負担軽減など,社会的弱者に配慮した仕組み • 公平な医療アクセスの保証 • 教育・研究・資金配分でFNDを他の神経疾患と同等に位置づける
まとめ • FNDでは歴史的偏見や制度上の不備に由来する臨床倫理的課題が残存するが, 四原則の枠組みは,臨床現場で課題に立ち向かうための指針となる. • 今後の課題 • FNDの診療レベルの向上 ・医療者教育の標準化 • 患者体験を尊重する文化の醸成 ・基礎・臨床研究による疾患の理解 本講演内容は「臨床神経学(2026年1月)」にin pressになっています.