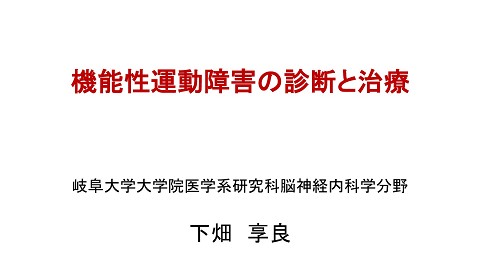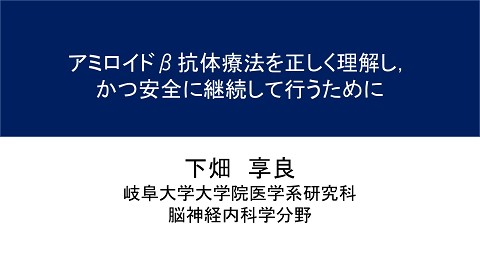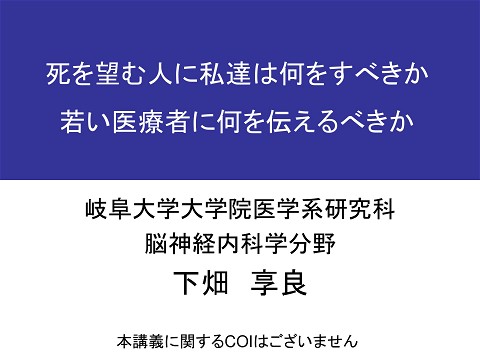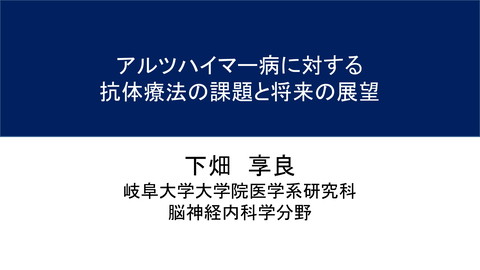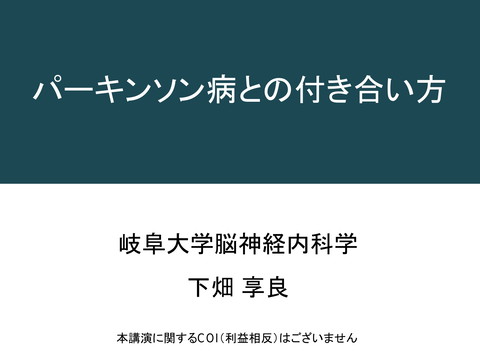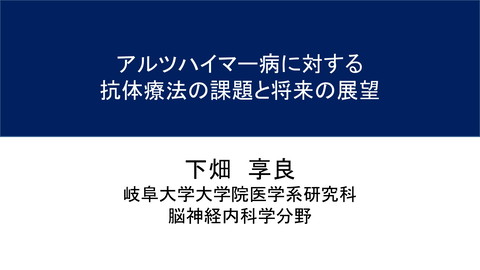第32回リベラルアーツ研究会「マネジメント」
813 Views
March 04, 25
スライド概要
第32回リベラルアーツ研究会「マネジメント」@岐阜大学医学部にて使用したスライドです.
岐阜大学大学院医学系研究科脳神経内科学分野 教授
関連スライド
各ページのテキスト
第32回 医学生のための リベラルアーツ研究会 マネジメントを読んで,組織, 社会への貢献と自己実現の方法 を学ぼう! 岐阜大学 脳神経内科学分野 下畑 享良
もしドラ(2010) • 『マネジメント』の理論を,高校野球の マネージャーという身近な題材に落とし 込み,わかりやすく解説した本. • 川島みなみは,親友が入院したことを きっかけに,彼女に代わって高校野球 部のマネージャーになる.本屋で偶然 見つけた『マネジメント』を手に取り, その内容をもとに野球部を改革する.
課題図書の目的 • 「もしドラ」でみなみが行った「マネジメント」について議論する. • マネジメントの父,ピーター・ドラッカーがマネジメントの考え方に 至った背景や,彼の目指したマネジメントの目的を学ぶ. • マネジメントにおける重要な考え方を理解する (とくに3つの貢献について) .
Management と Leadershipの違い Peter Drucker ( ) is doing things right, whereas ( ) is doing the right things. The Practice of Management, 1954
Management と Leadership の両者を学ぶべき! 定義 マネジメント 役割 組織の目標を達成するために, 既存の枠組みの中で最適化を プロセスや手順を最適化し, 図る. 成果を最大化すること. 大局的な視点から何を目指す リーダーシップ べきか,どの方向へ進むべき かを決定し,組織を導くこと. 枠組み自体を見直し,新たな 道を切り開く. 両者は対立する概念ではなく,補完し合うものであり,組織の成功 にはどちらも欠かせない.
みなみが影響をうけた ドラッカーの言葉(6) 「マネジメント=組織の目的達成」を意識して考えてみよう! 1. マネジメントの目的は顧客を創り出すことである みなみは「高校野球における顧客」はまず「選手」であることに 気づく.選手が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整え ることが,マネージャーとしての使命と認識する. 2. 強みを活かす ドラッカーは,個人や組織の「強み」を最大限に活用すること が重要と述べた.みなみは選手一人ひとりが最も活躍できる ポジションや役割を考えることで,チームを向上させた.
3. 目標を明確に設定する ドラッカーは,組織の成功のためには「明確な目標」が必要と 述べた.みなみは「甲子園出場」を明確な目標として掲げた. 4. 組織への貢献を意識する ドラッカーの「貢献がマネジメントの本質である」という考えを もとに,みなみは「自分はどのように貢献できるか?」を常に 問い続けた.
5. 組織における最大の資源は人である 選手たちが最大限の力を発揮できるように,みなみはマネジ メントを通じて環境を整え,コミュニケーションを円滑にし, モチベーションを高めることに努力した. 6. イノベーションとは組織の成長を促す新しいやり方を見つけること みなみは,従来の高校野球のやり方にとらわれず,新しい 発想を取り入れることでチームを変革しようとした.
私がチームで考えたこと 当科の方針の中はドラッカーの影響を受けている
私がチームで考えたこと 当科の顧客とは? 教室のメンバー,患者さん・家族,社会 当科の強みとは? 神経免疫学,摂食・嚥下,コミュニケーション 当科の目標とは? ①臨床・研究は患者さんや世の中の役に立つことをつねに 念頭に置く ②意識して人を育てる(医学生,若手医師,学会のリーダー) ③リーダーシップを学び,レジリエンスを高め,チームの一員と して考えて活動する 組織への貢献とは? 教室のメンバー(教育,スペシャリストの育成) 患者さん・家族(最善,最新の医療) 社会(情報発信,啓発活動) 最大の資源である人 意識して人を育てる 各人が幸せでないと患者さんを幸せにできない. 早くから海外学会,国内留学,海外留学していただく イノベーション いままでにない方法を積極的にトライする (リモートカンファ,抄読会の公開,社会への発信)
さてピーター・ドラッカーはどんな人? Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005) オーストリア・ウィーン 生まれのユダヤ系 オーストリア人 一言でいうと,人間への深い洞察ができる人, つまり人間とはなにか?社会とはなにか?を考えた人.
ピーター・ドラッカーの人生 • 1930年代にナチスの支配するドイツから脱出 して,ロンドンを経て米国に渡ったユダヤ人 の亡命者であった • 若い頃,肌身に感じていた不条理に,アメリ カ社会のなかで,経営的な知識を編み上げ ることで対抗しようとした. • 資本主義も社会主義も人間を幸せにし得な かった理由を「経済至上主義」を基本にして いたからだと結論づけた. • それらに変わるものとして,組織運営の仕方 (マネジメント)に注目すべきと考えた.
ドラッカーの命題 「人間の本当に幸せとはなにか?」 • 人と人が一緒に働きながら,成果を上げ,それ ぞれが幸せになり,真っ当な社会を作っていく ためには,いかなる組織運営を行っていけば 良いのかに注目した. • 実際の組織・企業(例:GMなど)に入り込み, 観察して多くの著作を書いた. • 「マネジメント」は経営学の本というより,人間 を感動させ,幸せに導くために書かれた本とも 言える. 1950年代のドラッガー
マネジメントは 「組織,社会,自分」に向かう! 1. 自らの組織の目標達成に対し,各々が使命を果たす 2. 組織は自らの強みを用いて,社会の問題・ニーズに貢献する 3. 他者への貢献を通して,自己実現を達成する. 組織への貢献が社会への貢献を生み,最終的には自己実現にも つながる
①組織への貢献 1. 組織のマネジメントにもっとも必要とされるのは才能ではなく, 真摯さ(integrity)である・・・他人にも自分にも厳しくなる 2. セルフマネジメントを行うということは「すべての人が経営者 (ボス)と同じ意識を持つこと」である 3. 絶対というものは存在しない.すべて変わっていく.あえて自らを 陳腐化し,絶えず新しいものにチャレンジしていく姿勢が大切. 今,起こっていることをしっかり観察すれば,おのずと次に起こる ことが見えてくる.
②社会への貢献 1. 企業は社会の一員として,社会に貢献する責任がある. 2. 社会のニーズに応える製品やサービスを提供し,社会問題を 解決する役割も担うべきである. 3. 知りながら害をなさない(責任の倫理) Not knowingly to do harm “Primum Non Nocere” ヒポクラテスの考え方に通じる
③自己実現への貢献 1. 組織に属するものが,成果を上げるために努力工夫をすれば 組織や社会のためになるだけではなく,本人の自己実現に つながる 2. 他者への貢献を通して,存在意義を感じ,自己肯定感を高める 貢献によって新しい知識・スキルを学び,自身の成長を促す. 3. 「何を持って憶えられたいか?」子供や孫,あるいはまわりの 仲間たちに,自分はどういう存在として記憶にとどめておいて もらいたいかを意識する.
ドラッカーは日本を愛し期待していた • 日本の伝統文化(水墨画)にたまたま触れ,日本 の芸術に関心を持った. • 日本企業が「組織の目的は人々の強みを活かし, 弱みを最小限にすること」という彼の理論に非常に 合致していると考えた.日本企業の「終身雇用」や 「チームワーク重視」の文化を,欧米とは異なる強 みとして捉えた. • 「武士道」の精神を経営やリーダーシップの観点か ら高く評価し,日本の企業経営における倫理観や 責任感に深い敬意を抱いた.
まとめ 1. マネジメントの本質,組織・社会・自己の関係を理解しよう マネジメントとは単なる効率化の手法ではなく,組織を通じて社会に貢献し, 最終的には自己実現につなげるプロセスである. 2. 真摯さと貢献の精神を大切にしよう 才能よりも真摯さ(integrity)が組織には不可欠である.個人の強みを活か し,組織の目標達成を支援しながら,社会のニーズに応えることで,自らの の成長を促していく意識を持とう! 3. 「何を持って憶えられたいか?」を考えてみよう 組織や社会への貢献を通じて,私たちはどのような足跡を残すのか.自身 の存在意義を問い続けながら,誇りを持てる生き方を追求していこう.
次回の課題図書 • 「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」 という疑問を,労働と読書の関係の歴史に 着目して,明治時代から現代まで追ってい くことで明らかにした本. • わかりやすい現代史,文化人類学の教科 書のようです. • どうすれば労働と読書を両立できる社会を 作ることができるのかを提案しています. • 知的好奇心をくすぐる本です.