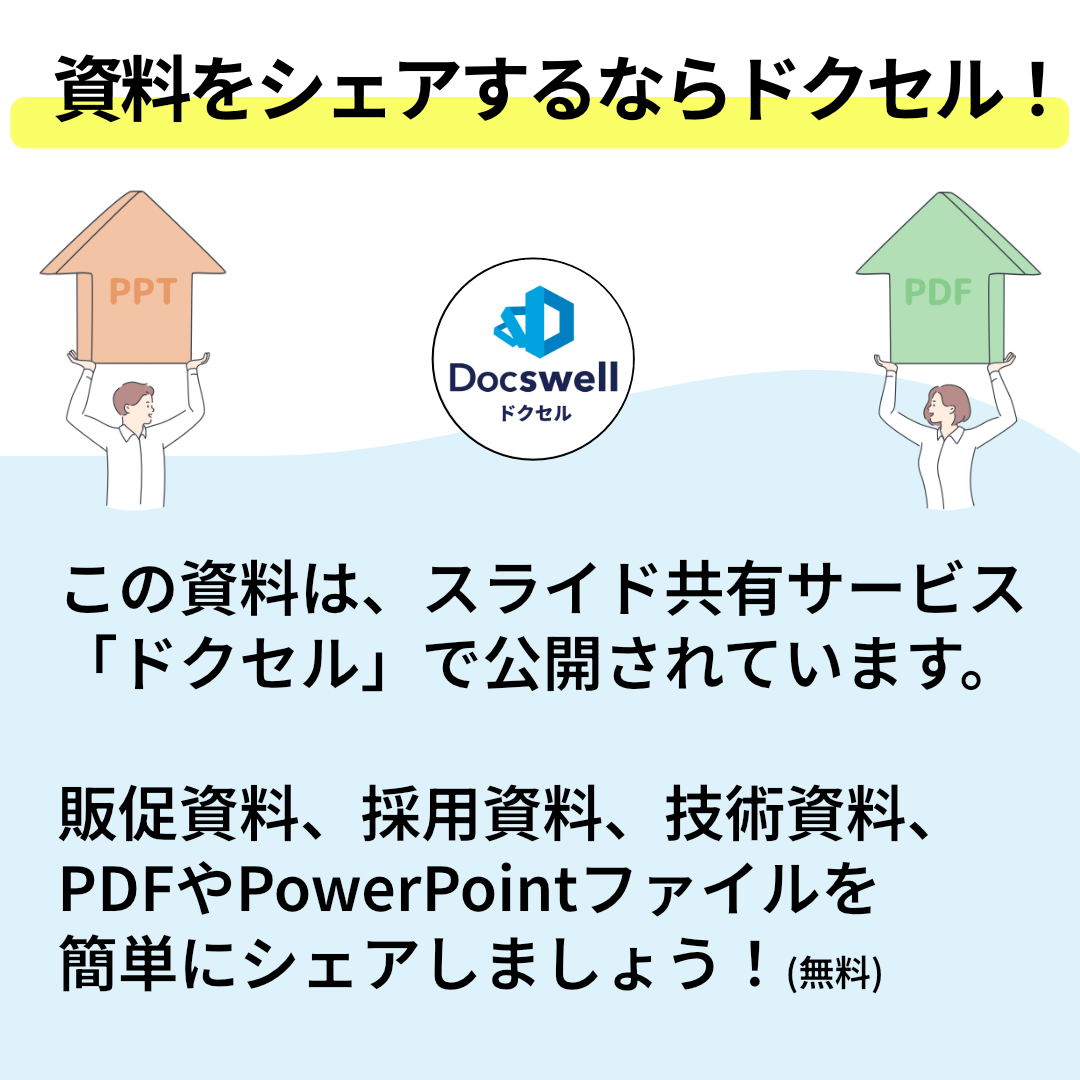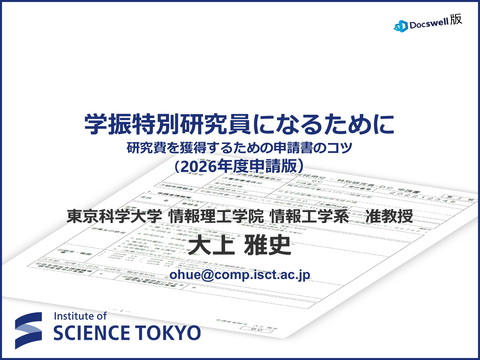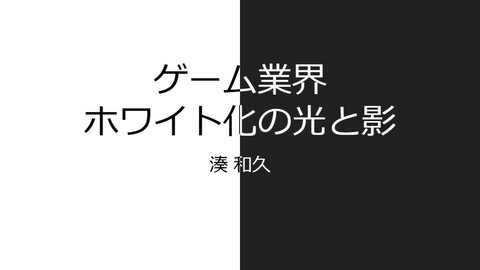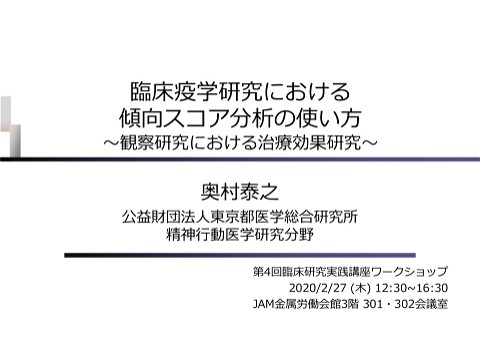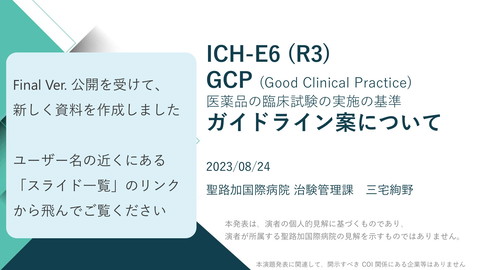関連スライド
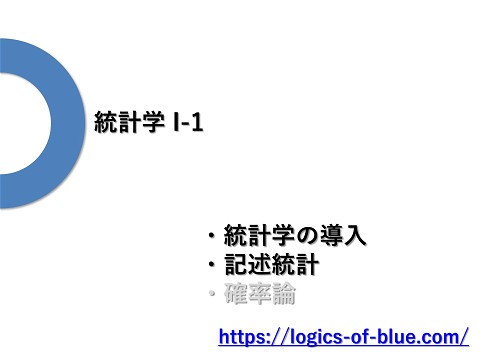
統計学I-1
 Logics of Blue
232.9K
Logics of Blue
232.9K
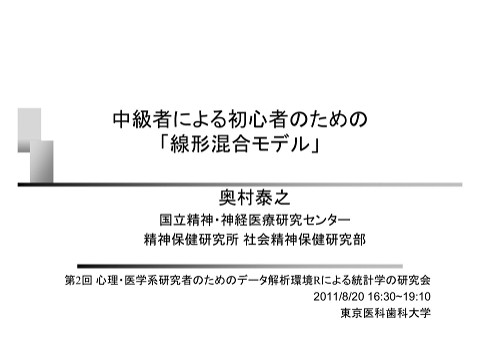
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
188.3K
奥村 泰之
188.3K
各ページのテキスト
目次 1.亜麻についての概要……………………1 〜 4p (1)亜麻という植物……………………………………………………1p (2)亜麻の主な用途【花・種】…………………………………………2p 【茎】………………………………………………3p (3)亜麻の品種…………………………………………………………4p (4)亜麻の主な栽培地…………………………………………………4p 2.亜麻の歴史………………………………5 〜 8p (1)人類最古の亜麻繊維(リネン)……………………………………5p (2)古代〜古代エジプト………………………………………………6p (3)古代ギリシア………………………………………………………6p (4)聖書と亜麻…………………………………………………………7p (5)中世…………………………………………………………………8p (6)近代〜現代…………………………………………………………8p 3.亜麻と文化……………………………9 〜 12p (1)チェコの絵本「もぐらとずぼん」…………………………………9p (2)クロード・ドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」…………………10p (3)グリム童話「糸くり三人女」………………………………………10p (4)有島武郎「カインの末裔」…………………………………………11p (5)油彩画「油絵技法の発展」…………………………………………12p 4.亜麻と産業……………………………13 〜 16p (1)リネン…………………………………………………………13・14p (2)食用油・種子(亜麻仁・アマニ)…………………………………15p (3)化粧品………………………………………………………………15p (4)リノリウム…………………………………………………………15p (5)塗料・油絵具………………………………………………………16p (6)馬房敷物材…………………………………………………………16p (7)飼料(種子・搾り粕)………………………………………………16p 5.亜麻と食………………………………17 〜 20p (1)亜麻仁油・アマニ油…………………………………………17・18p (2)種・種子・亜麻仁・アマニ…………………………………19・20p 6.亜麻と当別町…………………………21 〜 22p (1)亜麻の衰退…………………………………………………………21p (2)種・種子・亜麻仁・アマニ………………………………………22p 参考文献……………………………………………………………………23p
1.亜麻についての概要 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻という植物について、解説していきます。 繊維用亜麻 一年草の亜麻 油糧用亜麻 茎 宿根草の亜麻 ボール (1) 亜麻という植物 亜麻は中央アジア原産のアマ科の一年草で、繊維用と種子用の2系統が あります。原種の亜麻はもともと宿根草ですが、産業用に改良されたものが 一年草といわれています。宿根・多年草の亜麻は、観賞用としてガーデニ ングでも人気があります。 草丈は繊維用で100~150cm、種子用で60~80㎝あります。 花弁は5枚で、青紫または白色の花を咲かせます。雄しべ・仮雄しべともに 5本。基本的に自家受粉をします。 茎の表皮と木質部の間に繊維の束 (リネン) が形成されます。 1
1.亜麻についての概要 (2) 亜麻の主な用途 ●花 一年草の亜麻は開花期間が約1か月、盛花期は2週間ほどです。日の出と ともに咲き始め午後までには散ってしまう儚い花です。 花の直径は約3㎝で 薄紫色です。観賞用品種では白・赤・黄など様々な色があります。 また収穫時の穂先 (鞘・実) は、 ドライフラワーとしても利用されています。 一年草と多年草の種子 ●種 <食品として利用される場合> 加熱した種は、そのままトッピングにしたり製粉してパンや焼き菓子等の 副原料に使います。また、種子を低温圧搾(生種子を圧力によって搾る) したものは食用油(亜麻仁油)となります。 <工業用として利用する場合> 種から搾った油(亜麻仁油)をペンキ・木工用塗油・印刷インク・絵具・ 床材(リノリウム)などに利用します。 油彩画用の亜麻仁油は様々なラインナップがあります 2
1.亜麻についての概要 リネン(亜麻繊維)いわゆる亜麻色 リネン製品(EU 製) 馬房敷物材 ( 亜麻の茎由来 ) ●茎 天然の繊維(リネン)が取れます。リネンは天然繊維のなかで最も強靭で、 かつてはテントや軍服、船の帆、消防ホースなどに使われました。リネンは 吸湿・速乾・防カビ性に優れ、ソフトな肌触りで使うほどに柔らかく しなやかになる特性を持ち、現在も衣服やシーツ、テーブルクロスなどに 重宝される高級繊維です。 またカーボンニュートラルを背景に、 グラスウールに代わる天然素材として、 車の内装やテニスラケット、ヘルメットなどへの利用も期待されています。 リネンを取ったあと、表皮や芯の部分は馬房の敷物として利用され、 北海道でも多くの育成牧場で使用されています。天然素材で吸収性に優れ、 馬体にやさしいのが特徴です。 3
1.亜麻についての概要 (3) 亜麻の品種 亜麻には大きく分けて種子用(油糧用)と繊維用(兼用種)の2系統が あります。 種子用 (油糧用) の品種は、 種子を多く収穫するために品種改良され、 枝分かれ (分枝) が多く、 花も多くつけます。 草丈は60~80㎝と低く、 風による倒伏の 影響が少ないのが特徴です。 収穫時期は8月下旬から9上旬ころです。 繊維用(兼用種)は細く長い繊維をとるために改良された品種で、 枝分かれが少なく草丈が100㎝ ~150㎝と高いのが特徴です。 収穫時期は8月上旬ころで、茎の繊維が硬くなる前に収穫されます。 油糧用(草丈60〜80cm) 繊維用(草丈100〜120cm) (4) 亜麻の主な栽培地 亜麻は冷涼な気候を好むため、世界の亜寒帯の地方で多く栽培されて きました。日本では北海道が最適地ですが、北半球の栽培地域のなかで 南端に位置しています。 【中国】 【ロシア】 【ヨーロッパ中・北部】 世界最大の栽培量です。 黒龍江省で栽培されて います。 油糧用・繊維用ともに盛ん です。亜麻の文化を育んだ 地域です。 【ニュージランド・オーストラリア】 4 【カナダ・アメリカ】 油糧用品種の栽培が盛んです。 試験研究も進んでいます。 【ペルー・チリ・アルゼンチン】
2.亜麻の歴史 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻の歴史について、解説していきます。 セティ 1 世 ( 在位 紀元前 1294 年頃または紀元前 1290 〜 1279 年頃 ) の墓から出土した象形文字が描かれた壁の断片 ヒエログリフ 古代エジプトの象形文字 ヒエログリフの 1 子音文字にある「よりあわせた亜麻糸」の文字。 一般的な字訳では「h」と訳される。 (1)人類最古の亜麻繊維(リネン) 2009年にハーバード大学などの調査チームが、グルジアの洞窟から 3万4000年前の世界最古の亜麻繊維を発見したことを米科学雑誌 「サイエンス」に発表しました。 この繊維は、糸状に加工した状態であったことから、衣服・紐・ロープ などに使われたと考えられるそうです。なかには色が染められた繊維も あるなど、古くから現在と同様の使われ方がされていたのかもしれません。 これまで人類最古の亜麻繊維は紀元前4000〜8000年前だと 知られていましたが、大きな発見となりました。 5
2.亜麻の歴史 出典:Wikipedia , 地図 メソポタミア , 著者ゴランテクエン https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N-Mesopotamia̲and̲Syria̲english.svg ピーターパウルルーベンスによる ヒポクラテスの彫刻、1638年 (2)古代〜古代エジプト 一般的に知られる亜麻の歴史は、紀元前8000年ごろチグリス川・ ユーフラテス川沿岸で栽培されていた植物ということ、また同じころ スイス湖畔の遺跡でリネンが利用されていた事がわかっています。 その後、紀元前6000年からエジプトにおいて利用が進み、紀元前 4000年にはエジプト文明において亜麻は質・量ともに大きな発展を 遂げました。 古代エジプト人は亜麻を非常に重要な作物として扱っており、 亜麻織物は 『月光で織られた布』と呼ばれ、広く神事に使われていました。 またピラミッドに眠るミイラには亜麻の包帯が相当量使われており、 各装飾品の空洞部分にも亜麻布が詰め込まれるなど、重宝されていた 様子がうかがえます。 (3)古代ギリシア 医学の父といわれるヒポクラテスは、亜麻種子を食べると胃腸の不快を 解消するとして亜麻栽培を推奨しました。また病気は 4 種の体液の混合に 変調が生じたときに起きるという、4体液説を唱えた人です。現代科学では 亜麻仁油に含まれる油が、ホルモンバランスを補正するため、亜麻仁油を 増やすよう奨励しています。紀元前400年の説が、現代の治験と論理的に 似ている点に驚かされます。 6
2.亜麻の歴史 ジュリオ・クロヴィオ (1498‒1578) トリノの聖骸布で十字架からの降下 (4)聖書に登場する亜麻 ここでは聖書に登場する亜麻について解説していきます。 ● 旧約聖書に登場する亜麻 《聖句》 亜麻と大麦は壊滅した。大麦はちょうど穂の出る時期で、亜麻は つぼみの開く時期であったからである。 (出エジプト記 9:31,Exodus) イスラエルの先祖が飢饉により食料を求めてエジプトへ降りた。しかし 人口が増え、エジプト人から危険視され労働奴隷にさせられる。この状況に 立ち上がったのがモーセで、イスラエルの民を率いてエジプトを脱出しよ うとする。これを阻止しようとしたエジプト王ファラオに対して十の災い が降り、作物を壊滅した雹(ひょう)はその一つである。 ● 新約聖書に登場する亜麻 《聖句》そこで、ヨセフは亜麻布を買い求め、イエスをとりおろして、その 亜麻布に包み、岩を掘って造った墓に納め、墓の入口に石をころがして おいた。 (マルコ福音書 15:46) イエス・キリストが磔にされて死んだ後、その遺体を包んだとされるのが 聖骸布(せいがいふ、トリノの聖骸布)です。キリスト教の聖遺物の一つで、 トリノの聖ヨハネ大聖堂に保管されています。 7
2.亜麻の歴史 日本での亜麻産業のはじまりは 1871 年 ( 明治 4 年 )。北海道開拓史に 雇われたトーマス・アンチセルが 開拓使次官 黒田清隆に亜麻の重要性 を報告し世界各地から亜麻種子を 取り寄せ、官園で試験栽培させました。 アイルランドの科学者 トーマス・アンチセル (1893-1893) の肖像 1879 年(明治 12 年)ロシア特命全権 公使 榎本武揚が繊維を採るノウハウ を持って帰国しました。さっそく 機械を模造して繊維製造試験をしま した。記念すべき北海道第一号リネン が誕生した瞬間です。 シャルルマーニュ皇帝 アルブレヒト・デューラー (1471‒1528) 榎本武揚 (1836-1908) (5)中世 フランク王国の王、後の西ローマ帝国の皇帝/カール(シャルルマー ニュ)大帝 [742~814年 ] は、食用・薬用として亜麻栽培を義務付けて いました。他にも、中世ヨーロッパでは多くの首長が亜麻栽培を奨励して いました。また亜麻は重要な繊維作物として栽培され、布の生産が盛んに 行われていました。また亜麻の種から取れる油は、薬や塗料などに使われ ていました。なお、ヨーロッパで木綿が定着するのは大航海時代以降です。 それまで繊維といえば亜麻のことを指すほど、一般的な衣類などに用い られました。 (6)近世〜現代 1617年 カナダ人の農民ロイス・へバートがケベックに亜麻を 持ち込みました。これが北米への最初の伝播だと言われています。 1690年 元禄時代の日本に、中国から薬用油として伝わりました。 中国では亜麻の種(アマニ)は漢方の一種として扱われていました。江戸 時代の記録には小石川の幕府の植物園で栽培された記録もありますが、 中国から比較的容易に入手できたことから、国内での栽培は定着しません でした。 8
3.亜麻と文化 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻と文化について、解説していきます。 「もぐらとずぼん」 (1967 年 福音館書店) エドアルド・ペチシカ ( 文 )、 ズデネック・ミレル ( 絵 )、 うちだりさこ ( 訳 ) (1)チェコの絵本「もぐらとずぼん」 (1967 年 福音館書店) エドアルド・ペチシカ ( 文 )、ズデネック・ミレル ( 絵 )、うちだりさこ ( 訳 ) もぐらは青いズボンがほしてあるのを見つけ、ほしくてたまらなくなり ます。ですが、どうやったら手に入るのかがわかりません。ひとまず、いろ んなことを知っていそうなちょうちょうを追いかけますが、いきなり川に 落ちてしまいます。そこにはえびがにがいました。ズボンについて聞くと、 きれを持ってくれば形に合わせて切ってくれるといいます……。青いすて きなズボンを手に入れるまでのもぐらの働きを、コミカルに描きます。 (福音館書店 HP より) チェコの国民的キャラクター、もぐらのクルテクがリネンのズボンを 作る奮闘記。森の仲間たちに、いろいろな工程で協力してもらう様子が とても可愛らしい絵本です。 9
3.亜麻と文化 出典:wikipedia タイトル : グリムの家庭物語、1912 年。グリム兄弟、マリアン・エドワーズ ( 翻訳 )、R・アニング・ベル ( イラスト ) (2)グリム童話「糸くり三人女」 ある怠け者の娘は、糸紡ぎが大好きな、働き者であると偽り、王子と結婚 します。しかしその証拠の品として、亜麻の糸を紡いだのは 3 人の女。 女たちは亜麻の糸紡ぎにはうってつけの風貌と身体的な特徴を備えて いますが、それを知った王子は、自分の妻がそうなってしまっては困ると、 糸紡ぎを一生させないと告げます。 こうして娘は大嫌いな亜麻糸紡ぎから解放されました。 (3)クロード・ドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」 (フランス 1890 年) ドビュッシーの前衛的で、視覚的な印象や感性的なイメージに基づいて 作曲された印象派的なピアノ曲です。フランスの民謡風の旋律を持ち、 優しく懐かしい雰囲気があります。 また、 左手の和音による伴奏が、 曲全体に 深みを与えています。題名からもわかるように、亜麻色の髪を持つ乙女に ついて描写しており、音楽を通して感情を表現することの可能性を示しま した。この曲は、繊細で感性的な旋律と、美しい和音が特徴的であり、聴く 者を魅了する魅力的な曲です。 またこの歌曲はフランスの詩人ルコント・ド・リールの同名の詩 「亜麻色の髪の乙女 (La fille aux cheveux de lin)」をもとに作曲されました。 10
3.亜麻と文化 有島武郎旧邸 札幌市南区にある札幌芸術の森では 1913年(大正2年)に建てられた邸宅を見学できる (4)有島武郎「カインの末裔」 (1917 年) 明治末〜大正時代に活躍した白樺派の作家、有島武郎の中編小説。 獰猛な欲望と生命力に突き動かされる農夫、仁右衛門(にえもん)。人間の 前に立ちはだかり圧倒する自然の猛威。羊蹄山のふもと北の大地を舞台 に、無知ゆえに罪を犯す主人公の焦がすような生のいとなみが描かれる。 なお、 「カインの末裔」とは、キリスト教において聖書に登場する人類の起 源と人間の宿命を諭す概念としても知られている。 参考 HP「青空文庫 カインの末裔 作品について」 この小説には主人公の農夫、 仁右衛門が仲間の忠告を無視して作付けした 亜麻が、ほかの作物が不作の中でも、豊作で儲かったというエピソードが 語られています。 11
3.亜麻と文化 ヤンファンエイク自画像 ヤンファンエイク 「アルノルフィーニ夫妻の肖像」 (5)油彩画 油絵の起源は、1世紀頃よりニスの代わりとして油を使った記述がロー マ人プリニウスの「博物誌」にあるようです。また5〜6世紀にはギリシャ 人アエティウスの著述にアマニ油・クルミ油をニスのように絵画に用い たとあるそうです。 なお油彩画は15世紀前半〜中頃、ファン・エイク兄弟によって完成 されたといわれています。弟のヤン・ファン・エイクはルネサンス期に おける初期の芸術家のひとりとしても知られており、写実的な描写や細密 画法、透明感あふれる色彩表現など、現実の物と見間違えるようなリアリ ティの高い描写で影響を与えました。 油絵具としての亜麻仁油は乾燥性が高く、耐久性に優れているため、 油絵に適した材料とされています。通常、亜麻仁油を顔料と混ぜて、絵具を 作ります。 亜麻仁油は、 顔料を均一に混ぜやすく、 また、 油絵具にツヤや光沢を 与える役割も担っています。 また亜麻仁油は安定性が高く、長期間保存することができます。これは、 油絵が乾燥すると、油分が酸化して硬化するためです。亜麻仁油は、この 酸化反応が速く、塗布した絵具が乾燥して硬くなるのが早いため、油絵に 使われることが多いのです。 12
4.亜麻と産業 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻と産業について、身近な用途を解説して いきます。 和名 英名 繊維名 分類 繊維の原材料表示 (家庭用品品質表示法) ぬめご flax リネン アマ科 麻 大麻 麻 hemp ヘンプ アサ科 ヘンプ ちょま からむし 苧麻 苧 rami ラミー イラクサ科 麻 jute ジュート シナノキ科 ジュート manila hemp マニラ麻 バショウ科 マニラ麻 漢名 あま 亜麻 たいま こうま 黄麻 つなそ 綱麻 マニラ麻 麻と呼ばれる植物 (1)リネン リネンは寝具を意味する単語としても使われますが、語源は亜麻繊維の 名称であるリネン(linen)です。汚れを落としやすく速乾性に優れる特徴が あります。かつてはシーツやテーブルクロスは亜麻の布で作られていました。 今でも高級ホテルやホワイトハウスなどではリネン製のものが使われて います。 さてリネン(亜麻の繊維)を取り出し、紡績する方法は時代と共に変わっ てきましたが、昭和初期、亜麻工場が盛んだったころの工程は以下の通り です。 生の茎 ➡ 浸水 ➡ 干し茎 ➡ 砕茎 ( さいけい ) ➡ ムーラン ➡ 櫛梳 ( くしすき ) ➡ 延線 ➡ 精紡 ➡ 糸 13
4.亜麻と産業 ● 浸水 琴似工場(札幌市)の池浸水の風景 亜麻の茎を池やタンクに満たし、 水に浸けます。 こうすることで、 茎の繊維 以外の部分が腐り、繊維だけを取り出しやすくします。水温の管理、浸水 時間の調整は難しく、職人技だったそうです。 ● 砕茎 ( さいけい ) 浸水した茎を乾燥させたのち、砕茎工程に入ります。茎を大きな歯車に かませることで、繊維以外の部分を砕きます。この際、繊維は強度が大きく 細いため切れることはなく、繊維以外の殻が砕けます。 ● ムーラン 砕いた茎を、ムーランと呼ばれる大きな扇風機のような機械の回転羽根 にぶつけます。こうすることで、繊維から殻を飛ばし、繊維だけを取り出す ことが出来ます。 ● 櫛梳 ( くしすき ) さらに、 櫛ですくことで、 きれいな繊維が得られます。 ここまでの工程の間、 長い繊維は正線、短いカスは粗線と呼ばれ仕分けされます。 ● 延線 延線機にかけます。この工程で、繊維を平行にし、質量を一定にします。 ● 精紡 紡績には2種類のやり方がありました。潤紡 ( じゅんぼう ) はお湯を 通した後に撚り乾燥させるやり方で、中番手以上の中細から細糸を撚る 時に行われました。乾紡 ( かんぼう ) は、潤紡のようにお湯を通さずに撚る 方法で、太目の糸に適用されました。 14
4.亜麻と産業 (2)食用油・種子 近年、ヘルスケア市場では亜麻仁油に含まれるオメガ3系 (n-3 系 ) 脂肪 酸であるα- リノレイン酸の機能性が大きく注目され、1日に必要な栄養 成分が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品として推奨さ れています。 (3)化粧品 アマニ油は皮膚親和性に優れ、閉塞性により皮膚の水分蒸発を抑え、 その結果として皮膚に柔軟性や滑らかさを付与するエモリエント性を 有すとされています。それらを配合目的とし、各種クリーム、メイクアッ プ製品、ヘアケア製品、ネイル製品などに使用されています。 (4)リノリウム 1860年代に英国のフレデリック・ウォルトン博士によって作られた 素材です。床材などに使われるリノリウム。この語源は亜麻の学名 Linum usitatissimum(リニューム ウシタティシマム) の属名部分 Linum です。リノリウムは亜麻 仁油、松ヤニ、石灰岩、木粉、コルク、ジュートなどから作られます。近年は 総天然素材の床材として、シックハウス症候群対策や抗ウィルス性、抗菌性 などから幅広く利用され続けています。また製造時の環境負荷が少なく、 処分時も有害物質が出ないことから、これからの地球環境にも適した素材 です。 15
4.亜麻と産業 油彩画用の亜麻仁油には様々なラインナップがあります (5)塗料・油絵具 亜麻仁油は乾性油として知られ、不飽和脂肪酸 (α- リノレン酸 ) を 50%以上含むことから空気 ( 酸素 ) に触れて固化する性質を持ちます。 乾性油は薄い膜にして空気中に放置しておくと、だんだん粘って比較的 短時間で乾いた膜を形成するので、絵具・ペイント・印刷インキなどに 最も適した油です。 また光沢のある丈夫な塗膜を作ります。 またリノリウムと 同様に、 天然素材であることからシックハウス症候群対策としても有用です。 (6)馬房敷物材 ヨーロッパや北海道内で競走馬の馬房敷物材(敷き藁)として利用され ます。亜麻の繊維を取った後の芯部分や表皮が原料で、 吸収性が高く (自重の 430%の水分を吸収)チップや藁よりも匂いを吸収し、害虫も寄せ付け ない効果があります。 (7)飼料(種子・搾り粕) 亜麻種子には水溶性の食物繊維と脂質を含むことから、腸の調子や毛艶 を整える効果があります。亜麻仁油に含まれるα- リノレン酸が、穀物主体 になりがちな飼料全体の脂肪酸バランスを整える効果もあり、種子には ポリフェノールのリグナンを豊富に含んでいます。 16
5.亜麻と食 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻と食について、解説していきます。 亜 麻 の 種 ゴ マ 0.1g ひまわりの種 ト す サ 20.0g じ 0.3g ロ 5.2g こ 5.1g バ 3.7g オメガ3(n-3)系脂肪酸含有量(可食部100g当り) ※亜麻のデータは、 ウィスコンシン州立大学 ポール・テスィト。その他食品は、五訂日本食品標準成分表(科学技術庁) (1)亜麻仁油・アマニ油 近年、その機能性から注目されるオメガ3(n-3) 系脂肪酸のα- リノレ ン酸が約50%と豊富に含まれているのが特徴です。 5年おきに公表される 日本人の食事摂取基準 ( 厚生労働省 ) に、摂取目安量が設定され、積極的に 摂ることが推奨される成分です。 オメガ3(n-3) 系脂肪酸は非常に不安定なため酸化しやすく、 体に有害な トランス酸に変性しやすいなど、油を搾る過程で慎重に扱わなくてはなり ません。亜麻仁油が注目されるのは、 植物性のオメガ3だからです。 魚油にも オメガ3はたくさん含まれていますが、亜麻仁油の製造工程はシンプルな ため変性が少なく、良質なオメガ3が得られるということなのです。 世界的な油脂学の権威であるウド・エラスムス氏は、動物性のオメガ3 (魚油)には見られない効果が植物性のオメガ3である亜麻仁油には見ら れる、といっています。 また、栄養機能食品表示にもオメガ3(n-3) 系脂肪酸は「皮膚の健康維持 を助ける栄養素」として表示が許されている、根拠の確かな唯一の脂肪酸 (油)です。 このほかにオメガ3(n-3) 系脂肪酸に期待される、効果効能について ご紹介いたします。 17
5.亜麻と食 ① 中性脂肪・コレストロール低減させ、脂質代謝を改善 オメガ3系脂肪酸由来のホルモンが体内のコレストロール値や中性脂肪の 対外排出を助けます。 ② 血圧の安定化 コレステロールや中性脂肪が下がることで、血流の流れがよくなり、 血圧が安定します。近年は機能性表示食品に、亜麻仁油の機能性として 「血圧が高めの方に対し血圧を下げる機能があることが報告されています」 と記された商品が販売されています。 ③ アトピー・アレルギー性皮膚炎の症状軽減 アトピーの症状である「かゆみ」などの炎症は、オメガ6系脂肪酸の摂り 過ぎが原因のひとつです。オメガ3系脂肪酸を摂り、オメガ3とオメガ6の 摂取バランスをとることで炎症が軽減されます。 ④ 美肌・エイジングケア オメガ3系脂肪酸が、皮膚のバリア成分セラミドの材料となります。 亜麻仁油を摂ることでお肌の乾燥を防ぎ、内側から皮膚の健康を整えます。 ⑤ 女性特有のお悩み改善 PMS( 生理前不順 )・更年期障害・ニキビなどでお悩みの女性は、ホル モンバランスが整うことで、これらの症状の軽減が期待できます。 18
5.亜麻と食 (2)種・種子・アマニ 亜麻の種子は、スムージーやヨーグルト、シリアル、グラノーラ、パン、 クッキーなど、様々な料理に使うことができます。使い方は、食べる前に 挽いてから摂ることが推奨されます。これは、種子の外側にある硬い殻を 砕くことで、栄養素が体内でより効率的に吸収されるためです。また加熱 調理は油脂が酸化する恐れがあるため、不向きです。 また栄養成分では上記の通り、オメガ3(n-3) 系脂肪酸に分類される α- リノレン酸、また食物繊維、リグナンの3つが、特徴的な成分です。 19
5.亜麻と食 30.5g 亜麻の種 20.0g 10.5g ゴ 10.8g マ 1.6g 9.2g 玄 米 3.0g 0.7g 2.3g さつまいも 2.3g 0.5g 1.8g り ん ご 1.5g 0.3g 1.2g 食物繊維合計 水溶性食物繊維 不溶性食物繊維 食物繊維含有量(可食部100g当り) ※亜麻のデータは、 ウィスコンシン州立大学 ポール・テスィト。その他食品は、五訂日本食品標準成分表(科学技術庁) ● オメガ3系脂肪酸 亜麻種子には、 α- リノレン酸というオメガ 3 系脂肪酸が含まれています。 これは、心臓病や糖尿病、関節炎などの病気のリスクを減らすのに役立ち ます。 ● 食物繊維 亜麻種子には、水溶性と不溶性の両方の食物繊維が含まれています。 これらの食物繊維は、便秘や下痢などの消化器系の問題を改善するのに 役立ちます。 ● タンパク質 亜麻種子には、植物性タンパク質が豊富に含まれています。これは、肉や 乳製品などの動物性タンパク質が摂れない人にとって、重要な栄養素と なります。 ● ビタミンとミネラル 亜麻種子には、ビタミン E、タンパク質の合成に必要なビタミン B1、 脳や神経系の健康に必要なマグネシウム、 骨の健康に必要なカルシウムなど、 多くのビタミンとミネラルが含まれています。 20
6.亜麻と当別町 亜麻は古代から人類の生活に欠かせない最古の植物の一つとして利用 されてきました。ここでは亜麻と当別町について、解説していきます。 製線工場全景 (1)亜麻の衰退 北海道石狩郡当別町と亜麻の歴史は、明治22年 (1889年 ) まで 遡ります。入植当時は食糧の自給が先決であったため、ソバ・麦・豆などが 作られたといいます。その後、換金作物として大麻などが普及すると、 開拓使の奨励作物として亜麻の栽培も始まったそうです。 一時は隆盛を誇った当別町の亜麻産業ですが、昭和2年 (1927年 ) に 火災によって工場が消滅しました。栽培自体は昭和40年頃 (1965年 ) まで行われていたようです。 21
6.亜麻と当別町 (2)亜麻の復活 それから約40年の時を経て、2002年当別町で亜麻栽培が復活しま した。当別町東裏の有限会社大塚農場の大塚利明さんが、有限会社亜麻公社 ( 当時は株式会社北海道技術コンサルタント 起業推進室 ) からの試験栽培 の依頼を受け、途絶えていた亜麻栽培の技術獲得に向け試行錯誤し、その 後、町内の青山地区などにも栽培は広がりました。 2007年には当別町亜麻生産組合が発足し、現在は「北海道亜麻ルネ サンスプロジェクト」として亜麻の栽培・製造・販売を一貫し事業を行っ ているとともに周辺地域や住民の協力のもと、 「亜麻まつり」 「亜麻カフェ」 「亜麻フォトコンテスト」など亜麻をテーマにしたまつり・イベントが開 催されています。 また、復活した亜麻の事業や景観は、2007年には農林水産省の『立ち 上がる農山漁村』に、2010年には北海道開発局の『わが村は美しく - 北 海道』に選ばれています。 22
参考文献 本書の制作にあたり種々の書籍などを参考にしました。本文中に注記して いませんが、以下に記し感謝を表します。なお、出版年順に記し年次は初版 の発行年次ではありません。 原 松次「北海道における亜麻事業の歴史」 , , 噴火湾社 ,1980 森田 恒之「画材の博物誌」 , , 中央公論美術出版 ,1994 前田 まゆみ「リネンが好き」 , , 文化出版局 ,2002 𠮷原 高志 ,𠮷原 素子「初版グリム童話集 , 1」,白水社 ,2012 池上 英洋「西洋美術史入門」 , , 筑摩書房 2017 ホルベイン工業技術部「絵の具の科学」 , , 中央公論美術出版 ,2019 西南学院大学聖書植物園書籍・出版委員会「聖書植物園図鑑」 , , 丸善プラ ネット株式会社 ,2019 ジャック・ルール/香山 学 監修 , 尾崎 直子 訳「リネンの歴史とその関連 , 産業」,白水社 ,2022 帝国繊維株式会社ホームページ 日本麻紡績協会ホームページ 制 作 監 修・協 力 亜麻のふるさと当別活性化協議会 有限会社亜麻公社 23