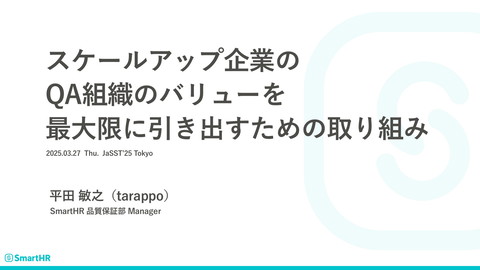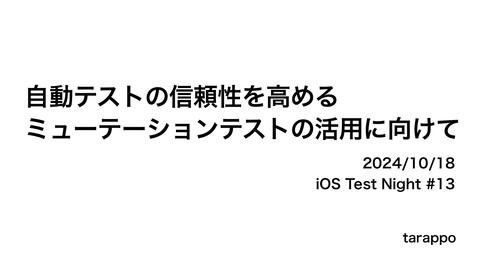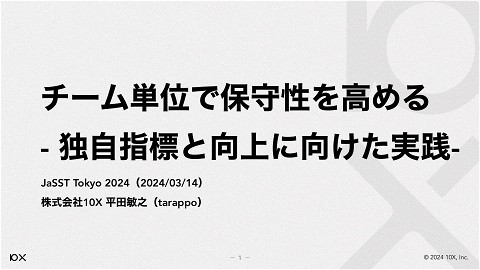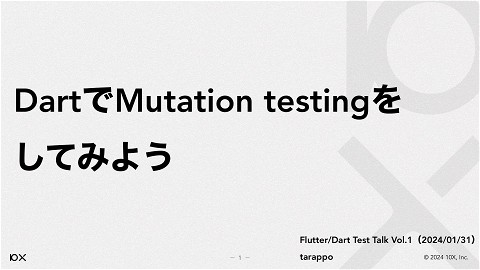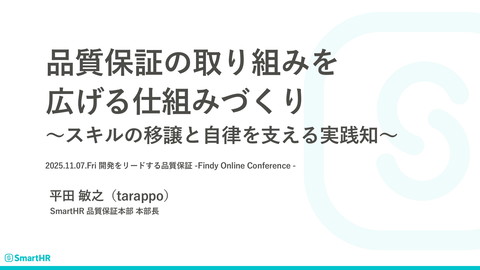組織全体で品質を担保するための品管メンバーとしてのさまざまな役割
13.7K Views
June 22, 24
スライド概要
2024/6/22(金) JaSST Kansai 24で発表した資料です。
関連スライド
各ページのテキスト
©︎ 組織全体で品質を担保するための 品管メンバーとしてのさまざまな役割 JaSST Kansai 2024(2024/06/21) 株式会社10X 平田敏之(tarappo) 1 2024 10X, Inc.
©︎ 自己紹介 平田敏之(tarappo) かんたんな経歴 • DeNA SWET → 10X(2022/04 -) 領域 ・「開発生産性の向上」「品質の担保」をミッション 2024 10X, Inc.
©︎ JaSST Kansai 24 - アブストラクトより 皆さんはどのようにして「プロダクトの品質」を担保していますか? そのための活動はテスト実施以外にも多岐にわたります。 ① しかし、これらの活動を品管メンバーだけで実施するのは難しいです。 10Xでは、品管メンバーがリードしながら、組織全体で品質を担保するために様々 な取り組みを行っています。 ② 例えば、開発チームの一員としての活動や、組織全体への働きかけなどです。 本発表では、弊社で実際に行っている事例を基に、組織全体で品質を担保するため の具体的な取り組みを一つ一つ紹介していきます。 これにより、皆様が自社での品質向上に役立つ具体的なヒントを得られることを 願っています。 3 2024 10X, Inc.
©︎ ①についてのお話 皆さんはどのようにして「プロダクトの品質」を担保していますか? そのための活動はテスト実施以外にも多岐にわたります。 ① しかし、これらの活動を品管メンバーだけで実施するのは難しいです。 10Xでは、品管メンバーがリードしながら、組織全体で品質を担保するために様々 な取り組みを行っています。 ② 例えば、開発チームの一員としての活動や、組織全体への働きかけなどです。 本発表では、弊社で実際に行っている事例を基に、組織全体で品質を担保するため の具体的な取り組みを一つ一つ紹介していきます。 これにより、皆様が自社での品質向上に役立つ具体的なヒントを得られることを 願っています。 4 2024 10X, Inc.
©︎ 「プロダクトの品質の担保」は誰がコミットメントするか 「プロダクトの品質」という面において「得意」なのはQAに関する職種のメンバー QAエンジニア、テストエンジニア、SETなどなど QAに関する職種のメンバーは (一般的に)「プロダクトの品質」に関することについてコミットメントを求められる ※ただし会社によってやることの範囲やその詳細は(大幅に)異なる 「プロダクトの品質」はどのように担保すればいいのでしょう? コミットメント=「QAに関する職種のメンバー」だけで全てを担うべき、担える? ※QAに関する職種=以後、弊社にあわせて品管メンバーと呼びます 5 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトの品質のためにおこなっていること プロダクトの品質を担保していく上でなにをおこなっていますか? 今おこなっていること、おこないたいこと列挙すると書ききれないぐらいありますよね • テスト設計、テスト実施 • 不具合分析 • 仕様レビュー • E2Eテスト(UIテスト)の実装 • プロセス整備 技法や手法はたくさん ある などなどなどなど 結局、これらを駆使してどうしたいのか 「良いプロダクトを世に早く出せるようにしたい」 ※ 良いプロダクトとはの定義については一旦ここでは割愛 6 2024 10X, Inc.
©︎ 良いプロダクトを世に早く出せるようにしたい (1)「だれが?」 (2)「どうやって?」 「品管メンバー」だけが やれること/やるべきことはたくさん ・おこなうべきものか? ・なにをおこなう? ・おこなえるものか? ・なにを優先するべき? メンバーのスキルだけ 品管メンバーだけで で全てできるか? 足りるのかどうか? 7 2024 10X, Inc.
©︎ すべてにおいて品管メンバーだけでできる必要はないはず もちろん • 品管メンバーの「スキルアップ」は重要 • 「品管メンバー」をふくめた組織体制の構築も重要 「プロダクトの品質」の担保はむずかしい • やること、やるべきことは多い • それらを品管メンバーだけで「すべて」やることはむずかしい 「品管メンバー」だけで「すべて」をおこなう必要はない 品管メンバーがリードしながら組織全体で動くことが大事 8 2024 10X, Inc.
©︎ 良いプロダクトを世に早く出せるようにしたい (1)「だれが?」 (2)「どうやって?」 「品管メンバー」だけが やれること/やるべきことはたくさん ・おこなうべきものか? ・なにをおこなう? ・おこなえるものか? ・なにを優先するべき? 組織全体で動くほうができる 組織全体で動くほうが早い 品管メンバーがリードしつつ進める ことは多い たりないスキルセットのところは「組 織全体」で補ってもらう 9 2024 10X, Inc.
©︎ 組織内で一緒に動くためにはどうすると良いのか 品管メンバーが淡々とタスクを進めていく • それだけで自然に「組織内」でなにかしらが動き出すのかどうか? • 組織内で一緒に動けるようになるのかどうか? 品管メンバーだけが闇雲に動いていても「勝手に」組織でコラボレーションは発生しない 「コラボレーション」に至るまでには「その前段階」の状態がいくつか存在する 2024 10X, Inc.
©︎ 組織内で一緒に動くためのステップ まずは品管メンバーがリードしながら進めていく 認知 存在、行ってることを知ってもらう コミュニケーション コラボレーション 関わりながらタスクを進めていく 「チーム」で一体となって動く 品質にまつわることを知ってもらう 11 2024 10X, Inc.
©︎ 組織全体で品質を高めるために 前提: • 組織、チームの状況によりステップを上げる難易度は異なる • ステップをクリアしても前のステップのことを一切やらなくていいわけではない ステップ 1. 品管メンバーの「存在」を認知 2. 品管メンバーの「活動」を認知 ステップを上げることで 組織で守っていける 3. 品管メンバーとコミュニケーション 4. 品管メンバーとコラボレーション 5. 品管メンバー関係なく自発的に様々なアクションが発生する 12 2024 10X, Inc.
©︎ 言うは易し行うは.. 大前提:「会社」によって「アプローチ」の方法は異なる(はず) 私たちが先程のステップを登っていくためにおこなってきたことをステップごとに時系列 で紹介していきます。 全てにおいて「そのまま」適用できるわけではないはずです。 ただし、なにかしらの参考にはなるとは思います。 13 2024 10X, Inc.
©︎ 弊社(10X)での事例を紹介 14 2024 10X, Inc.
©︎ ②についてのお話 皆さんはどのようにして「プロダクトの品質」を担保していますか? そのための活動はテスト実施以外にも多岐にわたります。 ① しかし、これらの活動を品管メンバーだけで実施するのは難しいです。 私の入社直後から時系列に沿って話をしていきます 10Xでは、品管メンバーがリードしながら、組織全体で品質を担保するために様々 な取り組みを行っています。 ② 例えば、開発チームの一員としての活動や、組織全体への働きかけなどです。 本発表では、弊社で実際に行っている事例を基に、組織全体で品質を担保するため の具体的な取り組みを一つ一つ紹介していきます。 これにより、皆様が自社での品質向上に役立つ具体的なヒントを得られることを 願っています。 15 2024 10X, Inc.
©︎ 組織 • Our Mission:10xを創る プロダクト • 2020年:ネットスーパー・ネットドラッグストアの立ち上 げと成長を支援する「Stailer」ローンチ • 2024 10X, Inc. 2024年:Stailer導入企業(13社) Culture Deck https://speakerdeck.com/10xinc/zhu-shi-hui-she-10x-culture-deck
©︎ チェーンストアECに特化した EC/DXプラットフォーム お客様アプリ スタッフアプリ 配達スタッフアプリ 17 2024 10X, Inc.
©︎ 1つ1つが むずかしい領域 広いカバー範囲 18 2024 10X, Inc.
©︎ 最初の状況(組織面) 入社時点での状況 • 私(tarappo)が1人目の弊社(10X)の品管メンバー • 入社時点で複数名の第三者検証会社の方が関わってくれている • ただし数ヶ月前に関わりだしてくれたぐらいの時期感 • 品管メンバーがすべてのリリースには関われていない • プロセスなどが整っておらず現在の「状況」が定量的にわからない • 今までに品管メンバーと一緒に働いたことがない人がいる • チームは「パートナー単位」だが品管メンバーは入っていない などなど 19 2024 10X, Inc.
©︎ 最初の状況(プロダクト面) 入社時点での状況 • プロダクトの難しさ • 範囲は広く1つ1つの領域がむずかしい • 個別性が多数あり、複雑性が高い • • コードの認知コストが高い状態 リリース • 今後の新規パートナーのローンチ計画が複数ある • 複数の既存パートナーがいて機能改修、修正が必要 • 障害が定期的に発生している などなど 20 2024 10X, Inc.
©︎ 最初に考えたこと • 今、関われている範囲を増やさないと厳しい • • 巻き込まれていく必要性 品管メンバーだけですべてを進めるのは厳しい • 巻き込んでいく必要性 組織で進めていく必要がある 21 2024 10X, Inc.
©︎ 最初のターゲット 品管メンバーがリードしながら進めていく ここはまだ厳しい 認知 知ってもらって 巻き込んでもらう コミュニケーション コラボレーション 巻き込みながら 進めていく 22 2024 10X, Inc.
©︎ 最初にターゲットとしたステップ 最初の時点でやるべき、できるであろうと判断したステップは1〜3 このステップを強化して次につなげていくことにした ステップ 1. 品管メンバーの「存在」を認知 知ってもらって巻き込んでもらう 2. 品管メンバーの「活動」を認知 3. 品管メンバーとコミュニケーション 巻き込みながら進めていく 4. 品管メンバーとコラボレーション 5. 品管メンバー関係なく自発的に様々なアクションが発生する 23 2024 10X, Inc.
©︎ 最初におこなったこと 1. 品管メンバーの「存在」を認知 認知度向上活動 2. 品管メンバーの「活動」を認知 相互に影響 3. 品管メンバーとコミュニケーション 品管メンバーがメインですすめる プロダクトを守る活動全般 これらは「直列」ですすめるのではなく「並列」でいろいろと進めていく 1、2が3につながっていき、3での活動が1、2へにもつながっていく 24 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 前提 • 誰もが品管メンバーと働いたことがあるわけでもない • QAということに対する解像度は人によって(だいぶ)異なる ・なにを頼めるかわからない ・なにができるかわからない ・なにを行うのかわからない などなど おこなったこと(の例) • 目指すべきQAの姿の立案と共有 • 全社員との1on1 • 品管週報 • 入社時オンボーディング • 全社ミーティングでの定期的な報告 • 社外へのアウトプット 霧を無くそう! 25 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動の実施タイミング はじめるのに適したタイミングはある • 目指すべきQAの姿の立案と共有 • 全社員との1on1 • 全社ミーティングでの定期的な報告 • 入社時オンボーディングの実施 • 品管週報 • 社外へのアウトプット 終了 終了 入社時点 26 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 目指すべきQAの姿の立案と共有 目的 • 目標とするQAの姿、その姿を目指す理由を把握してもらう • 社内:「ToBe」を知ってもらう、「見ている方向」を同じにする • 社外:同じ方向を目指したい人に興味を持ってもらう おこなったこと • 社内向けページにドキュメント(Notion)を用意 • • 上記ページを使って社内発表 アウトプット • ブログ発信:https://10x.co.jp/blog/10xblog/qa-team-interview/ • Podcastなど 27 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 目指すべきQAの姿の立案と共有 この姿を目指すには「コラボレーション」が重要 https://10x.co.jp/blog/10xblog/qa-team-interview/ 28 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 全社員との1on1 目的 • 「存在を認知」してもらう • なにかあったときに「あ、そういえばあの人がいる」と思い出してもらうだけで良い • 組織のメンバーを少しでも知る • 知られている・知っているだけできっかけになる おこなったこと • 全社員とカジュアルな1on1の実施 • 人によって話す内容は変えていく • 「存在を認知」レベルでもいいし、「品質に課題感を持っている人」にはその手の話 しをしたりする 29 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 全社ミーティングでの定期的な報告 目的 • 全社員と関われるわけではないので「変化」を全員にしってもらう • 「定量的なデータ」を共有し、現状を説明する おこなったこと 整備した情報を元に説明 • 「体制」がどう変わったか、どう変えたか • 「プロセス」がどう変わったか、どう変えたか • 関わってきた案件がどれぐらいか、どれぐらい増えたのか 30 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 入社時オンボーディングの実施 目的 • すでにいるメンバーと新規のメンバーのQA視点を少しでも同じようにする おこなったこと 次について共有する • (1)「目指すべきQAの姿」のところで共有したのと同様の内容の説明 • (2)現状の体制やできていること・できてないことの共有 • (1)、(2)に対する質疑応答 31 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 品管週報 目的 • 品管チームとして「なにをおこなっているのか」を知ってもらう • 「存在」の認知と「活動」の認知 • 特に初期は関われている方も少ないため おこなったこと 週報に書く内容は組織の状況によって変化させていく • どういった案件を対応したのか • なにに課題をもっているのか • 今週、良くやったことはなにか 32 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動 社外へのアウトプット 目的 • 得られた知識の言語化をすることでより理解が深まる • • 社内へ共有することによる知識の循環 社外への認知度向上 = 採用活動にもつながる おこなったこと • 自分たちが得た知見を社外へアウトプット • ブログ • 登壇 • Podcast 33 2024 10X, Inc.
©︎ 認知度向上活動の結果 霧は減った! 各施策の効果もありコミュニケーションの敷居は下がった 結果 • • なにかしら「相談事項」は以前と比べて増えた • 「品質にまつわること」は基本的に相談される • 知らないところで品質に関する施策が進むということは基本的にない ※全てのことに関われるわけではないが関わるべきかどうかの判断はできるのが大事 34 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 品管メンバーが「リード」しつつ次を進める (※リードの度合いは内容によって異なる) おこなったこと(の例) この情報(過程・結果)を関係者に共有 • 組織体制の検討と推進 • テストプロセスの整備 • 不具合チケットの整備と不具合分析 • 障害報告の整備と障害分析 • システムテスト ステップ1、2につながる 品管がメインでリードして手を動かしており、コラボレーションまで至っていない 35 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般の実施タイミング はじめるのに適したタイミングはある • 組織体制の検討と推進 • テストプロセスの整備 開発チームに委譲 • 不具合チケットの整備と不具合分析 開発チームに委譲 • 障害報告の整備と障害分析 • システムテスト 入社時点 36 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 組織体制の検討と推進 担当者 • 品管メンバーが「リード」:担当者1名 解像度がより高い「品管側」が主体的に動いていく必要がある おこなったこと • プロダクトの状況、チームの状況に応じて「品管メンバーの体制」について検討 • 今後の体制についても検討し、それに向けたアクション(例:採用周り)も実施 最初に想定した組織体制 • 現状のメンバー数、スキルを判断 = チーム専任はむずかしい • 「目指すべきQAの姿」から遠のいたとしても今取れる最善と思われる形を選択 37 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 組織体制 案件 (1)機能開発、修正 リリースされ続ける機 能開発、修正に対応 (2)パートナーローンチ 今後のパートナー ローンチに 向けての型化 38 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 テストプロセスの整備 担当者 • 品管メンバーが「リード」:担当者1名 おこなったこと 現状の組織体制にあわせたテストプロセスを整備 • 現時点でできないことはしない • 臨機応変にする前に「守」を優先する • 型化することを優先 • チーム単位での独自性は基本もたない • ※状況(メンバー数や組織状況)に応じて更新していく※ 39 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 テストプロセスの整備 プロセスの変化 初期 関わるチームの増加 Updateを繰り返していく 関わるチームの増加 関わらずにリリースされる機能も多数あり ローンチにおいては別のプロセス 40 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 不具合チケットの整備と不具合分析 リリース前に見つかった不具合情報 担当者 • 品管メンバーが「リード」:担当者1名 おこなったこと(整備) 不具合チケットにおいて次を一つ一つ策定 • フォーマット • • 必要な入力内容の決定 決めた内容は関係者に周知 ライフサイクル • 一定期間は使い方に対してフォロー 状態について決定 ドキュメント化 41 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 不具合チケットの整備と不具合分析 リリース前に見つかった不具合情報 担当者 • 品管メンバーが「リード」:担当者1名 おこなったこと(分析) 特定期間の結果を元に分析を実施 • (1)結果をまとめて共有 • (2)結果を元にした改善施策を立案 • (3)改善施策を実施 トップダウン、ボトムアップ的な動き • (4)改善施策の結果が出ているかを確認 不具合分析 関係者への共有 巻き込みながら進めていく 42 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 不具合チケットの整備と不具合分析 不具合分析からのアクション例 不具合分析の結果 • 「仕様起因」の不具合が多い(約4割) • 仕様書がそもそも存在しない、仕様が決まっていない機能が多数ある おこなったこと • 関係者に上記の結果を共有 • PdMのメンバーによる「仕様書作成祭り」が発生 • 仕様書のtemplateが作成され、それをベースに仕様書が一気に作成されていった 結果 • 仕様起因にまつわる不具合は大幅減 • 仕様書があるという事実だけでなく、ここが課題になりやすいという認識も効果に 43 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 障害報告の整備と障害分析 リリース後に見つかった不具合情報 担当者 • 別チーム(SREチーム)のメンバーがリード • 品管メンバーとしてFBする形:担当者1名 おこなったこと(整備) • 障害報告のテンプレート • 障害報告プロセスの整備 • SREチーム が対応 その内容に対して品管視点でFB https://product.10x.co.jp/entry/2023/06/12/171003 44 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 障害報告の整備と障害分析 リリース後に見つかった不具合情報 担当者 • 品管メンバーが「リード」:担当者1名 おこなったこと(分析) 特定期間の結果を元に分析を実施 • (1)結果をまとめて共有 • (2)結果を元にした改善施策を立案 • (3)改善施策を実施 トップダウン、ボトムアップ的な動き • (4)改善施策の結果が出ているかを確認 障害分析 全体共有 巻き込みながら進めていく 45 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 障害報告の整備と障害分析 障害分析からのアクション例 障害分析の結果 • 障害が一定起こってきた重要機能においてさらにフォーカスして分析 • プロダクトコードの「複雑性」、あるべき仕様の「未確定」が大きな課題 おこなったこと • 特定チームの設立(トップダウン)と上記課題に向けたアプローチの推進 • 複雑性 → リファクタリング、リプレイスの実施 • • 必要なドキュメント、コードの整備など含め経営メンバーも入ったチームで推進 仕様の未確定 → 関係者と協議したうえで確定 結果 • 本領域に関する類似の障害の発生は基本的に起きていない 46 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 システムテスト アサイン先、アサインメンバーについて 前提 「理想」の姿はあるが、そこから遠ざかるとしても「今できること/すべきこと」に注力 • チームに専任で入るのは厳しい • リリースの種類を大きく次の2種類にわけてアサイン • (1)機能開発、修正 • (2)パートナーローンチ 決めたこと メンバー数、スキルを元に • チーム単位でなくリリースの種類単位でメンバーをアサイン 47 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 (1)「機能開発、修正」の対応 案件 前提 • チームに専任メンバーは厳しい • リリースにおいて関わる範囲を広げて (1)機能開発、修正 守りを広げたい おこなったこと • 窓口をたててアサイン調整 • この体制に沿って他チームと調整 48 2024 10X, Inc.
©︎ プロダクトを守るための活動全般 (2)「パートナーローンチ」の対応 前提 • チームに専任メンバーは厳しい • 今後ローンチが複数くる (2)パートナーローンチ おこなったこと • ローンチに向けた準備のためのチーム • 今後に向けて少しずつ型化 49 2024 10X, Inc.
©︎ この時点での変化・成果(1) おこなったこと • 現状を分析できる土台の整備 • • 改善サイクルを回せるための各種データ 組織体制の整備(守りの強化) • システムテストの対象範囲の拡充 • 今後に向けたローンチのための型化 結果 「認知度向上施策」との掛け算で次のような変化が発生 • 現状を分析できる土台の整備 • これで得られた情報を元に「トップダウン」「ボトムアップ」それぞれの動き 50 2024 10X, Inc.
©︎ この時点での変化・成果(2) 結果 • リリースする案件の多くに関わることが可能となった • 検証をしてリリースした案件においては障害は減った • 見つけるのが比較的むずかしい障害が生まれはじめた(障害分析のところと関連) 全体に関わる ことを宣言 https://speakerdeck.com/tarappo/zu-zhi-noli-tishang-ketoti-zhi-bian-geng-no1nian 51 2024 10X, Inc.
©︎ この時点での課題 「認知度向上活動」「プロダクトを守るための活動全般」により 関係者と「コミュニケーション」しながら進められている ステップ3までは 普通にできるように なった 良いプロダクトを世に早く出せるようにしたい まだ足りない 今のやり方をそのまま進めていくのでは到達できない 52 2024 10X, Inc.
©︎ 次へのステップにむけて 良いプロダクトを世に早く出せるようにしたい 対象となる「プロダクト」に向き合ってより良くする動きが必要 チーム、組織として一体となって動く = 「コラボレーション」が必要 組織体制の変化を実施し「次のステップ」へ進めていく 53 2024 10X, Inc.
©︎ 組織全体で品質を高めるために チーム内でコラボレーションできるようにしていく ステップ 1. 品管メンバーの「存在」を認知 2. 品管メンバーの「活動」を認知 3. 品管メンバーとコミュニケーション 次のステップへ 4. 品管メンバーとコラボレーション 5. 品管メンバー関係なく自発的に様々なアクションが発生する 54 2024 10X, Inc.
©︎ チーム内でのコラボレーションへ 品管メンバーが他メンバーと協業 認知 コミュニケーション コラボレーション チーム内で一緒に進める 55 2024 10X, Inc.
©︎ 組織体制の変化 コラボレーションできる体制に向けて • 現状 • 「窓口」をもうけて案件を一元管理する体制 • • [課題] チームに入れていない、関わるのが後手になりやすい 次のステップ • 一緒に作るという点 では足りない 各チームへメンバーをアサインする体制 「体制強化」の準備をすすめ、次の2ステップを実施 • (1)一部チームで専任アサイン • (2)(ほぼ)全チームで専任アサイン 開発体制が変わる タイミングで実施 56 2024 10X, Inc.
©︎ 開発チーム体制(FY23)の変更 パートナー単位からドメインベースの開発体制へ移行 品管メンバー 品管メンバー 品管メンバー 品管メンバー(兼) 参照:https://speakerdeck.com/10xinc/10x-purodakutobu-men-shao-jie-zi-liao?slide=11 57 2024 10X, Inc.
©︎ チームメンバーとしての動き メンバー数、スキル、チーム特性を元にアサインを決定 前提 • それぞれのチームによって特性がある • 必要なスキルセットが全チームにおいて同じとは限らない 動き方 • プロセスや守り方はチームで方針を決めていく • チームの一員として、チーム全体で動いていく チームの「外」でのコミュニケーションから チームの「一員」としてのコラボレーションへ 58 2024 10X, Inc.
©︎ 開発チーム体制(FY23) メンバー数、スキル、チーム特性を元にアサイン先を決定 品管メンバー Case 2 品管メンバー Case 1 品管メンバー 品管メンバー(兼) 参照:https://speakerdeck.com/10xinc/10x-purodakutobu-men-shao-jie-zi-liao?slide=11 59 2024 10X, Inc.
©︎ Case 1 お届けチームとは 前提:パートナーのスタッフが利用する機能が多い 複数の人がさわったり、状態が複雑になりやすい機能がある 60 2024 10X, Inc.
©︎ Case 1 お届けチームの例 • シフトレフトな取り組み • シフトライトな取り組み • リファインメントに参画し、受け入れ基準の • 実際にパートナーの店舗へ行き、リリース後の 策定を開発者と協力して行う アプリを使っている店舗スタッフの横で観察を している • 受け入れ基準がコードレベルな表現になっ • 運用上でカバーしている部分や、使いづらそ ている場合、「それってアプリ上の振る舞 いではどうなっているんですかね?」と問 いかけて議論している うな点を見つけて、次の改善に繋げている • 開発した機能に対して、ログを仕込むことで、 • そもそもの前提が見えない場合に積極的に どれぐらい業務のパフォーマンスが改善したの かをモニタリングしている 問いかけることで、チケット起票者のみが 把握している事象の言語化を行っている JaSST Review 23でのスポンサー発表より抜粋 https://speakerdeck.com/10xinc/10x-purodakutobu-men-shao-jie-zi-liao?slide=18 61 2024 10X, Inc.
©︎ Case 2 お会計チームとは • 前提:扱っているものから「特に」守りを強くするべきチーム 62 2024 10X, Inc.
©︎ Case 2 お会計チームの例 守りを強くする必要があるチームにおいて他とは違った形の「テストプロセス」を整備 • 自動テストを「いかに活用するか」にフォーカスした形 • (1)どう守るかを考えてプロダクトコード、テストコードをチェックしFB • (2)おこなうべきテストを「自動」「手動」テストの両観点から判断 • (3)判断した内容をもとにテスト実施しリリースへ JaSST Review 23でのスポンサー発表より抜粋 63 2024 10X, Inc.
©︎ Case 2 お会計チームの例 https://product.10x.co.jp/entry/okaikei̲qa 64 2024 10X, Inc.
©︎ この時点での変化・成果 チーム「外」からの関わりからチーム「内」への関わりへシフト • チーム内の一員として、そのチームに対して動くことができるようになった • (一部の)チームは、チームとして動けるようになった 横断的に「判断」からチームで「判断」への委譲 • 今まで横断的におこなっていたものの一部についてはチームに委譲 • チームによっては実施しなくてもいいものもある • やる、やらないの判断も任せる 65 2024 10X, Inc.
©︎ 次のステップに向けて 現状 • 一部のチーム「内」ではコラボレーションは起きており進められている 課題 • 品管メンバーがすべてに関わることの限界がある • 品管メンバーが介在せずに他メンバーの視点でのアプローチが重要 そのためには「定量的」なデータの共有やチーム外メンバーとのコミュニケーションの積 み上げが次につながっていく 66 2024 10X, Inc.
©︎ 組織が自発的に動き出す 品管メンバーがリードしなくても何かしらのアクションが発生 認知 コミュニケーション コラボレーション この先へ 67 2024 10X, Inc.
©︎ 組織全体で品質を高めるために チームに品管メンバーがいなくても動いていく状態にむけて ステップ 1. 品管メンバーの「存在」を認知 2. 品管メンバーの「活動」を認知 3. 品管メンバーとコミュニケーション 4. 品管メンバーとコラボレーション 5. 品管メンバー関係なく自発的に様々なアクションが発生する 68 次のステップへ 2024 10X, Inc.
©︎ 品管メンバーがリードしなくても「アクション」は発生 「定量的」な情報による課題、「定性的」な情報による課題 発生したこと(の例) CTO(経営メンバー)がリード 「保守性」をハンドリングできるようにするための独自指標の定義 EMの一員としてFB メンバーの一員として活動 各チームが推進 指標を元にしたアクションの立案と実行 69 2024 10X, Inc.
©︎ JaSST Tokyo 24での発表 https://speakerdeck.com/tarappo/timudan-wei-debao-shou-xing-wogao-meru-du-zi-zhi-biao-toxiang-shang-nimuketashi-jian 70 2024 10X, Inc.
©︎ CTO(経営メンバー)がリード Focusすべきもの 独自指標の定義 プロダクトの機能と実装を整理し、 開発チームが十分に管理可能な状態まで保守性を高める われわれにとって「管理可能な状態とは?」「保守性が高い」とは? そのためにはどういったものを見るべき、追うべきなのか? CTO主導で進めEM(私含む)と話した上で定義したのは次の4つの独自指標 • (1)運営自律性 • (2)機能適合性 • (3)テスト容易性 • (4)システム運用効率性 71 2024 10X, Inc.
©︎ CTO(経営メンバー)がリード 独自指標の定義 CTO主導で進めEM(私含む)と話した上で定義したのは次の4つの独自指標 (1)運営自律性 • • 定義:ネットスーパー運営が小売事業者で完結する機能が揃っている (2)機能適合性 • • 定義:プロダクトの機能群が提供価値に適した形になっている (3)テスト容易性 • • 定義:プロダクトに対する変更を検証するコストが低い (4)システム運用効率性 • • 定義:プロダクトが正常な状態を維持するコストが低い 72 2024 10X, Inc.
©︎ 指標についてのかんたんなまとめ 「提供機能についての話」 • 事業価値につながる機能を提供できている • 小売事業者側が機能を理解して使えている 「問題の発見コスト・対応コストの話」 • リリース前後に「問題」を見つけられる • 「問題」を見つけられるコストが低い • 「問題」を対応するコストが低い JaSST Tokyo 24でのスポンサー発表資料より抜粋 73 2024 10X, Inc.
©︎ 各チームが推進 独自指標導入と運用の結果 チーム単位で「独自指標を導入と運用」 どの指標をターゲットにするかなどアプローチについてチームで判断 チームによって進み方の差がでてきた • 数値が改善できるサイクルがまわるようになっているチームがある • 改善サイクルがまわしづらい構造になっているチームがある チームがわるいとかではなく次のような要因がある • 取り組むのが難しいモチモノを扱っている • 改善に向けてやるべきことが多い モチモノの整理やアプローチの仕方の検討などを通して次へつなげる 74 2024 10X, Inc.
©︎ 組織体制のアップデート 指標の定義、可視化によって「チーム内外」の人が現状を(ある程度)分かる これらの指標を元に判断できること • • コミットを強化するべきチームがより「明確」になった • 品質に対して自律性が高いチームもある • → 品管としてのコミットを弱めても平気といえる 「組織としての成果を最大化」するためのチームアサインを実施 • 品管メンバーの関わり方のグラデーションが「より」可能に 75 2024 10X, Inc.
©︎ 品質に対して自律性が高いチームとは? 品管メンバーがリードしないでも「品質面」に関して動ける • • 機能に対して • どのように守るべきかが判断できている • どこに影響があるかを判断できている 上記のような行為に対しての改善活動が進められている 自分たちのモチモノに対して 「ハンドリング」ができている状態 もちろんモチモノ全てではなくグラデーションはある 76 2024 10X, Inc.
©︎ 開発チーム体制(FY24)の変更 NEW データなどを元にした チーム体制の変化 NEW FY24 NEW 領域を分けた上で細分化 NEW 77 2024 10X, Inc.
©︎ 開発チーム体制(FY24)の変更 品管メンバー アサイン増 伸びしろが多い 品管メンバー 品管メンバーの アサインの 品管メンバー アサイン減 品管メンバー(兼) 品管メンバー グラデーション 品質における 自律性が高い 品管メンバー 人を増やせば解決というわけでなく適したスキルセットがある 78 2024 10X, Inc.
©︎ おわりに 「プロダクトの品質」を組織全体で担保するために弊社でおこなってきたことを紹介しま した。 次のステップを意識しつつ1つ1つ進めていき、今の状態になっています。 1. 2. 3. 4. 5. 品管メンバーの「存在」を認知 品管メンバーの「活動」を認知 品管メンバーとコミュニケーション 品管メンバーとコラボレーション 品管メンバー関係なく自発的に様々なアクションが発生する 一方、今の状態がゴールというわけではなく、まだまだやることはたくさんあります。 引き続き「組織」として進められていけるように全体をアップデートしていく予定です。 79 2024 10X, Inc.