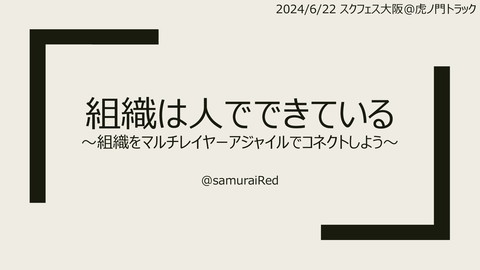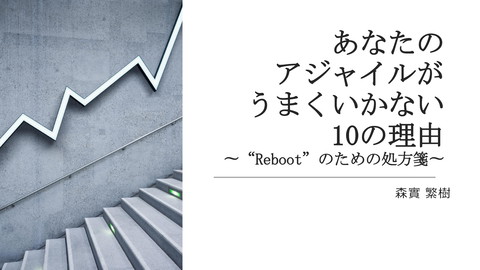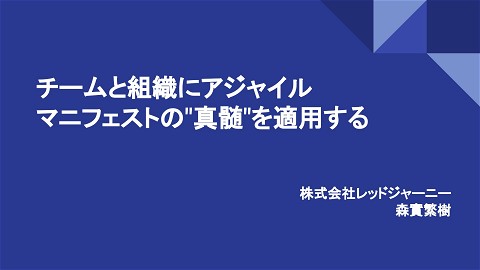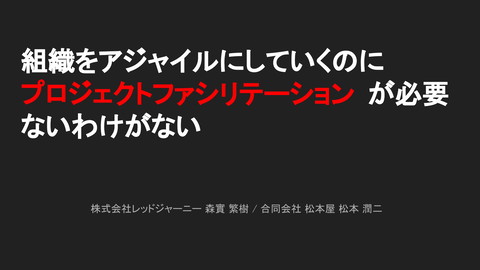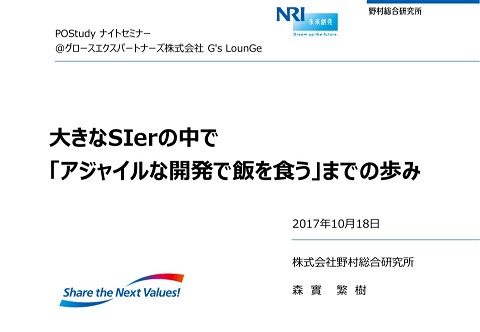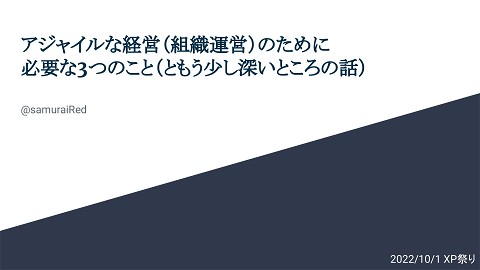【アジャイルラーニングウィーク】アジャイル型プロジェクトのためのアダプティブプロジェクトマネジメント
2.5K Views
November 25, 25
スライド概要
【アジャイルラーニングウィーク】アジャイル型プロジェクトのためのアダプティブプロジェクトマネジメント より
大手SIerでの開発/運用、大規模プロジェクトマネジメントを経験した後、ミドルベンチャーでCTO、通信系事業会社でエンジニアリングマネージャー、国立大学で非常勤講師などを歴任。プロダクト開発や組織づくりに造詣が深い。 2003年からアジャイルを実践しており、社内外問わずいくつものチーム、組織の支援を行ってきた。現在は、株式会社レッドジャーニーで認定スクラムプロフェッショナルとしてDX支援、組織変革に邁進している。 日本XPユーザグループスタッフ BIT VALLEY -INSIDE-ファウンダー 保険xアジャイルコミュニティ「.insurance」オーガナイザー 人材ビジネスxアジャイルコミュニティ オーガナイザー Agile Tour Yokohama実行委員 SWise株式会社、Pluslab株式会社外部顧問 ゼロからはじめるチームプロジェクトマネジメント著者
関連スライド
各ページのテキスト
【DAY1】 アジャイル型プロジェクトのための アダプティブ プロジェクトマネジメント アジャイルラーニングウィーク PRODUCED BY REDJOURNEY
森實 繁樹 株式会社レッドジャーニー Swise株式会社 外部顧問 Pluslab株式会社 外部顧問 国立筑波大学 非常勤講師 (所属ユニット) 侍塊s プロジェクトマネージャ保護者会 ITかあちゃんず (所属(運営)コミュニティ) 日本XPユーザグループ BIT VALLEY –INSIDE保険xアジャイルコミュニティ 人材業界ビジネスアジャイルコミュニティ Agile Tour Yokohama 2
私の経歴 2003-2006 富士通株式会社 SE 2006-2018 株式会社野村総合研究所 上級SE 2018-2020 LEVERAGES株式会社 技術顧問 2018-2020 レバテック株式会社 CTO 2020-2020 HAL東京 特別講師 2020-2021 株式会社MEDIBA SRMANAGER 2019- 国立筑波大学 非常勤講師 2021- 株式会社レッドジャーニー 2022- PLUSLAB株式会社 外部顧問 2023- SWISE株式会社 外部顧問
本日の前提(アジャイルジャパンより再掲) SIERで15年以上、事業会社で4年以上の経験から、 マネジメントの基本は、 ①中日程 ②体制図 にあると考えます。 ③課題管理表
本日のゴール 初手の初手として下記2つのイメージがもてること • プロジェクトマネジメントをスクラムの営みに取り入れる • アダプティブプロジェクトマネジメントを理解する
プロジェクトマネジメントを スクラムの営みに取り入れる
プロジェクトマネジメント ① どこへ向かうのかを決める(目的とゴールの設定) ② どうやってそこへ行くかを決める(計画と役割) ③ 途中でズレたら直す(進捗・リスク・変更の管理)
プロジェクトマネジメント ① どこへ向かうのかを決める(目的とゴールの設定) なにを達成するのか 成功の基準はなにか なにをやる/やらないか 「ゴールの地図をつくる」仕事
プロジェクトマネジメント ② どうやってそこへ行くかを決める(計画と役割) 必要な作業、順番、リスク 誰がどの役割を担うか 合意形成とコミュニケーションの設計 「進み方とチームの動かし方をデザインする」仕事
プロジェクトマネジメント ③ 途中でズレたら直す(進捗・リスク・変更の管理) 状況を見て判断し直す 想定外の問題を調整する ステークホルダーへ説明と合意形成を行う 「目的に向けて軌道修正し続ける」仕事
プロジェクトマネジメント ① どこへ向かうのかを決める(目的とゴールの設定) ② どうやってそこへ行くかを決める(計画と役割) ③ 途中でズレたら直す(進捗・リスク・変更の管理) 全然アジャイル型プロジェクトでも普通にやっていることですよね?
アジャイル型に特化した表現で説明した プロジェクトマネジメント ① 最初から全部決めない。まず“今わかっていること”だけ で始める。 ② 小さい単位でつくり、すぐにフィードバックをもらう。 ③ 学んだ結果にあわせて計画も目的も“編み直す”
アジャイル型に特化した表現で説明した プロジェクトマネジメント ① 最初から全部決めない。まず“今わかっていること”だけ で始める。 わからないことが多い前提 ゴールの“仮説”を置いて出発 必要に応じて方向を変えられるようにしておく 変化に強い立ち上げ方
アジャイル型に特化した表現で説明した プロジェクトマネジメント ② 小さい単位でつくり、すぐにフィードバックをもらう。 スプリント(短いサイクル)で試す 実際に動くものを見せる 顧客や利用者の声を、すぐ反映する 「早くつくる」よりも「早く学ぶ」ことが目的
アジャイル型に特化した表現で説明した プロジェクトマネジメント ③ 学んだ結果にあわせて計画も目的も“編み直す”。 毎回ふりかえって、やり方を調整する バックログを入れ替え、優先度を変える チームとして決める小さな意思決定を積み重ねる つくって終わりではなく、“学びながら方向性を最適化する”経営 に近い動き
プロジェクトとは 独自のプロダクト、サービス、所産を 創造するために実施する有期性のある 業務
これまでのプロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメントはプロジェクトマネージャのため プロジェクトマネージャは創造のための活動を行う 価値 ←一定(計画通り) ---------コスト↓ ←下げるマネジメント=費用対効果があがる
これからのプロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメントはチームのためのものとなり プロジェクトマネージャは価値創造のための活動を行う 価値↑ ←市場価値、顧客価値、ブランド価値向上 ---------コスト↓ ←下げるマネジメント=費用対効果があがる
つまり、ものづくりから価値づくりへの変化 だから変化に応じた マネジメントスタイルにしないといけない
立ち上げ 計画 Decide 方針決定 実行 管理・監視 Act 実行 Observe 観察 終結 Orient 情勢判断 プロジェクトのライフサイクルに再帰点を設けて、OODAループを取り込む
既存のガバナンス ソフトウェア開発標準 共通フレーム2007(「ソフトウェア開発の標準プロセス」)は、構想から開発、運 用・保守・廃棄までのライフサイクルを通じて、“何を実施すべきか”を定めた枠組 みとしてIPAが関与して策定 ISMS、ISO、PCI-DSS、監査等 何をどう判断してどうなったか、どう承認されたかをトレースすることでプロセスか ら品質を担保しようとする堅牢性の象徴
なので… 既存ガバナンスを大切にしながら アジャイルなプロジェクトを組み立てる
PMBOK第七版がアジャイルに準拠した??
つまり… 結局PMBOK第6版までに定義されている 活動を実行するしかないんです 今日はプロジェクト計画の話までします
プロジェクト計画書の主な8観点 • 目的と目標 • プロジェクトの特性 • スコープ • 役割と責任、体制 • アプローチ • 成果物・マイルストーン • リスクと制約 • コミュニケーション
目的と目標 目的は今も昔もあまり変わっていないはず 目標には以下が含まれる ・自社の目標 ・ユーザーの目標 ・チームの目標 ・個人の目標(事実上の育成計画) インセプションデッキ で取り込める内容
ここ
プロジェクトの特性 • ヒト • 事業 • アーキテクチャ • ツール
スコープ 何を達成するのかは、ものづくりではなく価値づくりなので、 価値基準がスコープにかわっている 逆に言うと、価値づくりを満たせればものづくりはなんでも よいということ つまり、途中でものづくりはかわる→P計画変更ではない 価値到達ができない場合→P計画変更
役割と責任、体制 ステアリングコミッティ アプリ横断会議 スプリントレビュー こうやって出した必要な会議体を、スクラムイベントの中、あるいは外に織り込む
役割と責任、体制
アプローチ ワーキングアグリーメントでもなんでもよいが、この特性、 このタイミング、このフェーズにあわせてどういうスタイル で実現するのかをスプリントプランニングに織り込む →スキルトランスファーを大事にするのでペアプロでETC…
成果物・マイルストーン 中日程、3ヶ月先~半年先まで決めよう 決めたらプロダクトバックログリファインメントで見直そう
リスクと制約 QCDSなんて最初からすべて制約 だからこそリスク管理をする必要がある →リスクは責任者に承認させて転嫁できることが重要 →リスク費用は使わなければ利益に直結するのでプロジェクトに判断権限はない →スプリントレビューやステアリングコミッティ、プロジェクト計画変更承認の場に もちだすこと
コミュニケーション ワーキングアグリーメントでもなんでもいいので、コミュニケーショ ンのパスを確立すること 何かをするための枠というのは形骸化しやすいので運用は注意が必要 なにかあったら使う枠、というとりかたも可、雑談枠みたいにするこ とも可、アジェンダのない会議という枠をとっておくのも可 そんなことしなくても会話できるチームでありたいけれど… ドキュメントの格納や証跡の残し方もコミュニケーション ガバナンスで要求されるものはコミュニケーション設計を正しくする
これまでのプロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメントはプロジェクトマネージャのため プロジェクトマネージャは創造のための活動を行う 価値 ←一定(計画通り) ---------コスト↓ ←下げるマネジメント=費用対効果があがる
これからのプロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメントはチームのためのものとなり プロジェクトマネージャは価値創造のための活動を行う 価値↑ ←市場価値、顧客価値、ブランド価値向上 ---------コスト↓ ←下げるマネジメント=費用対効果があがる
つまり、ものづくりから価値づくりへの変化 だから変化に応じた マネジメントスタイルにしないといけない
立ち上げ 計画 Decide 方針決定 実行 管理・監視 Act 実行 Observe 観察 終結 Orient 情勢判断 プロジェクトのライフサイクルに再帰点を設けて、OODAループを取り込む
• 『ゼロからはじめる • チームプロジェクトマネジメン ト』 • 2026/1/8 インプレスさんより発売します! • チームのみんなで一度読んでみてください! 40