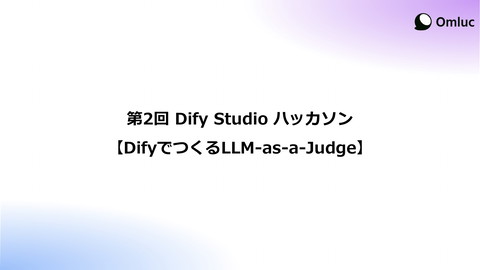コミュニティで実現する共創型AI推進: Dify Studioの実践事例
3.5K Views
October 24, 25
スライド概要
AI開発で陥りがちな「開発サイド」と「ビジネスサイド」のすれ違い。この根深い課題を、AIアプリ開発プラットフォーム「Dify」を"共通言語"として、いかに乗り越えていくかを具体的な事例とともに解説します。
2,000名規模へと急成長したコミュニティでのハッカソン運営を通じて、多様な専門性を持つ人々が化学反応を起こし、現場のリアルな課題を解決する質の高いAIユースケースが生まれるプロセスについてご紹介します。
関連スライド

Meta XR SDK(V66-74)でQuestアプリを開発
各ページのテキスト
コミュニティで実現する共創型AI推進 Dify Studioの実践事例 株式会社Omluc 代表取締役 岸⽥ 崇史
Contents 1 AI推進の課題とアプローチ 2 3 なぜDifyなのか 4 AI時代におけるコミュニティの価値 5 おわりに Dify Studioの共創型AI推進の紹介 2
自己紹介 TAKASHI KISHIDA Omluc Co., Ltd. CEO/ Dify Studio Founder 東京⼯業⼤学(現: 東京科学⼤)物質理⼯学院修了。味の素株式会社にて、機械学 習を活⽤した半導体材料開発に従事。フリーランスエンジニアを経て、2023年に ⽣成AI事業を⼿がける株式会社Omlucを創業。 Dify導⼊⽀援サービスをはじめ、 多くの企業の⽣成AI活⽤を⽀援。 UdemyのDify講座は受講者数2,500名を超える。 2,000名規模のDifyコミュニティ「Dify Studio」のファウンダー。 開発したアプリ「Deep Research」はDify公式テンプレートに採⽤され、公式ブ ログへの寄稿も⾏う。 【著書】 「Difyではじめる 業務効率化AIアプリ開発 AIを会社に根付かせる実践ガイド 」 (マイナビ出版) 3
1 AI推進の課題とアプローチ
AI推進における理想と現実 AI推進の難しさは、技術そのものよりも、 むしろ「人と組織」に根差した構造的な課題に起因することが少なくありません。 例えば 思ったより 業務効率化ができない ユーザーが欲しいものと 違うものができる PoC(実証実験)だけで 終わってしまう 作ったものが 現場で使われない 5
なぜAI推進は「現場のニーズ」と乖離するのか? AI開発の多くの課題は、「システムには詳しいが現場を知らない開発サイド(作る人)」と 「現場には詳しいがシステムを知らないビジネスサイド(使う人)」に共通の言語がなく、 互いに触れ合う機会も限られるため、連携しづらいという両社の分断から生じています。 AIを導入するスキルは持っ ているが、解決すべき現場 の課題が分からない・・・ 解くべき業務課題は山ほ どあるが、解決する方法 が分からない・・・ 開発サイド (作る人) ビジネスサイド (使う人) 作り⼿と使い⼿の分断 6
AI推進の課題解決アプローチ 開発サイドとビジネスサイドの両者を繋ぐ「共創」、その橋渡しができるツール選定が重要であり、 Difyを活用して両者の対話の場を交えながら開発を進めることが、企業のAI推進を加速させる鍵と なります。 真に解決すべき現場課題を 間近に触れ、AI開発に繋げ られる 開発サイド (作る人) 共創型AI推進 コミュニティ化 解くべき業務課題を伝え たら、驚くほどの速さで 解決に繋がる ビジネスサイド (使う人) 7
2 なぜDifyなのか
共創を生み出すための条件 優れた「共創」は、単なるコミュニケーションの活性化だけでは生まれません。プロジェクトの 土台として機能し、確かな成果を生み出す環境づくりには、2つの要素が重要です。 スキルによらず 議論に参加できること アイデアを即座に 形にできること
現場と開発の共通言語としてのDify AI開発の最大の壁は、開発サイドとビジネスサイドの「分断」です。専門知識がなくても理解で きるDifyの視覚的なインターフェースは、両者をつなぐ「共通言語」となり、現場のニーズを的 確に捉えたAI開発を可能にします。 業務の流れ データDL デ " タ 整 形 プ ロ ン プ ト ⼊ ⼒ 分 析 プ ロ ン プ ト ⼊ ⼒ 改 善 案 書 き 出 し Word DL 社 内 ツ " ル か ら デ " タ な ど に 資 料 化 データ整形 プロンプト ⼊⼒ 分析 資料化
アイデアを即座に形にする高速性 議論の中で生まれたアイデアは、実際に動くものにすることによって初めて価値が生まれます。 Difyの直感的な操作性は、アイデアから動くプロトタイプまでの開発を劇的に高速化します。 高速なPDCA 構築 検証
3 Dify Studioの 共創型AI推進の紹介
コミュニティ「Dify Studio」について Dify活用への高い熱量を持つメンバーが集まり、 現在2,000名規模へと急成長を遂げている、日本最大級のDify専門コミュニティです。 13
「共創」を加速させる2種類のDifyハッカソン Dify Studioでは、参加者のフェーズや課題感に合わせて、目的の異なる2種類のハッカソンを 戦略的に実施しています。 課題の深さ 第1回 ハッカソン:課題の”掘り起こし” 第2回 課題を持つ人 x 課題を解く人を 掛け合わせたブレスト型 第2回 ハッカソン:課題の”磨き込み” 一つの課題を全員で極める コンテスト型 第1回 課題の広さ 14
「共創」を加速させる2種類のDifyハッカソン Dify Studioでは、参加者のフェーズや課題感に合わせて、目的の異なる2種類のハッカソンを 戦略的に実施しています。 課題の深さ 第1回 ハッカソン:課題の”掘り起こし” 第2回 課題を持つ人 x 課題を解く人を 掛け合わせたブレスト型 第2回 ハッカソン:課題の”磨き込み” 一つの課題を全員で極める コンテスト型 第1回 課題の広さ 15
第1回 第2回 第1回Difyハッカソンのアプローチ 第1回のハッカソンでは、ビジネスサイトと開発サイドの壁を解決するために、戦略的なチーム組成 を行った上で、チームでユースケース創出からプロトタイプ開発まで一気通貫で実施しました。 課題 アプローチ ビジネスサイドと開発サイドの壁 現場の困り事を解決するためにDifyを触 ってみたけど、実際の業務に活かすまでは 作り込めてない... いろいろなことができるのは分かっている けど、実際に現場でどんな課題があるのか わからない... ビジネスサイドと開発サイドの 戦略的チーム組成 & ユースケース創出・プロトタイプ 開発を一気通貫で実施 16
第1回 第2回 「化学反応」を狙ったチーム組成 ハッカソンでは、「課題を持つ人」と「課題を解く人」を意図的に混合させ、 各チームで化学反応が起きることを狙いました。 業界に関しての深い知見や経験がある課題を持つ人たち コンサルタントやエンジニアなど課題を解く人たち 金融 マーケティング メディア・エンタメ 公共・官公庁 製造・工業 不動産・建設 17
第1回 第2回 プレゼンテーションに向けたディスカッション 当⽇結成されたチームでディスカッションし、短時間でプレゼンテーションまで⾏う。 18
第1回 第2回 「共創」が生んだ多様なAI活用ユースケース 多様な専⾨性が掛け合わされた結果、各業界特有の課題を解決する、 質の⾼いAI活⽤アイデアとプロトタイプがわずか数時間で⽣まれました。 金融 マーケティング メディア・エンタメ 市場情報分析エージェント SEO記事エージェント バナー⾃動⽣成 市場の最新情報を分析し、部署内 の特定の⼈にアクションを提案 検索流⼊強化や旧記事をリライト する際に、短期間で記事を⽣成 既存のLPから訴求内容とデザイン を同時に⾃動⽣成 公共・官公庁 製造・工業 不動産・建設 都⺠ボイスリサーチ 暗黙知のドキュメント化 不動産法令適合チェック 政策に対しての都⺠のリアルな反 応をもとに政策企画書を作成 PCに不慣れでも⾳声⼊⼒で、暗黙 知をドキュメント化 対象物件に対して、⾃治体の条例 などから適合性をチェック 19
第1回 第2回 例:不動産チームのアイデア創出プロセス 不動産チームでは、「物件の法令チェック」という具体的な業務課題に対し、 Difyの機能を駆使したソリューションを構築しました。 20
第1回 第2回 Difyによる高速プロトタイプ開発 ハッカソンで⽣まれたアイデアを、 Difyの直感的なインターフェースを使い、その⽇のうちに動くプロトタイプとして実装しました。 入力した物件情報をもとに、 その物件が属する区を判別し、 区によってその後のフローを分岐する 該当する区の条例を Difyナレッジから取得する 条例への適合/不適合を判断し、 情報をまとめる 21
デモ:不動産法令チェックワークフロー 第1回 第2回
第1回 第2回 専門家の知見に基づく判定レポート このワークフローは、単に法令との適合性をチェックするだけでなく、不動産の専⾨家が⾏うよう な多⾓的なリスク分析までを⾃動で⾏います。
「共創」を加速させる2種類のDifyハッカソン Dify Studioでは、参加者のフェーズや課題感に合わせて、目的の異なる2種類のハッカソンを 戦略的に実施しています。 課題の深さ 第1回 ハッカソン:課題の”掘り起こし” 第2回 課題を持つ人 x 課題を解く人を 掛け合わせたブレスト型 第2回 ハッカソン:課題の”磨き込み” 一つの課題を全員で極める コンテスト型 第1回 課題の広さ 24
第1回 第2回 第2回 Difyハッカソンのアプローチ(1/2) 第2回のハッカソンでは、ビジネスサイトと開発サイド両社が抱える問題解決経験の不足を課題に対 して、実践力を磨くための課題解決コンテストを実施しました。 課題 アプローチ 問題解決経験の不足 実際に現場で使えるような、クオリティの 高いアプリケーションを作れるようになり たい... 実践力を磨くための 「課題解決コンテスト」 アプリケーションの精度を高めるための ベストプラクティスを知りたい.... 25
実践力を磨くための「課題解決コンテスト」 実在する企業のリアルな課題をテーマにした、 アプリケーションの精度を競うコンテスト形式のハッカソンを開催しました。 26
ビジネスのリアルを追求したコンテスト設計 参加者全員が同じ条件下で開発に臨めるよう、実際の業務で利用されるリアルなデータセットを提 供。さらに、ビジネスで必須となるコストと速度の観点から、あえて厳しい制約条件を設けました。 27
第1回 第2回 第2回Difyハッカソンのアプローチ(2/2) 第2回のハッカソンでは、100を超えるオンライン・オフラインのハッカソン参加者が開発した プロトタイプの公平な評価を、LLM-as-a-Judgeを利用したAI評価システムを活用して達成しました。 課題 アプローチ 公平かつ大規模な評価の実施が困難 100を超える全アプリケーションを、 限られた時間の中で、複数の審査員が 公平な基準で評価することは、現実的 にほぼ不可能ではないか… LLM-as-a-Judgeを利用した AI評価システムの活用 28
第1回 第2回 LLM-as-a-Judgeを利用したAI評価システム 参加者が開発した全アプリケーションに対し、Difyで構築した評価システムがアプリケーションを スコアリングし、結果をスプレッドシートにリアルタイムで集計します。 AI評価システム アプリケーションA 90点 アプリケーションB 70点 アプリケーションC 45点 アプリケーションD 60点 アプリケーションE 80点
第1回 第2回 複雑な評価フローもDifyで実装 Difyのプラグイン機能を駆使することで、 多数のチャットボットを同時に、かつ自動で評価する高度なワークフローを実装しました。 30
第1回 第2回 競争が生まれるリアルタイムスコアリング 参加者が開発したアプリケーションの精度は、評価システムによって一定時間ごとに自動採点。 更新され続けるランキングが、ハッカソンにライブ感をもたらしました。 31
「競争」の後は「協調」へ ハッカソンの最後には、成績上位者が自身のノウハウや実装アプローチを惜しみなく共有。 競い合った経験をコミュニティ全体の財産へと変える、知見共有の場を設けました。 32
SNS上での参加者の声 ハッカソン後、SNS上には参加者からの熱量の高い感想が数多く投稿されました。これらの声から、 参加者が感じた価値が見えてきます。 33
4 AI時代における コミュニティの価値
AI時代におけるコミュニティの価値 Dify Studioでの実践を通じて、 共創型AI推進を成功させるためには、以下の3つの要素が不可欠であると私たちは考えています。 実践を通じた 「スキルと経験」の獲得 多様な人材による 「化学反応」 挑戦を称え、 学びを共有する「文化」 35
イノベーションの土壌となる「多様性」 Dify Studioは、IT・ソフトウェア業界がコミュニティの中核を担いつつも、製造、コンサル、金 融といった、AI活用の現場となる多様な業界からメンバーが集う、まさに「共創」のための交差点 となっています。 36
世代と役職を超えた「知の融合」 Dify Studioには、経験豊富なベテランから未来を担う若手まで、そして現場の実務担当者から経 営の意思決定者までが集結。多様な視点が交差することで、多角的な議論とイノベーションが生ま れます。 37
学びを全体に還元する「知見共有の文化」 Dify Studioでは、イベントの場で有志のメンバーが自身の学びや発見を共有するLTが活発に行わ れています。一人の学びをコミュニティ全体の資産へと変える、オープンな文化が根付いています。 38
集合知によるスピーディな課題解決 一人の専門家が答えるのではなく、多様なメンバーがそれぞれの知見を持ち寄ることで、 複雑な問題も迅速に解決することができます。 39
コミュニティの知見を結集したAIアシスタント 誰に聞いたらいいか分からない時には、 コミュニティに常駐するDify Studio Q&Aチャットボットが、疑問解決の第一歩をサポートします。 40
コミュニティを企業の出島に クローズドな自社内だけでは、イノベーションは生まれません。 企業にとって、Dify Studioのような外部コミュニティは、未来の才能と出会い、 リアルな課題を発見し、新たな技術やコンセプトを試すための「出島」となります。 41
5 おわりに
【10/25】 第3回 Dify Studioハッカソン LangGenius社の公式協賛のもと、第3回ハッカソンを開催します。個人での挑戦はもちろん、 課題解決を目指す企業様とのコラボレーションも心よりお待ちしております。 43
Thank you!