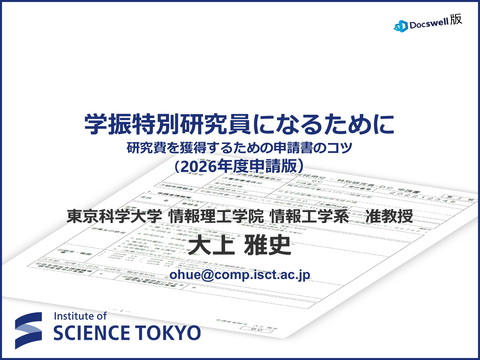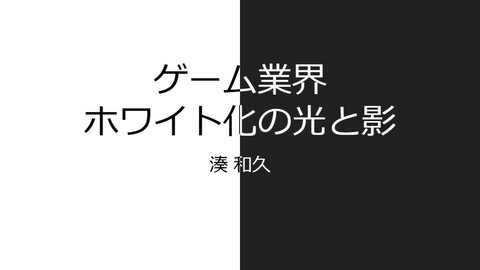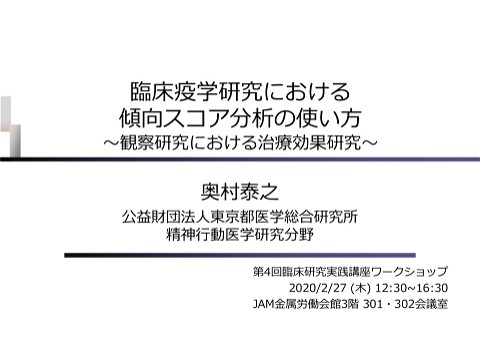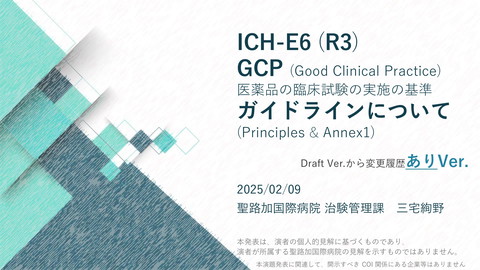20250222 公開シンポジウム 学校教育の言語と機能言語学の接続―外国につながる子どもたちの包摂を見すえて 南浦発表資料
533 Views
March 04, 25
スライド概要
2025年2月22日に行なわれた「シンポジウム 学校教育の言語と機能言語学の接続―外国につながる子どもたちの包摂を見すえて」の南浦発表資料です。
教育方法学・教科教育学という「一般的な教育」と,外国人児童生徒教育学という「特別な教育」をどちらも行っています。 このどちらもを同時に行う研究室は,日本の中ではほとんどありません。その結果,大学を含む多くの教育の場でこの両者は別々のものになってしまっています。
関連スライド
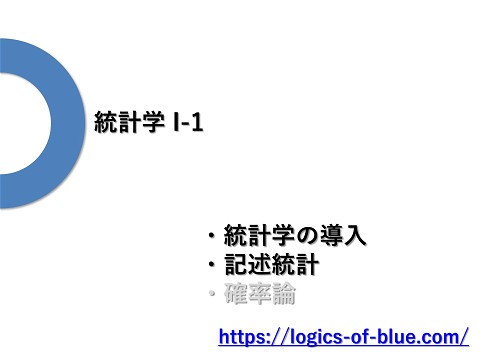
統計学I-1
 Logics of Blue
300K
Logics of Blue
300K
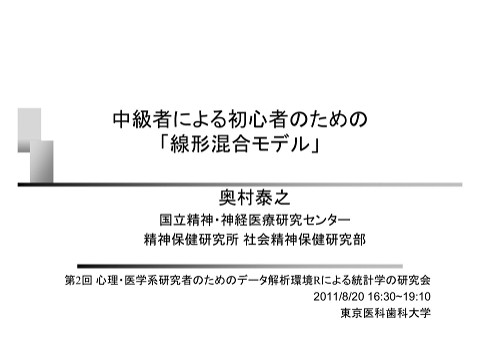
中級者による初心者のための「綿形混合モデル」
 奥村 泰之
222.4K
奥村 泰之
222.4K
各ページのテキスト
公開シンポジウム 2025.2.22 学校教育の言語と機能言語学の接続 ―外国につながる子どもたちの包摂を見すえて― 「CALPの'A' ? 」あるいは機能言語学の視点 外国人児童生徒教育を担う教師の「言語」への目を磨く 南浦涼介(広島大学)
外国人児童生徒と「言語」の関係性の研究系譜 ①学校教育で用いられる「言語」構造を簡易化するアプローチ • 「リライト」のアプローチによる教科学習への参加(松田・光元・湯川, 2009; 光 元, 2014など) ②学校教育で用いられる「言語」の分析的アプローチ • 語彙研究の方向性からの検討。例)教科の教科書に登場する語彙がどのような特性 を持っているのかを検討し,その傾向を指摘(例,池田, 2018; 田中, 2020など) • 学校で使用する学習語彙を計量的にデータベース化し,大規模コーパスをもとに総 合的日本語教科書をつくる(志村ほか, 2019など) 学校で用いられる「言語」に焦点をあてるものの 全体としては言語の構造的統語的側面に焦点がおかれており 学校のその言語の使われる社会・文化的文脈性には視点が薄い • • • • • 池田香菜子(2018)「JSL中学生の多義同士の意味・用法の知識と教科書におけるインプットの関係性 : BCCWJ『中納言』を用いて」『母語・継承語・バイリンガル教育(MHB)研究』14, pp.25-46. 志村ゆかり(2019)日本における年少者日本語教育と〈やさしい日本語〉―バイパスとしての〈やさしい日本語〉のその先にあるもの, 庵功雄・岩田一成・佐藤琢三・柳田直美(2019)『〈やさしい日 本語〉と多文化共生』(pp.317-336.)ココ出版, 田中祐輔(2020)「COSMOS : 帰国・外国人児童のためのJSL国語教科書語彙シラバスデータベース」『計量国語学』第32巻第5号, pp.277-287. 松田文子・光元聰江・湯川順子 (2009) 「JSLの子どもが在籍学級の学習活動に積極的に参加するための工夫―リライト教材を用いた『日本語による学ぶ力』の育成―」『日本語教育』142,pp.145155. 光元聰江(2014)「取り出し授業と在籍学級の授業とを結ぶ『教科書と共に使えるリライト教材』」『日本語教育』158, pp.19-35.
CALPの翻訳語としての「学習言語」の課題点 CumminsのCALP: Cognitive/Academic Language Proficiency は いかなる日本語訳であるべきか? CALP / BICSの訳の系譜 • Academic: relating to education, especially at college or university level (LONGMAN) 1980年代〜1990年代 • Cummins自身も ‘academic language’ について言及 • 「CALP」「BICS」(箕浦, 1984) しているが, それは「 (カミンズの場合とりわけ書き言葉 • 「認知・学習言語能力」「基本的対人伝達能力」 の)学校で用いられる言語」として述べており,イコール (野山, 1992; 縫部, 1993) ‘learning’の話ではない(例 Cummins, 2021)。 • 「学習言語」「生活言語」(梶田・速水, 1994) • 翻訳としても,教育学においては「教育(学び手に外在 する対象世界を教えること)」と「学習(学び手が内在 2000年代 化すること)」は伝統的には区別される。 • 「学習言語能力」「生活言語能力」の定着,その 略式としての「学習言語」「生活言語」という翻 • 日本語教育(とりわけ1980年代のSLA以降の文脈)にお 訳語 いては「教育」と「学習」が混在することが多い。 Academic=学習なのか? Cognitive=認知なのか? • • • • • • CALPを「認知」「学習」といずれも学び手に内在する用語で説明す ることで,学び手の内在的問題・欠損的言説になりやすく,外在する 「アカデミック」な言語への目線が薄くなりやすい? 梶田正巳・速水敏(1994)「日本語を母語としない子女に対する日本語の指導課程・指導方法の実践的基礎研究」科学研究費補助金 総合研究(A)03306019, 研究報告書. 縫部義憲(1993)「児童日本語教育学の構築に向けて(1)―現状と課題 : 広島県を中心に」『広島大学教育学部紀要. 第二部』42, pp.142-148. 野山広(1992)「在日外国人児童・生徒への日本語教育に対する多文化教育的一考察」『日本語教育論集』9, pp.35-66. バトラー後藤裕子(2011)『学習言語とは何か―教科学習に必要な言語能力』三省堂. 箕浦康子(1984)『子供の異文化体験―人格形成過程の心理人類学的研究』思索社. Cummins, J. (2021). Rethinking the Education of Multilingual Learners: A Critical Analysis of Theoretical Concepts. Multilingual Matters.
選択体系機能言語学(SFL)と学校教育の言語の展開① SFLの視点から学校で用いられる言語(外在的な言語)の特質を捉え,移民の子ども の教授学習への応用を探る研究の発展(Linares & Xin, 2020のレビュー) ①テキストの分析,リテラシーへの働きかけとSFL • 主として教科書などに表れた書き言葉のSFL的な分析を行い,そこにあるテクスト の特徴を子どもたちが/教師が 捉える(Achugar, Schleppegrell & OteÍza, 2007 など) ②教室のディスコースとSFL • 教室における現実のコミュニケーションの相互作用がいかなる言語選択によって構 成されているのかを分析する(Yang & Tao, 2018 など) ③言語の教授学習とSFL • 言語の機能を学び手が理解することで,学び手が多様な社会的文脈の中でコミュニ ケーションできるようにしていく(Berry, 2013 など) • • • • Achugar, M., Schleppegrell, M. & OteÍza, T. (2007). Engaging teachers in language analysis: A functional linguistics approach to reflective literacy, English Teaching: Practice and Critique. 6 (2), pp.8-24. Berry, M. (2013). The difference between formal written and informal spoken English. In L. Fontaine, Systemic functional linguistics: Exploring choice (pp. 365–383). Cambridge: Cambridge University Press. Linares, S. M. & Xin, Z.Y. (2020). Language Education and Systemic Functional Linguistics: A State-of-the-Art Review. Journal of Literature and Language Teaching. 11 (2), pp.234-249. Yang, X. & Tao, X. (2018). Comparing Discourse Behaviors of a High-Rated and a Low-Rated Chinese EFL Teacher: A Systemic Functional Perspective, The Modern Language Journal. 102 (3).. Pp.594-610.
選択体系機能言語学(SFL)と学校教育の言語の展開② 教師教育としての注目される方向もかなり多い Mickan (2007) Schall-Leckrone & McQuillan (2012) 教員養成課程の学生たちが科学の教科書や授 業の中で使われる言語の機能的な構成につい て分析的に学ぶ事例 英語を第二言語で学ぶ移民の子どもたちを念頭におい て,高等学校の歴史教育方法のコースにおいて歴史と 言語の統合的指導を念頭においた教師教育実践。この 中でアカデミックな歴史教育の言語的分析を行なう。 Accurso & Gebhard (2021)による教師教育的示唆 • 対象世界のテクスト的特性の理解:人々がどのような記号論的選択をするのか? どのような選択 肢があるのか? 異なる選択肢が互いにどのように関係し、それぞれが特定の文脈でどのように理 解されるのか? • 移民の子どもたちに対するリテラシーの育成視点の形成:学校において価値のあるジャンルの読み 書きとそのリテラシーを移民の子どもたちも身につけていけるように支えていく • 記号論的選択の社会的作用の理解:対象世界のテキスト的特性やその利用のありかたが,どのよう な社会的作用や権力構成(利益や損失など)を見通して教室空間を作り出せるようになる。 • • • Accurso, K. and Gebhard, M. (2021). SFL praxis in U.S. teacher education: a critical literature review, Language and Education, 35(5), pp.402-428. Mickan, P. (2022). Systemic Functional Linguistic Perspectives in TESOL: Curriculum Design and Text-Based Instruction. TESOL in Context , 31 (1): 7–24. Schall-Leckrone, L., and P. J. McQuillan. (2012). Preparing History teachers to Work with english Learners through a Focus on the academic Language of Historical analysis. Journal of English for Academic Purposes , 11 (3):246–266.
日本の外国人児童生徒教育研修における取り組みとその課題 日本語教育学会「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム」 例えばモデルG-3(日本語の特徴―教科書の日本語を考える)では教科の教科書の分 析活動があり,教科書の中でどのような点でつまずきやすいかを「文法」「語彙」の 面から検討している提案。 ➢ そもそもの「言語の捉え方」への言及はないため,機能的分析というよりは統語的 分析による「日本語の難しさ」に着目する流れが強調される。 ➢ 教科書の「日本語の難しさ」に対応する支援に着目することはできるが,当該のレ ジスター(言語使用域)への参加や組み直しの視点は得にくい。 教師研修において「言語の捉え方」を機能的に捉える視点を養い,具体的な言語の特 性を捉えて援用できるとりくみができないか? • 日本語教育学会(2019)『外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラム』 https://mo-mo-pro.com/modelprogram
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 外国人児童生徒に対する「読むこと・書くこと」「リテラシー」の教員研修(複数自治体) 1. 機能的に言語を捉えるということの意味 • 『もしも文豪たちがカップ焼きそばを食べたら』の事例を見てみましょ う。なぜこの人,このタイプだと,こうした文体になるのでしょうか。 そこにはどんな特徴があるでしょうか? • 関係性,媒体,言葉づかいの中にはどのような関係があるでしょうか。 2. 外国につながる子どもと学校の言語 • 「学習言語能力」を「学習における言語的特徴」から捉える • 学校の中にはどのような文体ジャンルがあるでしょうか。 3. 学校の言語の中にある機能的特徴を捉える • 実際に,「読書感想文」「理科の自由研究」「新聞の投書」「夏休み川 柳」をもとに,そこにある文体の機能的特徴を書き出しましょう(DLA 「書く」の観点を参考に) 4. 外国につながる子どもへの応用を考える • どのような応用可能性があるかを考えましょう • ただ「文体に子どもたちが合わせる」でいいのか,を考えましょう。 • 神田桂一・菊池良(2018)『もしも文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら―多彩な文体で綴る3分間の葛藤』宝島社. 機能言語的視点から言語を捉える 視点の形成 機能的特徴を学校で用いられる 多様なテクストから分析する 機能的特性を捉えながら 子どもたちへの 教育的応用を考える
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 機能言語的視点から言語を捉える視点の形成
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 機能的特徴を学校で用いられる多様なテクストから分析する 分析の観点 自治体の研修カリキュラムの関係からDLAの「書く」を参考にレジスターの中のモードの分析を行なう DLAとしてではなく,「言語に対する自分なりの気づき」(language awareness)を得るための手がかりとして 観点④「語彙」 観点①「レイアウト」 デザイン・レイアウトの特徴 観点②「構成」 ・文の「まとまり」としての特徴は? 観点⑤「文字遣い」 ・「文と文のつながり」の特徴は? 観点③「文の質」 ・使われる「文型」としての特徴は? ・その他文章表現の特徴は? もしあれば ・使われる「語彙」の特徴は? ・「文字遣い」の特徴は? 年齢の違いによる表現の違い?
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 機能的特徴を学校で用いられる多様なテクストから分析する 事例となったレジスターの参照→公開されている「優秀作品」を見る(規範的価値の分析) 読書感想文の文体 新聞投書欄の文体 理科の自由研究の文体 夏休み川柳の文体 青少年読書感想文 全国コンクール 内閣総理大臣賞の分析 全国紙の「投書」欄に ある小学生から10代の 投書事例の分析 企業の自然科学観察 コンクールの優秀作品 の分析 企業の夏休み川柳募集 の優秀作品の分析 分析の観点 自治体の研修カリキュラムの関係からDLAの「書く」を参考にレジスターの中のモードの分析を行なう DLAとしてではなく,「言語に対する自分なりの気づき」(language awareness)を得るための手がかりとして 観点④「語彙」 観点①「レイアウト」 デザイン・レイアウトの特徴 観点②「構成」 ・文の「まとまり」としての特徴は? 観点⑤「文字遣い」 ・「文と文のつながり」の特徴は? 観点③「文の質」 ・使われる「文型」としての特徴は? ・その他文章表現の特徴は? もしあれば ・使われる「語彙」の特徴は? ・「文字遣い」の特徴は? 年齢の違いによる表現の違い?
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 機能的特性を捉えながら子どもたちへの教育的応用を考える
ある自治体における外国人児童生徒教育研修における発表者の事例 機能的特性を捉えながら子どもたちへの教育的応用を考える マルチモーダルな 言葉の使用 による「教室の記号使用 の再構成」の示唆 外在的な “Academic” な言語と内在的な言葉と の関係性
SFLと外国人児童生徒教育と教師教育の関係性の中の課題 課題① 機能言語学をめぐる学術的厳密性と学校的応用性の関係をめぐる論点 選択的体系機能言語学の学問的な概念や用語の抽象度と,学校教員や支援者の 日常との距離。また,一般教師にとって「なぜここまで言葉を理解しないとい けないのか」という点への応答をどうするか?(今回はたまたま「外国人児童 生徒に対する教師」だったが) 課題② 「ジャンル理解」という言語規範の目標化をめぐる論点 「このジャンルはこのような言葉づかいをするものだから」という子どもたちへの 規範性の押しつけにもなりかねないことである。そもそも「選択的」である以上, 本来,そこには言語使用者の側の「選択」の面がある。社会的文脈に対応していく ことと,子どもに応答していくことの間をどう捉えるか? 課題③ 教師に対する学びの一貫性をめぐる論点 年に1度,あるいは数年に1度の講義とワークショップの研修が教師の知の形成 や活用に関われる隙間はそれほど大きくない。これらをどう中長期的な教師の成 長に関わるような連続性あるいは一貫性のあるプログラムとしていくか。
SFLと外国人児童生徒教育と教師教育の関係性の可能性 可能性① 教師にとっての「対象世界」と言葉の関係性の理解と指針 • 学校において子どもたちの外在にある「対象世界」を「ジャンル」という観点か ら捉え「今のこの時間にこのテーマにおいてどういう言葉を子どもたちは得てい くといいのか」についての指針を見つけ出すことができる。 • 「教え」の言語的鍛錬だけでなく,「対象世界」と「子どもの表出した言葉」と の関係性の中で言語を分析・評価していくことの言語的鑑識眼の形成へ。 可能性② 「言語的包摂の教室」としてのマルチモーダルな記号への拡張 • 「ジャンルの押しつけ」(課題②)を回避する「土俵」の視点の重要性。 • 様々な記号のテクストに子どもがいかにかかわり,「意味をつくりあげてい く」ことができるか? 記号≠言語,記号=マルチモーダルとして記号と意味 の関係を捉えることによる包摂的実践の可能性へ(→奥泉の発表への接続性) 可能性③ 「言語的包摂の学校」としてのカリキュラムへの拡張 • 機能的な言語の観点自体を,外国につながる子どもたちのものだけではなく,学 校全体の「言葉」の実践として組み直していくことが,言語的文化的な多様性の 包摂にもつながっていく(→小栁の発表への接続性)