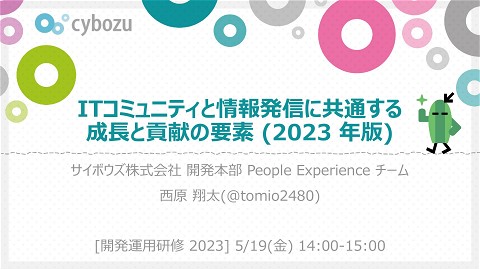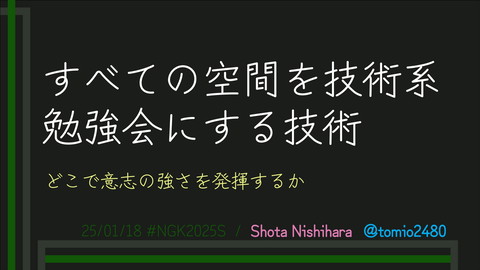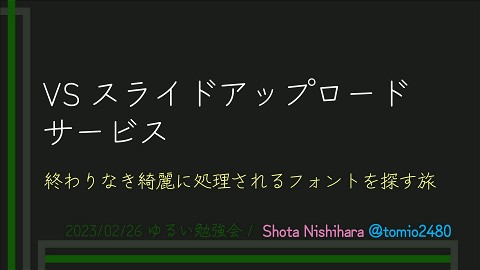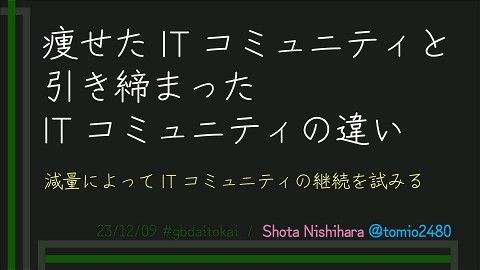実践!「テックブログを読む会」
2.3K Views
May 11, 24
スライド概要
2024-05-11(土) PHPカンファレンス香川2024 14:50-15:50 桐の間 で行ったワークショップの資料.
https://phpcon.kagawa.jp/2024/
tomio2480 です
関連スライド
各ページのテキスト
実践︕「テックブログを読む会」 ⼩さな変化の積み重ねでベースアップを図る試みを体験しよう サイボウズ株式会社 開発本部 People Experience チーム Developer Concourse Unit [#phpconkagawa] ⻄原 翔太(@tomio2480) 2024/05/11 (⼟)
サイボウズの技術情報は Cybozu Tech で ▌https://tech.cybozu.io/
$ whoami 旭川と⾼松は⾶⾏機で ⼀瞬だったよみんなきてね ▌Shota Nishihara @tomio2480 ▌サイボウズ株式会社 開発本部 People Experience チーム Developer Concourse Unit n ⾼校教諭(電)→セキュリティ⼈材育成→現職+専⾨学校講師(AI:Python基礎)→今 n 開発本部,運⽤本部,サイボウズ・ラボの⼈の発信,IT コミュニティ出没 n 流氷交差点よろしく https://soundcloud.com/cybozutech/sets/drifticecrossing n 情報処理学会 会誌編集委員 https://www.ipsj.or.jp/magazine/magazine.html ▌北海道旭川市からフルリモート n ゆるい勉強会(旭川),FuraIT(富良野),Co-KoNPILe(⼩平) に⼤体いる 🫶
地⽅異常IT勉強会に住んでいます 例) ▌1 週間 2,700 km 移動 5 連続勉強会 ▌⼩⾦井公園⻘空もくもく会 n 6/1(⼟) に開催決定︕︕︕ ▌スターリンク持参⼤雪⼭登⼭ ▌函館路⾯電⾞貸切LT⼤会(これはただの参加者) ▌#雪原駆動開発
【宣伝】 Cybozu Internship 2024 ▌エントリー受付中 n それぞれに期間が設定 されています ▌受⼊技術分野もさまざま
【宣伝】サイボウズ・ラボユース ▌各分野のエキスパートの指導を通年で受けられる制度 ▌奨励⾦⽀払いの有/無で枠が異なる ▌成果物の権利は個⼈に帰属 ▌過去のユース⽣,研究⽣との つながりも作ることができる
【宣伝】情報処理学会 – ジュニア会員制度 ▌会費無料で会員になれる制度 ▌学会誌,論⽂等にアクセス可能 ▌学会のイベントにも参加できる n 参加費がかからないなどの優遇あり
【宣伝】情報処理学会 - 技術書典16 ▌5/26(⽇) 池袋にて現地出展「あ04」 n オンラインでも書籍は購⼊可能 ▌学会誌の特集別刷を頒布 n 550 円(2 年経過したものは 0 円 ▌少しばかりのグッズ頒布もあり n T シャツ,バグ根絶 USB メモリなど
【宣伝】TechRAMEN 2024 Conference @ 旭川 ▌技術分野ごった煮のカンファレンス ▌7/26(⾦)-27(⼟) 旭川市にて開催 n 27(⼟) が本編,26(⾦)は前夜祭 n 28(⽇) に⾮公式後⽇祭アリ ▌ゲストスピーカーのみなさんは現地⼊り ▌懇親会は旭川・富良野エリアうまいもの n 参加整理券配布中
さて
テックブログを読む会とは ▌30 分の中でブログを読んで感想書いて感想戦する取り組み n note 記事にまとめてあります n https://note.com/tomio2480/n/nf909bb77b4b7 n ⼀年間継続したレポートはスライドで公開しました n https://www.docswell.com/s/tomio2480/51J367-blogreading-firstanniversary
どうやるか – 時間割 ▌00:00 集合 – 読むブログを探して,読む(いくつ読んでも OK) ▌00:08 読んだブログの感想を⼀⾏以上で書き始める(短くても⻑くても OK) ▌00:12 感想が書かれた記事を上から順に画⾯共有で選んだ⼈が⼝頭紹介 ▌00:30 中締め,残りたい⼈は勝⼿に残って雑談してもよい 今のところ機械的なタイマーは使わず 状況に応じてリードする⼈が声かけしている.
どうやるか – ツール ▌ブログをどこから⾒つけてくるか 例えば論⽂集など 読む対象の集まりを変えれば 同じやり⽅で別の何かを 読む時間にすることも可🙌 n 元々集めてくれているところを提⽰ n https://yamadashy.github.io/tech-blog-rss-feed/ n https://hatena.blog/dev n https://techplay.jp/blog n 上記以外から,⾃分で勝⼿に⾒つけてきて読みたいと思ったものを読んでいい ▌感想をどう共有するか n 社内 : kintone,社外 : HackMD
どうやるか – ツール(こんなかんじ
まずはやってみましょうか
どうやるか – 時間割(再掲) ▌00:00 集合 – 読むブログを探して,読む(いくつ読んでも OK) ▌00:08 読んだブログの感想を⼀⾏以上で書き始める(短くても⻑くても OK) ▌00:12 感想が書かれた記事を上から順に画⾯共有で選んだ⼈が⼝頭紹介 ▌00:30 中締め,残りたい⼈は勝⼿に残って雑談してもよい 今のところ機械的なタイマーは使わず,状況に応じてリードする⼈が声かけしています
事前準備 ▌参加者全員が編集可能なドキュメントを⽤意してそこでやっていきます n 今回は HackMD(ログイン必須) で進めます ▌実際,慣れてさえしまえば⽩紙スタートでもなんとかなります n Slack に専⽤チャンネルを作ってやっている会社さんもあります n https://blog.osstech.co.jp/posts/2024/02/techblog-reading/
8 分間 – ブログを探す + 読む (1) ▌ブログをどこかから探して読みます n フリーな感じのブログを読む会ではどこから⾒つけてくるかは制限していません n 今回もどこから探してもいいことにしましょうか n でも,ある程度まとまったところ(ホッテントリとか RSS 集めてるところとか)からの⽅が探す時 間が少なくなってより効果的に読めて,取り組みの充実度が上がります n ある分野について勉強してほしいときは,探す先を制限しています n 他社の開発組織に関する制度や取り組みを知るためのデータベースを作ってそこからとか n 最近の動きを知るためになるべく新しい記事から選択するとか
8 分間 – ブログを探す + 読む (2) ▌探し⽅ n 探すのに時間をかけすぎない n 偶然の出会いも楽しむ姿勢が⼤事 ▌読み⽅ n 微妙とか,難しいとか思っても,読んだことを紹介する気持ちで読み切ってみる n いろんな記事を斜め読みで渡り歩いてもよい n メモをとりながらでも OK n ちゃんと読むために調べながら深掘りしつつ読むのも OK こんなレベルの記事読んだの︖とか思われることもない,時間のなさなので気にしないでいこう
2 分間 – 感想を書きます ▌“感想” であることが重要 n 記事の要約や考察のレベルは必要ないとしています n 思ったこととか,それは君だからでしょ︖を込みで書いてよいということです ▌いっぱい書いてもよい,軽く書いて⼝頭で補⾜する前提でもよい n でもたぶん,書きすぎない⽅向で考えた⽅がいいかも n 書いてあることをトリガーに⼝頭であとで感想戦する気持ちで⾏くくらいの気持ちで ▌時間が余れば,他の⼈のところにコメントを書きに⾏くのもオツ n ⼝頭(特にオンライン)だとインタラクティブなやり取りがむずいのでチャットもオツ ここでしっかり書かないといけない︕という気持ちは全て捨てていこう.後で補えるから
20 分間 – 画⾯共有をして感想戦をしましょう (1) ▌みんなで同じ画⾯を⾒る体験が⼤事 n みんなで 1 枚の画⾯を⾒ながら,読んだ⼈の記事の感想を聞く n 話している⼈が「そのリンク先も⾯⽩い」と⾔えば,その画⾯で開いてみてもいい n 時間がなければその限りではない ▌みんなの感想が時間内におさまっていることが⼤事 n いろいろ話したくなるのは,もうそういうことなのでうまくやりましょう n よくやるのは,先にみんなの感想を聞ききってから,時間が余れば深掘りするとか n 最初から記事数が少なくていけそうだとわかれば,それぞれで深掘りしてもよい
20 分間 – 画⾯共有をして感想戦をしましょう (2) ▌画⾯共有 + 進⾏係は画⾯をみんなに⾒せて記事を開いておきましょう n タブを開いておくとその順番にやればいいだけなのでスムーズ n HackMD の感想は必要に応じて⾒るくらいで,実際はほとんど記事を⾒てる n このへんの匙加減は話している⼈とか,画⾯共有している⼈の気分による ▌ひとつひとつ,読んだ⼈に記事についての感想を話してもらいます n 進⾏係「これはどんな記事でしたか︖」→読んだ⼈「これは〜」 n 基本は読んだ⼈が⼀⼈で話していって,たまに進⾏の⼈が相槌打つくらいがいい n みんなで盛り上がると,時間内におさめるのがきつい(テキストも活⽤するとよい 感想なので「正直わからんかった」「Not for me だった」とかで終わるのもあり
おつかれさまでした
おつかれさまでした ▌通常はここで中締めとして,基本は解散とします n 時間的に余裕のある⼈は残って雑談するのもあり n ただ,しっかり中締めしないと帰りたい⼈が帰りづらくなるので締めたほうがいい ▌この時間に来れなかった⼈はテキストでの⾮同期参加も可能 n 他の⼈がどういう観点で読んだのかはテキストでもわかる n 感想戦が売りだけど,テキストで参加するのでもやらないよりは効果がある
やってみてどうでしたか︖ ▌せっかくなんで感想戦しましょうか n HackMD に今回やってみた感想を書いてから,⼝頭感想戦しましょう ▌観点は⾃由ですが,たとえばこんなことが考えられます n ⾃分の所属するコミュニティ,会社等でやるぞと思った/思わなかった理由は何か n ⾃分の所属するコミュニティ,会社等で導⼊するなら,何に重点を置くか n 単発で取り組んだ場合と習慣化された取り組みになった場合の差は何か n この取り組みを通じて,どういった能⼒のベースアップを期待できるか
ブログを読む会の肝となる設計はこれだと思っている ▌時間がない中で取り組むことによる「しかたなさ」を設計したかった n 準備時間をしっかり⽤意することは時に厳しさになる n 「これだけ時間があったのにこの質……」という悲しみを封殺するための短時間 ▌「書いてから話す」ことで話すことの満⾜度を⾼める設計をしたかった n ⾃分の意⾒や感想を⽂字化して向き合う時間が肝だと考えている n 「書く」に対して「話す」はやり直しが効かないので難しい n ⼀度やり直しが効く「書く」を経ることで,すらすら話す準備を整えられるはず
トップレベルの引き上げとブログを読む会 ▌事前準備を必要とする読書会や記事紹介時間の⽅がいいかも n ⽇常的に情報収集や学習ができる集団ならではのやり⽅がある n わざわざ集まるのだから,集まらないと難しい感想戦のみをやるみたいなほうがいい ▌上位層からのスキルトランスファーや全体のベースアップの難しさがある n どのように本や読む記事を選定し, n どういった観点で, n どれくらいの物量を, n どれくらいの時間をかけて読んでいるか が明らかになるのがブログを読む会 トップレベルを引き上げるには物⾜りないかもしれないけれど,ベースアップは期待できるはず
まとめ
まとめ ▌学びの習慣化最初の壁は「しかたなさ」と「⾔い訳」を味⽅につけられるかどうか n トップレベルの⼈たちが世の中に⾒せているアウトプットやインプットが強すぎる n いきなりそれを⽬指すから⼼が折れる n それくらいやらないと「意味ない」と思っている⼈も多いのかも ▌「まあいいか」でやらないのが普通,これを「まあいいか」でやってもらう n あのレベルまでいかないので「やらなくていいか」を封殺していく設計が必要 n 30 分なら「まあいいか」,事前準備がないなら「まあいいか」 n 感想も「これくらいでいいか」,理解できなかったけど「読んだしいいか」 やる気や権威は気まぐれに現れて難しい.怠惰と⾔い訳は常にそこにいるので簡単.
むすびに
頂の 憧る背中 遠きかな あだあだしきも 『やがて』と抜かる インチキ古語⾵五七五
頂の 憧る背中 遠きかな あだあだしきも 『やがて』と抜かる 頂点に⽴つ⼈の背中に遠くから思いこがれている ……のにも関わらず不誠実にも「そのうち」と抜かしおる インチキ古語⾵五七五
つまり
JUST
DO IT
実践︕「テックブログを読む会」 ⼩さな変化の積み重ねでベースアップを図る試みを体験しよう サイボウズ株式会社 開発本部 People Experience チーム Developer Concourse Unit [#phpconkagawa] ⻄原 翔太(@tomio2480) 2024/05/11 (⼟)