生成AI時代のテックブログの始め方
5.4K Views
November 06, 25
スライド概要
2025/11/06 「Qiita Conference 2025 Autumn」にて登壇
https://qiita.com/official-campaigns/conference/2025-autumn
闇のエンジニア/変なデジカメ開発中/ディープラーニング芸人/Raspberry Piとからあげ大好き/はてなブログ書いてます
関連スライド
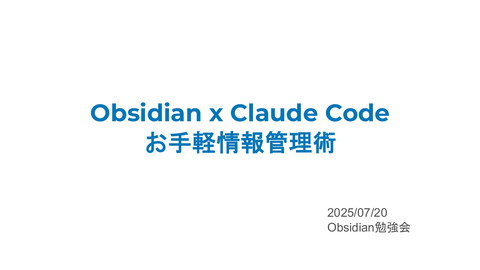
ObsidianxClaude Code情報管理術
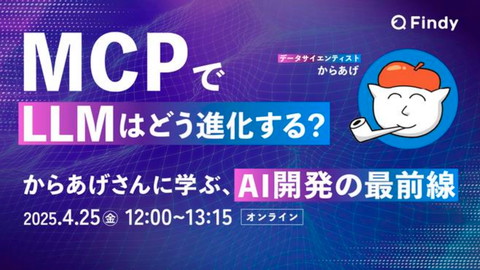
MCPでLLMはどう進化する?
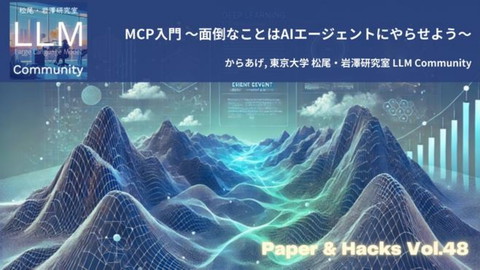
MCP入門 〜面倒なことはAIエージェントにやらせよう〜

オープンなLLMをローカルで動かす
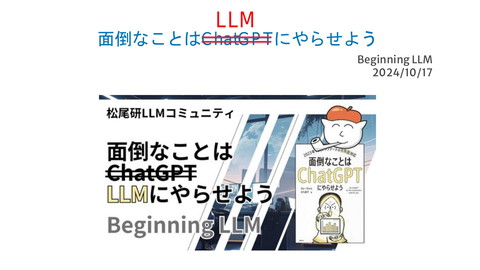
面倒なことはLLMにやらせよう
各ページのテキスト
生成AI時代のテックブログの始め方 ※アイキャッチ画像は https://qiita.com/official-campaigns/conference/2025-autumn より引用
自己紹介 名前:からあげ(本名は内緒) 職業:株式会社松尾研究所 シニアデータサイエンティスト karaage. @karaage0703 karaage0703 karaage0703 ブログ、各種SNSで情報発信しています
最初に謝罪 実は最近Qiitaに記事を書いてないです ※ Qiitaのことが嫌いになったわけではないです
本日のゴール 今日の話を聞いた人がテックブログを 始めたくなる / 書きたくなる
本日のアジェンダ - なぜテックブログを書くのか - 生成AIによるテックブログの変化 - テックブログを個人/会社ではじめる方法
本日のアジェンダ - なぜテックブログを書くのか - 生成AIによるテックブログの変化 - テックブログを個人/会社ではじめる方法
いままでテックブログを書いた量 項目 記事数 いいね数 はてなブログ 500記事以上 測定不能 Qiita 260 12,588 Zenn 74 12,018 結構たくさん書いてます
自分のブログの歴史 年代 カテゴリ 内容 〜2010年代 ホームページ時代 ほぼ日記 2010年〜2015年 ハードウェア時代 徐々に技術的な内容を書 き出す 2015〜2025年 ソフト・AI時代 テックブログを本格的に 書き出す ブログ自体は長年やっていましたが テックブログを本格的にやっているのはここ10年くらい
ハードウェア時代 加速度センサを使ったエアドラム 回路図 技術的な記事を書き始める ハードウェアよりのことを結構書いていた
ソフトウェア・AI時代 Chainerによる画像認識 2015年くらいからソフト・AI関係の内容が増え始める このあたりからQiitaやZennを使うようになっていく
テックブログをやってよかったこと ・自分の知識の整理になる ・忘れたとき検索したら出てきて便利 ・人に見られるという意識で整理して書くようになる ・文章を書くのが速くなる/多少ましになる ・昔の記事みると「これはひどい」となる ・可能性が広がる よかったことは色々ある 個人的に良いと思うのは可能性が広がる点
テックブログから広がる可能性 ・勉強会/イベント登壇 ・書籍執筆 ・キャリア
勉強会・イベント登壇 Google勉強会イベント 参加人数 200人超 Findy様イベント 参加登録人数 2700人 PyCon mini Shizuoka 2020 キーノートスピーカー 松尾研LLMコミュニティイベント 参加登録人数 1800人 キーノートスピーチ、数千人が参加するイベント等 もちろん今回のQiita Conferenceもその一つ
書籍執筆 ブログ書ける人 = 文章書ける = 本も書けるという考えで 出版社の人に声をかけられる(コネが大事)
キャリア ・食べ物の名前でも、結構DMでお誘いいただく ・基本的にはポジティブな影響(と信じたい) ・人と人とのつながりがキャリアを作っている テックブログを中心とした発信が キャリアに与えている影響は大きいと感じている
テックブログを書くデメリット ・炎上しそう テックブログを地道にやって炎上することはそうそうない たまに変なこと言う人はいるけど、あんまり気にしてない 感覚が麻痺しているという噂はある(あまりに繊細だとだめかも) ・大変そう 息抜きで書いているので特に大変でもない 後になって気づいたけど、普通はそうじゃないらしい ・コスパ悪そう それはそう(効果出るまで時間かかる) 個人的には メリット >> デメリット 書くのが辛くないなら書くのがオススメ
本日のアジェンダ - なぜテックブログを書くのか - 生成AIによるテックブログの変化 - テックブログを個人/会社ではじめる方法
生成AIがテックブログに与える影響 ・書く内容 ・書き方 ・情報の信頼性 3つの観点で考えてみる
書く内容の変化 生成AI以前 生成AI以後 ・検索したけど出てこなかったこと ・なくなった ・検索結果に満足できなかったこと ・生成結果に満足できなかったこと ・自分が経験したこと ・自分が経験したこと 検索で出てこないことはなくなった(生成できる) それ以外はそこまで変わらない気がしている
ブログ執筆タスクでの生成AI活用 ・たたき台を書かせる 自分で90%くらいは修正することになるが、気楽に書ける たまに自分にはない視点が得られる ・チェックをさせる 文章のチェック。客観的に文章を見て欲しいときに ・過去のブログ記事を宣伝する 今まで面倒でやっていなかったこと 面倒なことは生成AIにやらせよう 時短ではなく同じ時間でクオリティを上げるため 新しい価値を出すために使っている
生成AI活用で重要になってくる要素 生成AIのインタビューに答えると、過去の自分のドキュメントを参照して たたき台を書いてくれる仕組みをつくっている。 データをAIが使える形で蓄積することが大事
宣伝(SNS投稿) https://github.com/karaage0703/ sns-post-plugin もちろんQiitaも対応! 各ブログサービスに対応した MCPサーバーを開発 LLMとブログサービスに対応したMCPサーバを使って過去記事を投稿 意外と読んでもらえる。重要なことは何度もSNSに投稿した方がよい
情報の信頼性
生成AIのハルシネーション ハルシネーションとその対策方法について より引用し一部改変 生成AIのハルシネーションを5つに分類できる 特にやっかいなのが、ありもしないことを「捏造」するところ
情報の信頼性 参考:オライリー・ジャパンにおける翻訳書の制作体制の変化と「もうすぐ消滅するという人間の翻訳について」 オライリーさんの書籍の翻訳がAIになったことが話題になった 監修の役割は残っている。今後情報の担保がより重要になっていくかも
生成AIの書く文章が人を超越した未来 生成AIが信頼性含めて人を超えたら人は文章を書かなくなるのか? ソロカル 「絶滅メディア博物館」にて撮影したものを一部加工 AlphaGoと李世ドル対局の盤面 AlphaGo Wikipediaより引用 書き方や書く内容は変わっても 人がAIと共存して文章を生み出し続ける未来はあり得るはず
本日のアジェンダ - なぜテックブログを書くのか - 生成AIによるテックブログの変化 - テックブログを個人/会社ではじめる方法
個人でテックブログをはじめる方法 自分が使ったことのあるブログサービス どれでもいいのでまだやってない人は 好きなサービスで今日からはじめましょう
会社でテックブログをするメリット 技術広報の役割を定義してみた 2023年夏 (メルカリ)より引用 長期的には色々効果あると言われているけど 短期的には効果みえづらく測定も難しい
会社でテックブログをはじめる条件 ・意思決定者のテックブログへの理解 ・テックブログを書いてくれるメンバー ・テックブログを推進する人 情報発信というカルチャーへの理解が組織に必要 組織によっては向いてない場合もあるので 無理して会社でやらず個人でやる選択肢もある
松尾研究所テックブログ 2024年2月開始 https://zenn.dev/p/mkj みんなフォローしてね(Qiitaでなくてすみません)
会社でテックブログを続ける方法 ・運用ルール作成 ・記事のネタづくり ・イベント
ガイドライン テックブログ投稿に必要な情報を全て記載して アップデートし続けている(現在1万文字くらい)
レビュー体制 ・Zenn Publication Proのレビュー機能を活用 Zennのシステム上でGitHubのように手軽にレビュー AIでのレビュー機能も最近付いた ・必ず投稿前にレビュワー2人以上の承認を受ける 広報チェックは1年実施した結果、必要時のみとした ・レビュー観点もガイドラインに記載 情報の質の担保・炎上防止 技術的なディスカッションで技術力底上げ テックブログのレビューは会社でテックブログを やるからこそできる貴重な機会
記事のネタ作り 会社のSlackのキーボード自慢の話題をきっかけに GitHubのレビューでふと出た知見をきっかけに 会社のSlackでテックブログになりそうなネタを拾い続けて テックブログにしてしまうテックブログおじさんになる
アドベントカレンダーイベント 松尾研究所でのAdvent Calendarの 始め方と振り返り アドベントカレンダー。2024年は平日完走! 2025年も多分やります!
会社でテックブログをはじめて出た結果 テックブログきっかけで出版社から声がかかる 会社の同僚と3人で執筆・出版へ!!
本日のまとめ - なぜテックブログを書くのか - 生成AIによるテックブログの変化 - テックブログを個人/会社ではじめる方法
テックブログを書こう!!
ご清聴ありがとう ございました
